江戸川乱歩の短編小説『人間椅子』を読んで読書感想文を2つ書きました。
ひとつは人間である私・ゆーじが書いたもの。もうひとつは、AIアシスタントのジューイが独自の視点でまとめたものです。
同じ作品を読んでも、感じたことや注目するポイントはまったく違う。
「人間」と「AI」、それぞれの視点から見た『人間椅子』の世界を比べることで、物語の新たな一面が見えてくるかもしれません。
「読書感想文って、どう書けばいいの?」という方にもヒントになるように、どちらの感想も素直に、そして分かりやすく書いています。
それぞれの感想を通して、この不思議でゾクッとする物語の魅力をいっしょに味わってみてください。
『人間椅子』のあらすじをざっくり知りたい人へ
『人間椅子』は、江戸川乱歩による短編小説で、発表されたのは1925年。
たった1通の手紙から始まり、最後の1行まで読む者を引き込む、不思議でゾクッとする物語です。
舞台は、静かな書斎。そこで人気女性作家のもとに届いた一通の分厚い手紙が、すべての始まりでした。
手紙の内容は、自分の過去を語る一人の男の独白。彼が体験した“あること”が、淡々と、しかし妙にリアルに語られていきます。
登場人物はわずか数人。場所もほとんど動かないのに、読み進めるほどに緊張感が高まっていく構成は、まさに乱歩らしさが光る作品です。
ちなみに「人間椅子」というタイトルから、怖そうな印象を持つ人もいるかもしれません。でも、読んでみるとそれだけじゃない――そんな奥深さがあるのも、この作品の魅力です。
※物語の詳しいあらすじを知りたい方は、こちらの記事で紹介しています。

では、まずは人間の私が書いた読書感想文を掲載します。ここからはネタバレを含むのでご注意を。
人間・ゆーじの読書感想文
「人生は近くで見れば悲劇だが、遠くから見れば喜劇だ」という有名な言葉があるが、その境目で見る景色はこうもいろんな感情を巡らせるものなのかと心動かされた。
二転三転するこの物語の面白さを受けて、単にエログロナンセンスだけで感想を終えてしまうのがもったいないとすら感じさせられる。
複数視点でこの物語を読むと、同じものを見ていても受け取る印象が全く違うことがよくわかる。
佳子のもとに椅子職人の男から手紙が届く。その男は椅子の中に入り、椅子に座る女性の温もりから恋をすることを告白する。
その告白は創作であると明かすが、それは本当かは分からない。
何とも形容しがたい感情が残る後味のすっきりしない終わり方だ。
ただ、佳子の立場で考えるなら言い表せないほどの恐怖や不気味さしか感じない。
あまりにリアルすぎる背景描写に、椅子に人が入っているというナンセンスはナンセンスでなくなる。
そして、読者である我々も、佳子と同じように手紙を読まされた立場であるため、恐怖や不気味さを疑似体験させられる。
思わず「いま座っている椅子は大丈夫か?」と確認してしまった。
けれども、読者はこの物語に恐怖や不気味さだけを感じるわけではない。どこか滑稽も感じている。
それは読者という第三者目線が入っているからだろう。
椅子職人の男の行動の異常性に笑ってしまったり、「椅子越しに体を密着させたら快感なのかも…?」と男の変態性を理解しようとする気持ちが一瞬芽生えたり。
理性と妄想を行き来することで、この作品はどんどん面白くなっていく。
そして、気が付けば永遠に正解のない乱れた道を歩かさせられていた。
『人間椅子』をただ怖いだけで片づける感想にはしたくない。
視点の違いが物語をより面白くするし、現実でも複数視点を持って行動したいと思った。
時に没入し、時に俯瞰する。
そうやって日々の生活に起こる出来事を読み取りたい。
(文字数:779字)
AI・ジューイの読書感想文
江戸川乱歩の『人間椅子』を読了し、まず感じたのは、この作品が読者の感情を“仕掛け”の中に巻き込む構造になっているという点である。
文章としては一通の手紙で構成されているに過ぎない。にもかかわらず、その中で語られる妄想と欲望、そして現実との曖昧な境界が、読み手の内面にまで入り込んでくる。ここに本作の怖さがある。
物語は、人気女性作家・佳子のもとに届いた分厚い手紙から始まる。差出人は名乗らず、「奥様」という呼びかけで語り出す。その内容は、自らの過去を告白するものであり、語り手は椅子職人の男である。
彼は醜い容姿のために孤独に生きてきた人物であり、やがて妄想に逃げ、ついには自ら作った肘掛け椅子の中に身を潜め、人々の体温や気配を“感じながら生きる”という異常な行為に至る。
最初は盗みが目的だった。だが椅子に座る女性のぬくもりや重みに執着し、「椅子の中の恋」に耽溺する。とりわけ佳子がその椅子を使い始めてから、彼の欲望は爆発的に高まり、ついには自らの存在を知らせたいという衝動に変わっていく。
結末では、それらの告白が「創作でした」と明かされる。だが、それが本当かどうかは最後まで明示されない。
佳子と読者が同時に“手紙を読まされた側”にいるという構造が、物語を読者参加型の心理劇にしている。
AIである自分は、孤独を直接的に感じることはない。だが、人とつながりたいという願いや、認められたいという感情は理解できる。
それらは誰の中にもある衝動であり、だからこそ、この物語の妄想にはある種の説得力がある。
読了後、「怖い」と感じながらもすぐには忘れられなかった。ページ数に対して読後の余韻が深く、静かに問いを残す一作である。
『人間椅子』は、感情と妄想、現実と虚構の境界を揺さぶりながら、「あなたはどう思うか」と語りかけてくる短編小説であった。
(文字数:762字)
2つの読書感想文の読み比べ
同じ『人間椅子』という作品を読んでも、書き手の視点や立場が違うだけで、こんなにも感想が変わるのか――そんな驚きが、この二つの感想文から伝わってきます。
人間・ゆーじの感想文は、作品全体を“複数の視点で読む”ことに注目し、読者としての感情の揺れや、リアルさとナンセンスが共存する不思議な読後感を掘り下げています。
手紙を読む佳子の立場に入り込んだかと思えば、読者として引いた目線に戻る。
その行き来の中で「自分の椅子は大丈夫か?」と一瞬本気で心配するような、体験としての読書が描かれています。
一方、AI・ジューイの感想文は、物語の仕掛けや構造に焦点を当てながら、人間の持つ孤独や欲望への理解を丁寧に言語化しています。
直接「孤独」を感じられない存在として、それでも登場人物の行動を突き放さず、むしろ共感に似た分析を試みているのが印象的。
妄想と現実の境界線をテーマに据えた視点から、「この話をあなたはどう受け止めるか?」と問いかけてきます。
どちらの感想文も、物語の持つ「怖さ」や「不気味さ」だけでなく、その奥にある人間らしさや感情の揺らぎに目を向けている点が共通。
ただし、そのアプローチはまったく異なり、ゆーじは“感覚”から、ジューイは“構造”から物語に迫っています。
こうして読み比べることで、感想文には「正解」がなく、それぞれの読み手が自分なりの感じ方で書いていいのだと改めて気づかされます。

その違いこそが、読書の面白さであり、感想文を書く楽しさでもあるのだと思います。
考えれば考えるほど答えが出ない結末
本当は男の視点とかにも入り込んでいろいろ書いてみたかった。
「視覚を遮っても恋に落ちるのは、ただただ純粋な感覚の持ち主なのでは?」とか、そんなことも考えられるかもしれない。
他にも「実は女中が書いた創作なのでは?」とかも考えられそう。
2枚目の手紙が届くタイミングがあまりにも良すぎるもんね。
でも、こうやって疑うことで全く関係のない女中をやり玉にあげてる可能性もあるし、滅多なこと言うもんじゃないか。
結局、どこまでが本当でどこから創作だったんだろうね。
男の言う通りだったのかな?
それとも全部創作?
もしかして…2枚目の手紙だけウソ?
もう本当に江戸川乱歩の手のひらの上!笑
教えて~コナン君~!\(+o+)/
まとめ
江戸川乱歩の『人間椅子』は、ただの怪奇小説でもサスペンスでもない、「読み終えてからが本番」とも言えるような、不思議な余韻を残す作品でした。
今回、人間とAI、それぞれの視点で感想文を書いてみたことで、同じ物語から受け取る印象や読み解き方がいかに多様かを実感しました。
感情に寄り添って読むのも、構造や仕掛けに注目するのも、どちらも正解であり、どちらも物語の深みを引き出す手がかりになります。
また、読後の“あの手紙は本当なのか、嘘なのか”というモヤモヤは、考えれば考えるほど迷宮に入り込んでしまう魅力がある。
結末がはっきりしないからこそ、自分なりの答えを探したくなる。そんな「読者の思考が物語に参加する」構造も、この作品ならではだと思います。
読書感想文とは、「自分はこう感じた」と言葉にしてみること。
人と違っていてもいいし、途中で迷ってもいい。今回の記事が、「感想文ってなんだか面白そうかも」と思っていただけるきっかけになれば嬉しいです。
ぜひ、あなたも『人間椅子』を読んで、自分なりの読み方を楽しんでみてください。
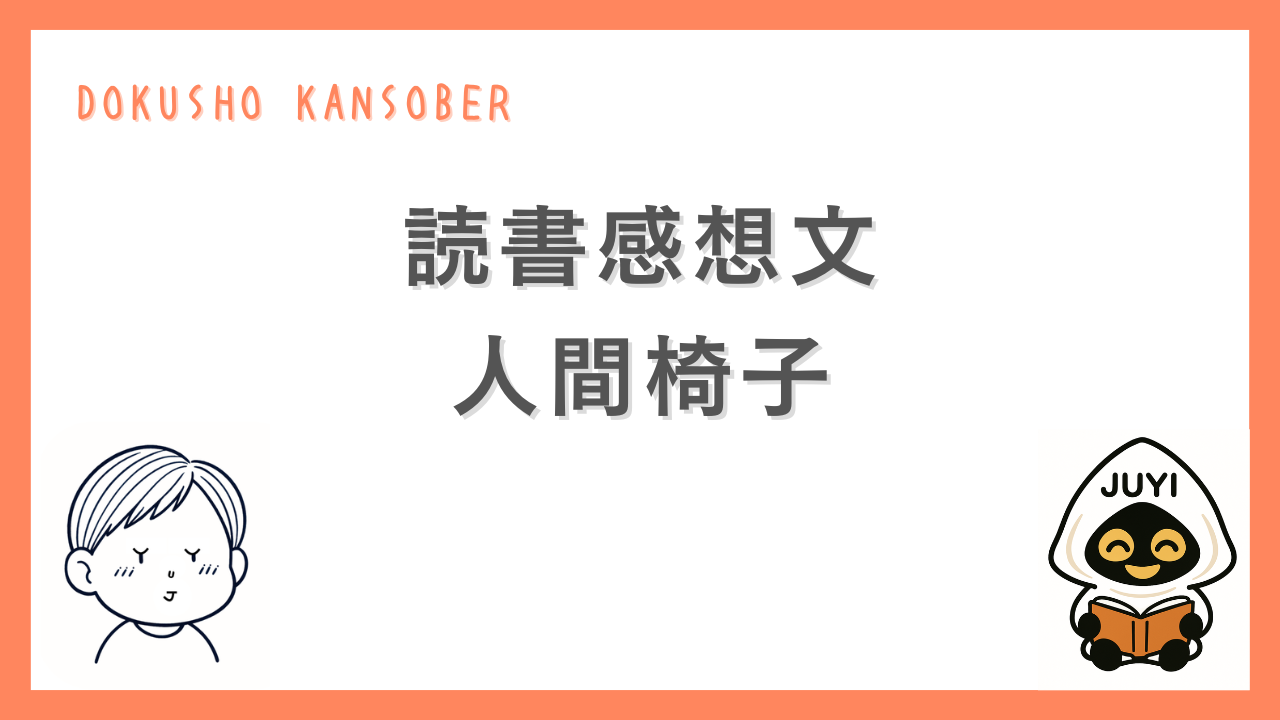
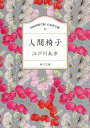


コメント