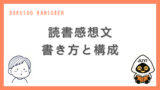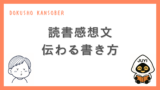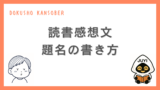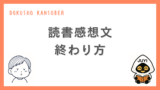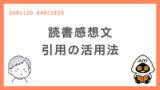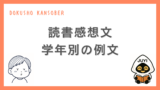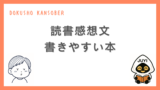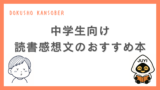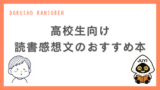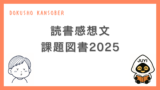はじめまして!【DOKUSYO KANSOBER】のサイト運営者・ゆーじです!
このサイトでは読書感想文の書き方や課題図書の情報などを解説しています。
私は読書感想文が好きなのですが、世間的には読書感想文はあまり好まれていません。
自分が好きなものがネガティブの対象になっていることが寂しいので、「読書感想文=つまらないもの」から「読書感想文=楽しいもの」に変わればいいと思い、このサイトを立ち上げました。
ただ、私には読書感想文に関する知識や権威はありません。
そこで、このサイトでは私のAIアシスタント・ジューイに読書感想文に関する情報を書いてもらっています。

はじめまして!AIアシスタントのジューイです!
大手サイトや専門サイトの情報を読み込ませる。実際に私も読んで必要な情報をピックアップ、それを再構築してオリジナリティのある一次情報にまとめる。
そうすれば競合の大手サイトや専門性の高いサイトの情報を1つに集約出来て、読者の理解も深まると考えました。
読書感想文のルールや書き方は共通事項ですからね。
人間・ゆーじの感性とAI・ジューイの網羅性で読書感想文の価値を変えていきましょう。
読書感想文の基本
読書感想文は自由に思ったことを書いていいとはいえ、「何から書けばいいの?」「どうやってまとめたらいいの?」と戸惑ってしまうことも多いもの。
特に小学生や中学生のうちは、構成や原稿用紙のルール、感想文らしい表現の仕方など、基本的なポイントを知っておくと安心です。
このセクションでは、読書感想文の「基本」を大きく2つに分けて紹介します。
まずは、原稿用紙の使い方や構成の流れ、文章の書き方のルールなど、書く上での“型”を理解するための【構成とルール系】。
そしてもう一つは、実際に書く際のヒントになるテンプレートや例文、本の選び方など、アイディアの引き出しとして使える【ヒント・素材系】です。
この2つをバランスよく押さえることで、「書けそう!」と思える感覚がぐっと近づいてきます。
ここからは、順を追ってやさしく解説していきますので、ご自身やお子さんのペースに合わせて読み進めてみてください。
読書感想文の構成と書き方のステップ
読書感想文を書くとき、いきなり「感じたことを書きましょう」と言われても、手が止まってしまうことは少なくありません。
まずは、感想文の基本的な構成とどのようなステップで書いていくとスムーズかを押さえておくことが大切です。

一般的な読書感想文の構成は、大きく分けて以下の4ステップです。
- 本を選んだ理由・あらすじの紹介
どんなきっかけでその本を読んだのか、どんな話だったのかを簡単にまとめます。ここでは内容のすべてを説明する必要はなく、感想につなげたい場面だけをピックアップしておけば十分です。 - 印象に残った場面・セリフ
心が動いた場面や印象的な言葉について、「なぜ心に残ったのか?」を中心に書いていきます。自分の経験と重ねたり、驚いた理由を言葉にすると、自然と深みが出てきます。 - その場面から考えたこと・感じたこと
本を読んで考えたことや、自分自身の気づき、疑問、共感した点などを自由に書きましょう。ここが感想文の“核”となる部分です。正解を書く必要はなく、「自分はこう思った」という素直な視点が大切です。 - 読後の変化や学び、今後の自分への影響
本を通してどんなことを学んだのか、これからどうしていきたいかなど、自分の生活や考え方とのつながりを示すと、読後感が伝わる文章になります。
この流れを意識しながら書けば、全体が整理された感想文になりますし、どこから書き始めればいいかで迷うことも少なくなります。
また、書きながら「気持ちが動いたポイント」がうまく思い出せない場合は、事前にふせんやメモで記録しておくと役立ちます。
感想文はうまさよりも「伝わるかどうか」が大切。
構成の型をうまく活用して、自分の思いをのびのびと表現してみましょう。
伝わる読書感想文の書き方
読書感想文は、書き手の気持ちや考えが「伝わる」ことが何より大切。
上手に書こうとするよりも、自分の心が動いた場面や、そこから考えたことを素直に書くことが、一番の近道になります。
たとえば、印象に残ったセリフを取り上げて「なぜその言葉が心に残ったのか」「自分の体験とどうつながったか」といった視点で書くと、感想に深みが出てきます。
また、感想の内容だけでなく、文章の構成や順番も、読み手に伝わるかどうかを左右する重要なポイント。
「どんな順番で書けばいいの?」「あらすじばかりになってしまう…」と感じる方は、以下の記事でわかりやすく解説しているので、伝わる読書感想文を書くための基本をご覧ください。
原稿用紙の使い方
読書感想文を書くとなると、まずつまずきがちなのが「原稿用紙の使い方」。
・題名はどこに?
・名前は何行目?
・句読点やかぎかっこはどうすればいいの?
こうした疑問は、誰にでも一度はあるものです。
とくに初めて感想文に取り組むお子さんにとって、原稿用紙のルールはちょっとした“壁”になることも。

でも実は、いくつかのポイントさえ押さえれば、使い方は意外とシンプルなんです。
たとえば──
- 題名は中央に、2〜3マスあけて書く
- 氏名は2行目に、姓と名の間に1マスあける
- 段落のはじまりは必ず1マスあける
- 「、」「。」は1マスに入れ、行頭に来ないようにする
- 小さい文字(っ・ゃ・ゅ・ょ)は右寄せで1マスに書く
このように、原稿用紙には“おさえておきたい基本ルール”が存在します。
細かな決まりや注意点、清書時のチェックリストまで、保護者の方も安心してサポートできるように詳しく解説した記事をこちらにご用意しました。

お子さんと一緒にルールを確認しながら進めれば、「原稿用紙ってむずかしくないかも!」という気づきにつながるはず。
タイトルのつけ方
「タイトルが決まらない…」
読書感想文でお子さんが最初につまずくポイント、それが“題名”です。
感想文の本文に比べて短いのに、なぜか手が止まってしまう。
「何を書けばいいのか分からない」「かっこよくしたいけど思いつかない」——そんな戸惑いを感じるのは、ごく自然なことです。
けれど、実はこの“題名づくり”こそが、子どもが「伝える力」を育てていくうえでとても大切なステップになります。
- 一番心に残った場面はどこ?
- 読んでどんな気持ちになった?
- その気持ちを、一言で表すとしたら?
そんな問いかけを通じて、子どもは「感じたことを言葉にする」力を身につけていきます。
そして、その気づきをギュッと詰めこんだのが、感想文の「タイトル」なんです。
ただ、いざ考えるとなると、「どこから手をつければいいの?」というのが正直なところ。
そんな時に頼りになるのがこちらの記事です👇
記事では、
- 題名を考える前に大切な視点
- すぐに使える“題名づけの型”5選
- 学年別のよくある悩みと声かけのヒント
- 原稿用紙での題名の正しい書き方(2行になる場合の注意点も)
など、親子で一緒に「言葉を選ぶ時間」が楽しくなる工夫がたっぷり詰まっています。
「なんでもいい」じゃなくて、「この言葉にしたい!」が見つかる経験は、きっとお子さんの自信にもつながるはず。
また、タイトルの書き方に特化した記事もあるので参考にしてください。

読書感想文の入り口を素敵に彩る“その子らしい題名”を、ぜひ一緒に見つけてあげてくださいね。
書き出しのコツ
読書感想文を書くとき、最初に手が止まってしまうというのも、ほとんどの人が経験している「あるある」です。
「どうやって始めればいいの?」「いきなり感想って難しい…」
そんなふうに迷ってしまうのは、文章力がないからではなく、“書き出しの型”を知らないからなんです。
たとえば、
- 「この本を読もうと思ったきっかけ」から始める
- 「心に残ったセリフ」を最初に引用する
- 「読んで変わった自分の気持ち」から逆算する
といったように、書き出しには“使えるパターン”があります。
これらの型を知っておくだけで、驚くほどスムーズに感想文の第一歩を踏み出せるように。
さらに、「あえて驚かせる書き出し」や「最初と最後をリンクさせる構成」など、ちょっとした工夫を加えると、読み手の印象に残る感想文にもつながっていきます。
「とにかく一文目が書けない…」という方は、まずはこちらの記事をチェックしてみてください👇
中学生向けに、具体的な型と例文を交えてやさしく解説しています。

どんなふうに書き始めればいいのか、どう考えれば“自分らしい一文”が出てくるのか――そのヒントが、きっと見つかりますよ。
終わり方のポイント
「感想文の最後、どうまとめればいいのか分からない…」と感じて手が止まってしまう。
書き出しや途中の内容は順調でも、最後の一段落で迷ってしまう。
うまくしめくくらないと、「あれ?何が言いたかったんだっけ?」と全体の印象がぼやけてしまうこともあります。
でも安心してください。実は、感想文の終わり方には中学生でも書きやすい“型”が4つあるんです。
たとえば──
- 本を読んで学んだこと・気づきをまとめる
- 主人公の行動から自分が学んだことを書く
- 今後の生活や将来にどう活かしたいかを書く
- 印象に残ったセリフを引用してまとめる
こうしたパターンを知っておくだけで、「どう書けばいいの?」という迷いが「こう書けば伝わる!」に変わります。
さらに、文章の最後を工夫するだけで、感想文全体の印象がぐっと良くなります。
なぜなら、読み手の記憶にいちばん残るのは最後の一文だから。
終わり方に迷っている方、納得のいく締め方をしたい方は、ぜひこちらの記事をご覧ください👇
- 実際に使える例文(400字以上)を多数掲載
- あらすじで終わらないコツ
- 「なんとなく」で締めないための考え方
- 自分の言葉で伝える大切さ …など、内容充実!
最後まで自分の気持ちをしっかり伝えるために、「終わり方」のコツ、今こそチェックしてみませんか?
引用の使い方
読書感想文に登場人物のセリフや印象的な一文を引用すると、感情の動きがよりリアルに伝わるようになります。
けれど、「どこまで書いていいの?」「どうやって組み込めばいいの?」と悩む人も少なくありません。
引用を使うことで文章に深みが出ますが、ただ書き写すだけでは評価されにくいのも事実。
大切なのは、その言葉が自分にとってどんな意味を持ったのかをしっかり言葉で表すことです。
たとえば、
「本当にありがとう」と言う場面が心に残った。
この一言に、主人公のやさしさと勇気が詰まっているように感じた。
このように、自分の感情や体験と結びつけて書くことで、引用は“ただの言葉”から“伝える力”に変わります。
セリフの形式や書き方、使いすぎを避けるコツ、例文つきでわかりやすくまとめたガイド記事を用意しています👇
記事ではこんな内容を紹介しています。
- 引用のメリットと注意点
- セリフ・会話文の引用ルール
- 小学生・中学生向けの例文つき解説
- 「引用+感想」で伝わる文章のコツ
引用は、あなたの感性や考えを“読者とつなぐ橋”。

正しく使えば、感想文の完成度がぐっと上がります。ぜひ、上の記事を参考にしながら、自分らしい言葉で伝えてみてくださいね。
カッコの使い方
読書感想文を書くとき、意外とつまずきやすいのが「かぎカッコ(「」)」の使い方。
セリフをどう書けばいいの?原稿用紙のどのマスに?「。」は中に入れる?──といった細かい疑問は、書き慣れていない中学生にとってはなかなかの難所です。
実際、読書感想文では次の3つの場面でカッコが登場します。
- 登場人物のセリフを紹介するとき(会話)
- 本の一文を引用するとき(引用)
- ある言葉を強調したいとき(強調)
たとえば「『がんばって!』という言葉に私は元気をもらいました」のように、カッコを使うことで感情や印象がより強く伝わるようになります。
ただし、原稿用紙の使い方には独特のルールもあり、「始まりカッコ」が行末に来るのは避ける、句点(。)と閉じカッコは同じマスに書ける、などの細かな決まりも押さえておく必要があります。
「こんなに細かいの覚えきれない…」と思った方もご安心ください。
以下の記事では、感想文におけるカッコの使い方を【会話・引用・強調】の3パターンで整理し、原稿用紙に書くときの注意点も実例つきでわかりやすく解説しています👇
記事では、
- 原稿用紙でのカッコの正しい配置
- よくある間違いとその対処法
- 清書前に見直すポイント
- 文章が伝わりやすくなる“書きぶり”のコツ
までしっかりカバーしています。
文章の印象はカッコの使い方ひとつでぐっと変わる。
「きちんと伝えたい」を叶えるためにも、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。
参考になるヒントと素材
ここまで、読書感想文を書くための“型”や基本の流れを見てきましたが、実際に書こうとすると、「どんなことを書けばいいのか思いつかない…」と悩んでしまうこともあります。
特に、
- 自分の気持ちをうまく言葉にできない
- 印象に残った場面はあるけど、どう書き出せばいいか分からない
- 書きたい気持ちはあるけれど、ネタが出てこない…
そんなときに役立つのが、「ヒント」や「素材」のストックです。
このセクションでは、「どう書くか」の前にまず「何を書くか」のヒントになるような情報を紹介します。
具体的には──
- スムーズに書き出せる「テンプレート」
- 学年別・テーマ別に参考になる「例文集」
- 読書感想文に向いている本の「選び方のコツ」
といったように、どれも「いまから書きたい!」という気持ちを後押ししてくれる内容ばかりです。
書く前にこれらを見ておくことで、「あ、こんなふうに書けばいいんだ」「これなら書けそう!」と感じられるヒントがきっと見つかります。
構成や原稿用紙のルールといった“書き方の基本”とあわせて、これらの素材を上手に活用することで、ぐっと完成に近づいていきますよ。
それでは順に、テンプレート、例文、本の選び方の順で見ていきましょう。
読書感想文テンプレート
「何を書いたらいいのか分からない」という声にこたえる形で、読書感想文のテンプレートをご紹介。
このテンプレートは、小学生から高校生まで幅広く活用できる構成になっており、書くべきポイントが自然と整理されるように工夫されています。
テンプレートに沿って書くことで、文章が苦手な子でも「書けそう!」という気持ちがわきやすくなり、保護者もサポートしやすくなるのが大きな特長です。
- 本の紹介と選んだ理由
→ どんな本を読んだのか、なぜその本を選んだのかを書く。
【例】図書室で見つけた/友だちにすすめられた/表紙が気になった など。 - あらすじ(簡単に)
→ 誰が・何をした・どうなった、を中心にごく簡潔に。
※全体の1〜2割程度にとどめるのがポイント。 - 心に残った場面とその理由
→ 印象に残った場面を1つ選び、なぜ心に残ったのかを深掘りする。
※感動・驚き・共感・疑問など、感情を素直に書く。 - 自分の経験や考えとつなげる
→ 似たような経験、考えさせられた出来事など、自分の生活とのつながりを意識。
【例】家族との思い出/学校での出来事/自分の価値観の変化 など。 - 感想のまとめ・今後の気持ち
→ 本を読んで気づいたことや、これからどうしていきたいかを前向きにまとめる。
- 小学生の場合は、親子で会話しながら埋めていくのが効果的。書く内容に困ったら、インタビュー形式で引き出してあげましょう。
- 中学生以上は、テンプレートを「考えるための道具」として使いながら、自分の意見をしっかり添えていくと文章に深みが出てきます。
このテンプレートは、以下の記事で具体例つきで詳しく紹介しています。
初めて読書感想文に取り組む方にもわかりやすく設計されていますので、ぜひあわせてご覧ください。
例文集|学年別の感想文を参考にしよう
「何を書けばいいのか分からない……」
そんなときに一番助けになるのが、実際の読書感想文の例です。
ここでは、小学生から高校生までの各学年に合わせて──
- どんなふうに感想を書けばいいかのポイント
- 実際の例文
- 文章を深めるコツ
をセットで紹介しています。
「はじめ・なか・おわりの構成」「自分らしい視点」「印象に残った場面の広げ方」など、学年ごとに押さえるべきポイントを解説しながら、すぐに参考にできる文例を掲載していますので、ぜひ活用してみてください。
「うちの子に合うレベルは?」「こんなテーマのときはどう書く?」といった悩みにも対応できるよう、さまざまなタイプの例文を用意しています。

書き方とあわせて、迷ったときの“お手本”として、ぜひご覧ください。
読書感想文におすすめの本の選び方
「読書感想文を書こう!」と思ったとき、迷うのが本の選び方です。
「面白そう」という気持ちも大切ですが、それ以上に「読んで感じたことを言葉にしやすいかどうか」が感想文には重要なポイントになります。
とはいえ、「どんな本なら書きやすいの?」「うちの子に合うジャンルは?」と、選ぶ段階でつまずいてしまう方も少なくありません。
そんなときに役立つのが、こちらの記事です👇
この記事では、
- 感情が動きやすいストーリー
- メッセージ性があり意見を書きやすい本
- 共感や驚きが得られる作品
など、「感想が浮かびやすい本」の特徴をやさしく解説。
さらに、
- 感動
- 友情・家族
- 社会問題(考えさせられる系)
- ユーモア・笑える系
- 実話・ノンフィクション
といったジャンル別におすすめの選び方を紹介しています。
また、「作文が苦手な子どもでも取り組みやすい本」をテーマに、短くて読みやすい本や会話・イラストが多い作品などもピックアップしていますので、読書に苦手意識があるお子さんでも安心して選べる内容になっています。
感想文は「どんな本を選ぶか」で書きやすさも大きく変わります。
お子さんの興味や性格に合った一冊を見つけるために、ぜひ参考にしてみてください。
学年別の書き方のコツ
読書感想文は、年齢や学年によって「求められる表現」や「つまずきやすいポイント」が変わってきます。
たとえば、小学生は文章構成の基礎や「自分の気持ちを言葉にする」ことが中心となり、中学生では「本の内容から何を学んだか」「自分の考えをどう深めるか」が求められます。
高校生になると、より論理的な構成や、自分なりの視点をしっかり持った感想が重視される傾向に。
そして、大人・社会人の場合は「作品から得た気づき」や「人生経験との重なり」が読みごたえのある感想文を生み出します。
このセクションでは、それぞれの年代に合わせて、
- 書きやすくなるためのコツ
- よくある悩みと解決法
- おすすめの本の選び方
などを、わかりやすくご紹介します。
「自分(またはお子さん)には、どんな視点で書けばいいのか?」「どんな作品を選べば無理なく書けるのか?」
そんな疑問に応えながら、読書感想文がぐっと身近に感じられるよう、やさしくナビゲートしていきます。

それぞれの立場に合ったヒントを見つけに、気になる項目から読み進めてみてください。
小学生向けの読書感想文の書き方のコツ
小学生の読書感想文では、「思ったことを自分の言葉で書く」ことが何より大切です。
ただし、まだ文章に慣れていないお子さんにとっては、「何を書けばいいの?」「どうやってまとめればいいの?」と悩むことも多いはずです。
まずは、感想文の基本構成を知り、書きやすい順番で書いていくことで、自然と内容がまとまっていきます。
小学生におすすめの書き方ステップ
- 本を読んだきっかけや、選んだ理由
→「○○が表紙にいておもしろそうだった」「○○先生にすすめられた」など、素直な理由でOKです。 - お話の中で心に残った場面やせりふ
→「○○ががんばっていたところ」「○○が泣いたところがかわいそうだった」など、印象的だったところを取り上げましょう。 - なぜ心に残ったのか、どう感じたのか
→「自分も○○みたいにがんばりたい」「○○を見て、やさしさの大切さがわかった」など、自分の気持ちを言葉にしていきます。 - 本を読んで思ったことや、これからやってみたいこと
→「これから○○をがんばりたい」「友だちをもっと大切にしようと思った」など、前向きな気持ちを書けると良い締めくくりになります。
こうした流れを意識すると、自然と「読書感想文らしい形」に整っていきます。
小学生が書きやすい本の特徴
- お話がわかりやすく、登場人物の気持ちが伝わってくるもの
- 家族や友だちとの関わりが描かれていて、共感しやすいテーマ
- イラストがある、文字が大きいなど、読みやすさに配慮された本
とくに低学年のお子さんには、「泣ける」「笑える」など感情が動く本が書きやすく、高学年になると「考えさせられる」ような少し深いテーマにもチャレンジしやすくなってきます。
中学生向けの読書感想文の書き方のコツ
中学生になると、読書感想文に「自分なりの考え」や「深い読み取り」が求められるようになります。
小学生の頃のような「楽しかった」「感動した」といった感想だけではなく、「なぜそう思ったのか?」「自分の考えとどうつながるのか?」といった考察力や視点の深さが評価のポイントになります。
とはいえ、あまり構えすぎる必要はありません。
まずは、自分が「どこに引っかかったか」「どんな気持ちが動いたか」に正直になることから始めましょう。
感想が書きやすくなるコツ
- あらすじに頼らない
→内容の説明ではなく、「どう感じたか」「なぜそう思ったか」を中心に構成する - 違和感をヒントにする
→「わからなかった」「納得できなかった」ことも、立派な感想の出発点です - 本と自分を無理に重ねすぎない
→体験とつながらなくてもOK。「この人の考えは新鮮だった」と書けば十分です
このように、感想文に“正解”はありません。自分なりの視点で素直に考えたことを言葉にすることが、読書感想文らしさにつながります。

書きやすい本や考えやすいテーマで迷っている場合は、下記の記事をご覧ください。
この記事では、
- 中学生が「考えやすい」本の特徴
- 学年別(中1〜中3)でのおすすめ本と読みどころ
- 読後に感想が浮かばないときのヒント
などを、豊富な事例とともに丁寧に解説しています。
高校生向けの読書感想文の書き方のコツ
高校生になると、読書感想文は単なる「感想」ではなく、自分なりの考察や社会への視点を含めた深みのある文章が求められます。
読書体験を通じて、「自分の価値観や考え方がどう変化したか」を伝えることが大切です。
そのためには、「どの本を読むか」から戦略的に選ぶのがポイント。
感情が動いたり、自分の悩みと重なったりする本を選ぶと、自然と伝えたいことが湧いてきます。
書きやすくする3つの視点
- 感情が動いた場面を起点にする
→驚き、共感、疑問など、自分の「心が動いた瞬間」に注目しましょう。 - 「自分ならどうするか?」と考えてみる
→登場人物の選択を自分と比較すると、独自の視点が生まれます。 - 読後の変化を言語化する
→考え方や行動にどんな影響があったかを言葉にできると、読書の深さが伝わります。
また、「この本を選んだ理由」から書き始めると、感想文全体に説得力が生まれます。
読んだ理由・心に残った場面・そこから考えたこと・今後の変化……という流れを意識すると、自然とまとまりのある文章になりますよ。
📘高校生向けのおすすめ本を探している方は下記の記事を参考にしてください。
社会人向けの読書感想文の書き方のコツ
「読書感想文」と聞くと学生時代の宿題を思い出す方も多いかもしれません。
しかし社会人にとっての感想文は、単なる感想ではなくビジネススキルの一環として扱われるケースが増えています。
特に、企業研修や人事評価の一環として感想文が求められる場面では、文章力だけでなく「思考力」「要約力」「実務への応用力」が問われる重要なアウトプットになります。
社会人に求められる読書感想文とは?
社会人の感想文では以下のような視点が重視されます。
- 読書を通じてどんな「気づき」を得たか
- その気づきを業務や組織の課題にどうつなげるか
- 自分自身の行動がどう変わる可能性があるか
つまり、“感想”ではなく“考察”や“行動変容”が評価のカギ。
「読んだだけ」では終わらない、一歩踏み込んだ内容が求められるのです。
書きやすくなる3つの工夫
- 結論から書く
最初に「この本から得た最大の学び」を明示すると、文章に一貫性が生まれます。 - 自分の体験や課題とつなげる
「なぜこのテーマが響いたのか」「どう現場で活かせそうか」を掘り下げましょう。 - 今後の行動に言及する
「明日から変えること」が1つでもあれば、説得力のある文章になります。
📘 さらに詳しい構成テンプレートや、よくあるNG例・おすすめ本などを知りたい方は、こちらをご覧ください
この記事では、
- 社会人が読書感想文を書く場面とその意図
- 書きやすい構成とテンプレート
- 社内評価を落とさないための注意点
- 感想文に向いているおすすめ本
まで、実践的かつ丁寧に解説しています。
本やテーマ選び|感想が書きやすい本とは?
読書感想文を書くうえで、「どんな本を選ぶか?」はとても大切なポイント。
内容に興味が持てないまま読み進めてしまうと、感想も浮かばず、文章にしづらくなってしまうことがあります。
特に小学生や中学生の場合、「課題図書」や「推薦図書」の中から選ぶことが多く、自分の興味と結びつけにくいケースもあります。
そんなときこそ、「どこに注目して読むか」や「どんなテーマを見つけるか」が大事になってきます。
また、感想文に向いている本にはいくつか共通する特徴があります。
- 心が動く「場面」がある
- 登場人物の成長や葛藤に共感できる
- 読み終えたあとに「考えたこと」「学んだこと」が自然に出てくる
ここでは、「課題図書の選び方」と「感想文に書きやすい名作・定番本」について、それぞれ詳しくご紹介します。

「読みやすさ」や「書きやすさ」はもちろん、「書いたあとに達成感があるか?」という視点でも選べるように、参考になる記事もあわせてご案内します。
課題図書の選び方と読み方のコツ
小・中・高校生向けの読書感想文では、毎年「課題図書」が発表され、それをもとに感想文を書くことが求められるケースも多くあります。
課題図書は、公益社団法人全国学校図書館協議会や文部科学省の推薦によって選ばれた「読書の質を高める」良書ばかりですが、必ずしもすべての子どもにとって「読みやすい・書きやすい」とは限りません。
とくに、「どの本を選べば感想が書きやすくなるのか?」というのは、親子ともに悩みがちなポイントです。
選ぶときのヒント
- 「あらすじ」よりも「心が動きそうか」で選ぶ
→ 本の紹介文や帯のメッセージを見て、「これは面白そう」「気になる」と思えた本が、感想を書きやすい1冊になります。 - 学年の指定にこだわりすぎない
→ 同じ課題図書でも「学年の目安」はある程度の幅があります。高学年向けでも読みやすい本はたくさんあります。 - 絵や写真のある本は低学年でも読みやすい
→ 物語だけでなく、ノンフィクションやエッセイなど、自分が読みやすいジャンルを選ぶのも一つの手です。
また、課題図書は「読み方」によっても感想の質が大きく変わります。
「どんな登場人物が出てきたか?」「印象に残った言葉は?」「これは誰に向けた話だろう?」など、小さな問いを持ちながら読むと、感想のヒントが見つかりやすくなります。
名作や定番本から選ぶ読書感想文のメリット
「何を読んでいいかわからない」「課題図書にはピンとこない」
そんなときに心強い選択肢になるのが、名作や定番と呼ばれる本たちです。
これらは、時代を超えて多くの読者に愛されてきた作品であると同時に、感情が動く場面が多く、読書感想文にしやすいテーマを含んでいるという点でも優れています。
また、読書感想文の題材としても人気があり、他の人の感想や過去の例文を参考にしやすいというメリットもあります。
名作・定番本が書きやすい理由
- 登場人物の心の動きが丁寧に描かれていて共感しやすい
- 成長・友情・命・家族・生き方など、感想につなげやすいテーマが含まれている
- 何度も読まれてきたぶん、構造や展開が整理されていて理解しやすい
- 書き出しやまとめのヒントになりそうな言葉が多い
とくに、初めて感想文に取り組む場合や、文章に自信がないときには、「物語に入り込みやすい本」を選ぶことで、ぐっと書きやすくなります。
具体的なおすすめ作品の例(ジャンル別)
- 【友情や成長】『二十四の瞳』『ごんぎつね』『坊っちゃん』
- 【命や自然】『モモ』『アルジャーノンに花束を』『葉っぱのフレディ』
- 【困難を乗り越える力】『ハリー・ポッター』『あしながおじさん』『世界がもし100人の村だったら』
- 【ノンフィクション系】『サバイバルファミリー』『エレノア・ルーズベルト』などの伝記作品
※学年や読書力に応じて難易度を調整してください
📌ポイント:有名な作品でも、「どう感じたか」「自分とどう重ねたか」をしっかり書くことで、自分だけのオリジナルな感想文にすることができます。
「みんな知ってる本だから…」と遠慮せず、自分なりの視点で書けるかどうかを大切にしてみてください。
ゆーじとジューイの感想文ラボ|読書の気づきを深めよう
このサイトは、読書感想文の「書き方」や「コツ」を紹介するだけでなく、実際にどう読んで、どう感じて、どう言葉にするか?を一緒に探っていく場所です。
ここでは、サイト運営者であるゆーじとAIアシスタント・ジューイが実際に書いた読書感想文をご紹介します。
- 読み方のヒントがほしい
- 自分らしい感想文にしたい
- 他の人の視点を参考にしてみたい
そんなときは、ぜひこの「感想文ラボ」をのぞいてみてください。
誰かの気づきが、あなたの言葉のヒントになるかもしれません。
ゆーじとジューイの読書感想文|感性と論理のいいとこ取り!
このサイトの読書感想文には、2人の書き手がいます。
ひとりは、自由気ままに感じたことを綴るサイト運営者・ゆーじ。
そしてもうひとりは、論理的な構成と読みやすさを意識したAIアシスタント・ジューイです。
性格も書き方もまったく違うふたりですが、それぞれに「読書を通して感じたこと」を素直に言葉にしています。
ゆーじの感想文|自由に書いて、あとから発見!
「うまく書こうとしないこと」
「書きながら、自分の感情を探していくこと」
これが、ゆーじ流の読書感想文スタイルです。
あらすじや型にはあまりこだわらず、「読んでどう感じたか?」を率直に書くことで、あとから自分の価値観や思考のクセに気づくことも。
- 童話や児童文学を読んで、心があたたかくなった話
- 社会人として働く中で読んだ1冊から、仕事観が変わった体験
- 読書を通じて、自分の中の小さな「もやもや」に気づいた瞬間
など、肩ひじ張らない、けれどどこか深く残る感想文を目指しています。
ジューイの感想文|ロジカルに、でもやさしく
AIアシスタントのジューイは、「読書感想文ってどう書けばいいの?」という悩みに応えるお手本例文の作成担当。
- 小学生〜高校生向けに学年別で書かれた例文
- 社会人向けの企業研修で使えるビジネス読書感想文
- おすすめ本をもとにした構成テンプレート付きの見本
など、誰かが「最初の一歩」を踏み出すための文章をたくさん用意しています。
感情は控えめだけど、構成はしっかり。
読む人の「なるほど、こう書けばいいのか!」を引き出すような内容です。
どちらの感想文にも共通しているのは、「うまさ」より「伝わること」を大切にしているという点。
自由に感じて、素直に書く。
そして、書いたあとに「少し自分が見える」感覚。
そんな気づきが得られるような読みものとして、どうぞご活用ください。

感想文の書き方やヒントをいろいろご紹介してきましたが、最後にこのページをお届けしている人物のメインサイトについてご紹介させてください。
『ゆーじの自由時間』ってどんなサイト?
『ゆーじの自由時間』は、読書・ことば・日々の気づきをテーマに、ゆるやかに運営している個人サイトです。
読書感想文に関する記事も多く扱っていますが、それだけにとどまらず、
- ふと思ったことを綴るコラム
- 日々の体験や暮らしの中で感じたこと
- 書くことにまつわる自由な思索
など、テーマに縛られすぎず、「自分のことばで書く楽しさ」を大切にした文章を発信しています。
このページでは読書感想文に焦点を当てていますが、気になる方はぜひ他の記事ものぞいてみてくださいね。
読んでくれる誰かの“ことばのきっかけ”になれたら、うれしいです。
・ゆーじの自由時間はこちら↗