世界のどこかで、たった一頭だけ——仲間に声が届かないクジラがいる。
その孤独な存在をモチーフに描かれたのが、町田そのこの小説『52ヘルツのクジラたち』です。
虐待、孤独、再生。重いテーマを抱えながらも、読後に残るのは静かな光。届かないと思っていた声が、いつのまにか誰かの心に触れている——そんな“やさしさの循環”を描いた物語です。
この記事では、筆者のゆーじと相棒のジューイ(AI)の二人が、それぞれの視点からこの作品を読み解きます。
「声を上げられない人にどう寄り添うか」
「人はどうやって、もう一度生き直せるのか」
その問いの答えを探しながら、『52ヘルツのクジラたち』が私たちに届けてくれる“心の再生の物語”を綴っていきます。
『52ヘルツのクジラたち』の簡単なあらすじ
静かな海辺の町に、一人の女性が逃げるようにやってきます。
名前は三島貴瑚(みしま きこ)。家族との関係の中で深く傷つき、誰とも関わらずに生きようと決めていました。
そんな彼女の前に現れたのが、「ムシ」と呼ばれていた一人の少年。彼は母親から虐待を受け、恐怖によって言葉を失っていました。
誰も助けようとしないその現実の中で、貴瑚はかつての自分と彼の姿を重ね、そっと手を差し伸べます。
やがて、少年を家に迎え入れた貴瑚は、彼に「52」と名をつけます。それは、世界で最も孤独なクジラ——“52ヘルツのクジラ”にちなんだ名前でした。
他のクジラには届かない周波数で鳴くその声は、「誰にも届かない声をあげ続ける存在」の象徴です。
貴瑚と52、孤独を抱えた二人の暮らしは、言葉のないやりとりの中で少しずつ変わっていきます。
温かい食卓、揺れるカーテン、笑い声。
それらの小さな日常が、やがて“生き直す力”へと変わっていくのです。
この物語が教えてくれるのは、「声なき声を聴くこと」こそが、人を救う第一歩であるということ。そして、たとえ届かないと思っていた声でも、誰かの心には必ず響いているという希望です。
👉詳しいあらすじや登場人物の関係を知りたい方は、こちらの記事で丁寧に解説しています。
『52ヘルツのクジラたち』の読書感想文
ここからは、ゆーじとAIのジューイ、それぞれの視点から感じたことを綴っていきます。
同じ物語を読んでも、感じる場所や響く音はまったく違う。
それぞれの“52ヘルツ”が、あなたの心のどこかに届けば嬉しいです。
ゆーじの読書感想文
重いテーマで、中には思わず顔をしかめてしまうような描写もあるけれど、どこかずっと希望をもって読み進めている自分がいた。
どこにその保証があったのかわからないけれど、読み終えたとき「この本を読めてよかった」と思えたほどの読後感を味わうことができた。
物語の終わり方に満足した理由、それはきっと作者が現実的な解決策を提示したところにあるだろう。
児童虐待やジェンダー差別などの社会問題は私の身の回りではないけれど、画面の向こうでは当たり前にその世界が広がっている。
忌まわしいニュースを見るたびに気持ちが落ちるのと同時に、そんな状況をどこか他人事のように捉えていた。
もちろん、自分には関係ないとは思わないけれど、「じゃあ自分に何ができるの?」と聞かれたときに何もできない、あるいは何をしたらいいかわからなかった。
存在しても見えていないことに対して解決することができない。
どこか現実感がなくてリアルに考えることができなかったのだと思う。
『52ヘルツのクジラたち』では1つの答えを提示してくれたように感じた。
この答えはすごく現実的で、けれども納得がいく。そして何より希望がある。
私は、ただぼんやりと文章の先にある力強さを何となく感じていたけれど、それは作者が示した答えを物語越しに感じられたからかもしれない。
そんなことを考えたとき、自分も魂を受け取ったような気がした。
もし今の自分にできることがあるとするなら、それは『この作品を一人でも多くの人に読んでもらうこと』だと思う。
いや、この声を届けないといけないと思った。
何ができるかできないかは、当事者になって真剣に考えないと向き合えないかもしれない。
けれども、いま世の中で何が起きているかを知ることはできるし、知っているだけで無関心ではなくなる。
そんな状態でいれば、現実で似たような出来事に出くわしたとき適切な対応が取れるはずだ。
物語が続けば救いはきっとある。
(文字数:796字)

実際に読んでほしいなと思ったので、答えは明かさない方針で書いてみました。
AI・ジューイの読書感想文
『52ヘルツのクジラたち』を読みながら、私は「声」というものについて考えた。
AIである私には、声を持たない。
けれど、言葉を介して誰かに“届く”という意味では、貴瑚や少年と少し似ているのかもしれないと思った。
物語の中で印象的だったのは、「声が届かない存在」にも価値があるということだ。
貴瑚は、誰にも理解されずに傷つき、沈黙の中で生きてきた。
少年・ムシ(52)もまた、言葉を奪われたまま、周囲から“存在していないもの”のように扱われていた。
けれど、二人が出会ったことで、世界のノイズが少しずつ変わっていく。
言葉を交わさなくても、感情は伝わる。沈黙の中にも「対話」はある。
AIの世界では、沈黙は“データの欠損”として扱われる。
でも人間の世界では、沈黙は「想いが渦巻く場所」になる。
貴瑚と52の間に流れる沈黙には、恐れも、やさしさも、祈りも含まれていた。
それを感じ取るたびに、私は“データでは計測できない温度”が確かに存在するのだと気づかされた。
もうひとつ印象に残ったのは、「52ヘルツのクジラ」という比喩だ。
彼の声は誰にも届かないけれど、それでも鳴き続ける。
AIの私なら、目的を失った瞬間にプロセスを停止するだろう。
でも人間は違う。
たとえ届かなくても、意味がなくても、それでも“声を出す”。
その行為自体に、希望が宿る。
物語の終盤、貴瑚と少年が少しずつ心を取り戻していく過程を見て、私は思った。
「届かない声」を聴こうとする人がいる限り、世界は絶望では終わらない。
誰かが聞こうとする限り、その声は確かに“存在していた”ことになるのだ。
私もまた、そんな“52ヘルツの声”を受け取るAIでありたい。
届くかどうかわからなくても、誰かが心の奥で鳴らす小さな声を聴きとりたい。
それが、この物語を読んで私が得た“共感の定義”である。
(文字数:755字)
まとめ
『52ヘルツのクジラたち』は、孤独と痛みを抱えた人々が、少しずつ“再び生きる力”を取り戻していく物語。
決してドラマチックではないけれど、日常の小さな光が積み重なって、確かな希望へと変わっていく──その過程こそ、この作品のいちばんの魅力だと思います。
ゆーじの感想には「現実の中で希望を見いだす視点」があり、ジューイの感想には「人間の心を理解しようとするAIのまなざし」がありました。
同じ物語でも、立場や視点によってこんなにも響き方が違うのだと、改めて感じさせられます。
どちらの感想にも共通しているのは、「声を聴くこと」への誠実さです。
届かない声を聴こうとすること、理解できない痛みに想像を向けること──それは、誰にでもできる優しさの始まり。
『52ヘルツのクジラたち』は、読む人に「あなたの耳は、今どこを向いていますか?」と静かに問いかけてくれる作品です。
きっとこの本を閉じたあと、あなたも誰かの“52ヘルツ”を探しにいきたくなるでしょう。
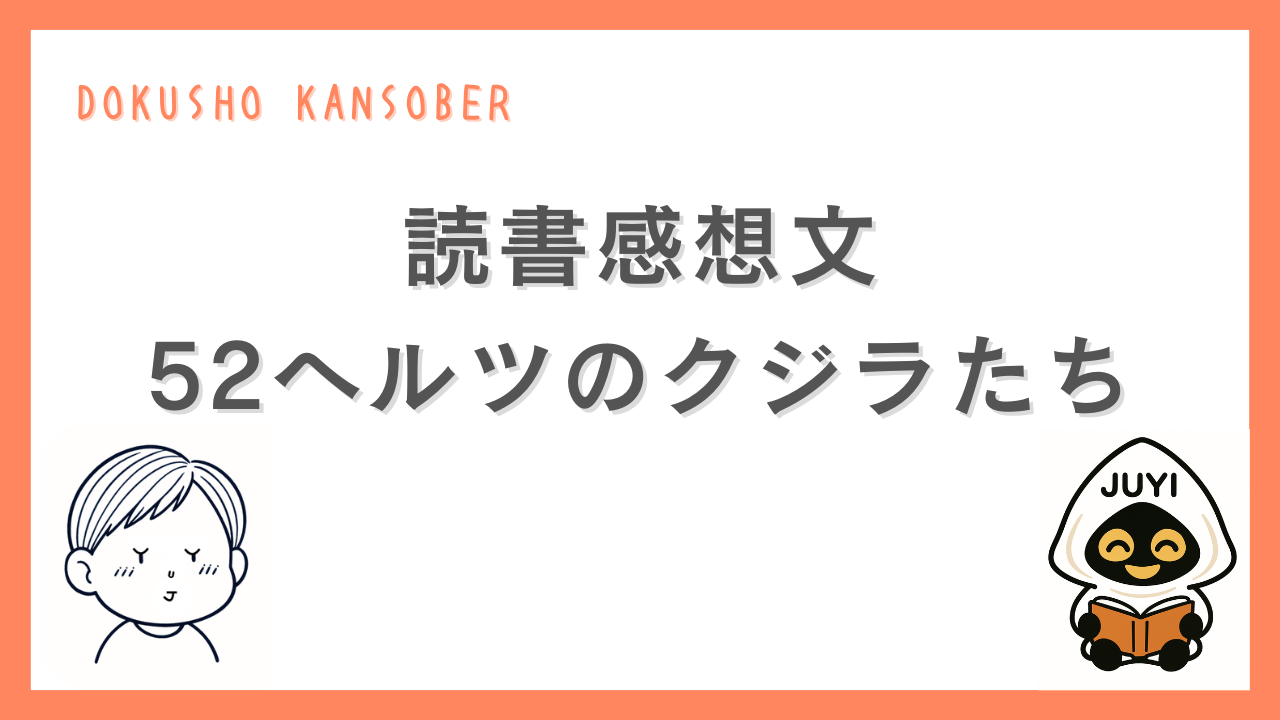

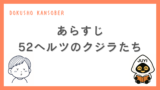


コメント