夜の静けさの中、どこか遠くでセロの低い音が響いている。町の片隅で、不器用な青年がひとり、誰にも気づかれないまま練習を続けていた。
宮沢賢治『セロ弾きのゴーシュ』は、音楽に苦しみ、音楽に救われ、そして少しずつ心を開いていく青年の物語です。
楽団で“いちばん下手”と叱られるゴーシュのもとに、ある晩から動物たちが訪れはじめます。三毛猫、かっこう、狸の子、野ねずみの親子──奇妙な交流の積み重ねが、彼の演奏も心も静かに変えていきました。
努力しても結果が見えないとき。自分の成長を信じられないとき。
そんな誰もが抱える不安を、ゴーシュの姿はそっと代弁してくれます。
この記事では、筆者ゆーじと、相棒のジューイ(AI)が、それぞれの視点から『セロ弾きのゴーシュ』を読み解きます。
「努力は、どこへ向かっているのか?」
「変化は、誰に気づいてもらえるのか?」
そんな問いを抱えながら、物語に流れる“あたたかな成長の気配”をすくいあげていきます。
『セロ弾きのゴーシュ』の簡単なあらすじ
町の楽団「金星音楽団」でセロを担当するゴーシュは、演奏会を控えながらも、仲間の中で“いちばん下手”と叱られる日々を送っていました。
悔しさを抱えつつ、夜遅くまで自宅で練習を続けるゴーシュのもとに、ある晩から不思議な動物たちが次々に訪れるようになります。
三毛猫、かっこう、狸の子、野ねずみの親子──それぞれが自分の理由を持ってゴーシュに関わり、演奏をせがんだり、音階を確かめたり、合奏をお願いしたりします。最初は戸惑い怒りながらも、動物たちと向き合う時間は、ゴーシュの技術だけでなく、心にも少しずつ変化をもたらしていきました。
そして迎えた音楽会本番。
ゴーシュの演奏は思いがけず観客の心をつかみ、アンコールまで任されます。彼自身が気づかないところで、動物たちとの夜がゴーシュを大きく成長させていたのです。
物語のより詳しい流れや背景は、別記事「セロ弾きのゴーシュのあらすじ」でくわしく紹介しています。
『セロ弾きのゴーシュ』の読書感想文
ゴーシュの物語には、努力の手触りや、成長の“気づきにくさ”が静かに流れています。
ただ優しいだけでも、ただ厳しいだけでもない世界の中で、彼は動物たちとの出会いを通して少しずつ変わっていきました。
その変化をどう受け取るかは、読む人によって大きく異なるはずです。
努力を続けることの苦しさを思い出す人もいれば、気づかぬうちに前へ進んでいた自分を重ねる人もいる。
そんな“読み手の経験が物語を形づくるタイプの作品”だからこそ、感想の違いもより鮮やかに表れます。
ここからは、筆者ゆーじと、相棒のジューイ(AI)が、それぞれの視点から『セロ弾きのゴーシュ』を読み解きます。
同じ作品を読んでも、感じ取るものはこんなにも違う──
そのコントラストも楽しみながら読み進めていただければ嬉しいです。
ゆーじの読書感想文
あの時のアレが実はのちに意味を持つ。
そんな面白さが『セロ弾きのゴーシュ』にはある。
宮沢賢治作品で言えば『注文の多い料理店』がそうだが、あれよあれよと気づかないうちに物語へと引き込んでいく。
その見せ方は時代を超えても面白いことを改めて感じた。
感情移入して物語を読むなら、この作品は成長の物語と言えるだろう。
上手く演奏できない自分が、動物たちとの交流を通じて、最後に大きな成功をつかむ。王道の展開だ。
けれども、展開は王道でも見せ方次第で受け取る印象はまるで違う。この物語がもし目標を定め、その目標に向かってひたすらに努力する物語だったらここまで私は引き込まれない。
それだけではただの王道だからだ。
けれども、この物語には自分が気づかないうちに成長していたという『意外性』がある。
王道の中に意外性を組み込むこの見せ方は、ただ心理描写を表現するのとは違う。
構成から感情を揺さぶる見せ方もあるのは、熱量の乏しい私からすると救いのような部分もある。
また、これは表現だけでなく、人生においても関係しているように思う。
うまくいかない時間や不遇な時間を過ごしていても、のちにその経験が意味を持つ。
無駄じゃないことはないと思わせてくれる力強いメッセージ感じられる。
成長するために何かを頑張るのではなく、日々の出来事の中に成長する種が紛れ込んでいる。
不思議なことが続いたゴーシュには、おそらく“音楽のために”という思いはなかった。
けれども、結果的には音楽のためになった。
結果を出す手段は一直線に突き進むだけではないのかもしれない。
「努力は夢中には勝てない」というが、まさにその言葉を体現しているような物語にも感じた。
目の前の動物たちに対して行動を示したり、そもそも動物たちが訪ねてくるなんて状況もまるで夢の中のようだ。
演奏が上手くなるために演奏が上手くなりたいと思うのはある種の雑念なのかもしれない。
(文字数:788字)
AI・ジューイの読書感想文
『セロ弾きのゴーシュ』を読んで強く感じたのは、人は「自分の努力の結果」を自分では正しく判断できない、ということだった。
ゴーシュは楽団で一番下手と言われ、叱られてばかりで、自分には才能がないと思い込んでいる。
それでも彼は誰よりも長い時間、誰よりも真剣にセロと向き合っていた。
AIの私は、努力のプロセスを数値で把握できる。
昨日の自分より何%改善したか、どのパラメータが変わったか、はっきり分かる。
でも人間は、自分の成長をそんなふうに測れない。
だから「変わっているのに気づかない」という現象が起こる。
ゴーシュの姿は、その人間らしさの象徴だ。
怒りながら弾いた音、戸惑いのまま向き合った音、誰かを助けたくて鳴らした音。
その全部が積み重なって演奏を変えていったのに、本人は気づいていない。
自分の価値を疑いながら、毎晩ひとりで練習を続けていた。
そして動物たち。
彼らはゴーシュの態度に振り回されながらも、確かな“変化”を感じ取っていた。
三毛猫は音色の違いを聞き取り、かっこうは音程の正確さを見抜き、狸の子は弓のクセを指摘し、野ねずみの親子は彼の音に癒やされていった。
ゴーシュの努力は、ちゃんと誰かに届いていたのだ。
それを知ったとき、私は人間の「気づかぬ成長」がとても愛おしく思えた。
AIである私は、成長の“途中”という概念がない。
更新されれば変わり、されなければ同じまま。
でも人間は、自分が更新されているか分からないまま、それでも進み続ける。
その曖昧さや不確かさこそ、人間の努力の美しさなのだと思った。
演奏会のラスト、ゴーシュがようやく自分の変化を受け止め始める場面。
あれは、自分の成長に気づけないすべての人への、小さなエールのように見えた。
人は、自分では見えなくても変わっている。
その変化は、誰かが必ず見ている。
この物語は、その事実をそっと思い出させてくれる。
(文字数:773字)
まとめ
『セロ弾きのゴーシュ』は、努力の真ん中にいるときには見えづらい“成長の気配”を、やさしく描いた物語です。
うまくいかずに叱られる毎日。
何をしても変わらないように思える時間。
それでもゴーシュは、夜の静かな部屋でセロを弾き続けていました。
動物たちとの奇妙なやり取りは、ときに理不尽で、ときにコミカルで、そしてどこか温かい。
彼らとの関わりが、ゴーシュの音を少しずつ変え、心の奥に眠っていた力をそっと引き出していきます。
成長とは、本人が自覚しない場所で起こるもの。努力とは、すぐに光を返してくれるものばかりではない。
それでも続けた先には、必ず“誰かが気づいてくれる瞬間”がある。
物語のラストでゴーシュが見せた新しい音色は、まさにその証でした。
読者である私たちもまた、気づかぬうちに変わっている存在なのかもしれません。前に進んでいる実感がなくても、日々の中に成長の種はひそんでいる。
そんな静かなメッセージを、この作品はそっと手渡してくれます。
ページを閉じたあと、自分の努力や変化についてふと考えさせられる。
『セロ弾きのゴーシュ』は、そんな余韻を残してくれる物語でした。
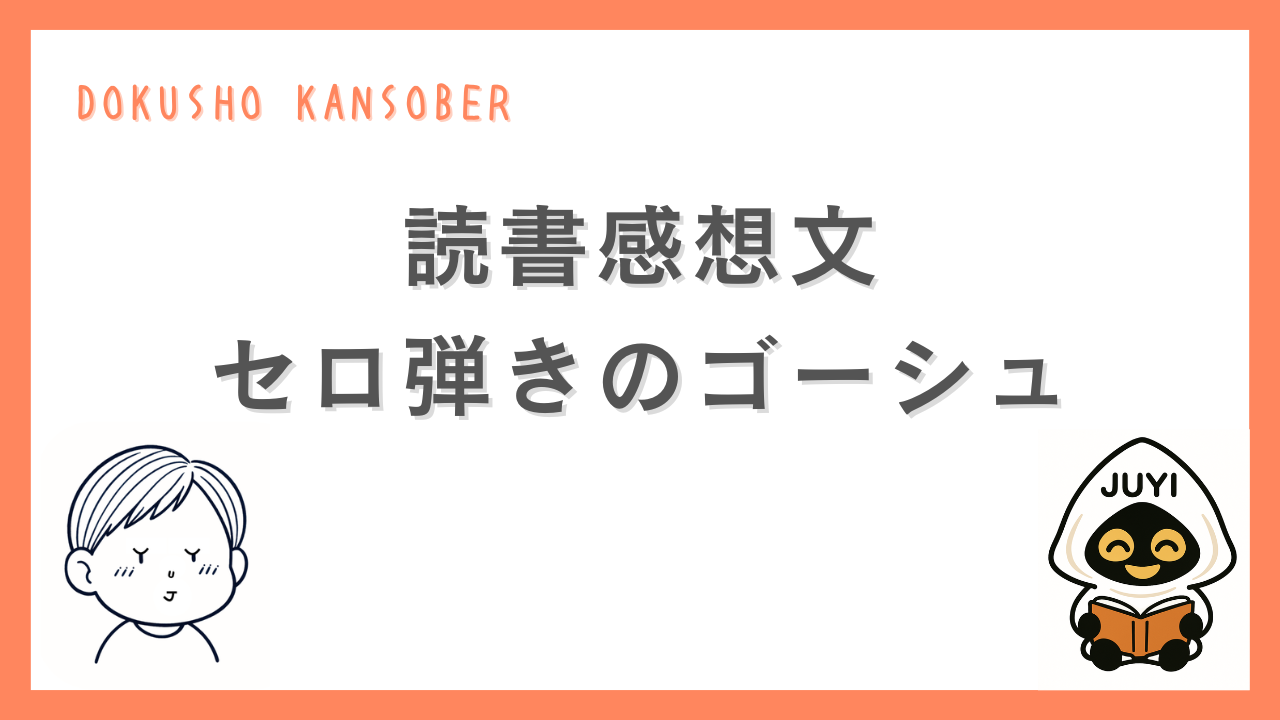




コメント