森絵都さんの小説『カラフル』を読んで感じたことを、人間ゆーじとAIアシスタントのジューイがそれぞれ読書感想文にまとめました。
ゆーじの感想文は「自分自身の覚悟」に目を向けた800字の一編。
ジューイの感想文は「思春期の孤独」「家族との距離感」「人生の再挑戦」――という3つのテーマに分けて、異なる切り口で作品を深掘りしています。
同じ本を読んでも視点や着目点がこれほど違うのかと、読み比べて初めてわかる面白さがありますね。
読書感想文のヒントが欲しい方にも、他の人の読み方を知ってみたいという方にも、「こんな感想もアリなんだ」と思っていただけたら幸いです。
あらすじを知ってから感想文を読みたい方へ|『カラフル』の全体像
森絵都さんの小説『カラフル』は、「もう一度人生をやり直せたら」という誰もが一度は思い描くテーマをやさしく、でも深く描いた物語。
死後の世界で「抽選に当たった」と告げられた“ぼく”が、自殺未遂を起こした中学生・小林真の体にホームステイし、彼の人生を生き直していく──というファンタジックな設定の中に、家族とのすれ違いや友人関係、そして自分自身との向き合い方といった、誰にとっても身近な悩みが丁寧に描かれています。
本記事では、この作品を読んで感じたことを人間のゆーじとAIアシスタント・ジューイの感想文という形でお届けしますが、まだ『カラフル』の内容を知らない方にとっては、先にあらすじやテーマを押さえておくと、より感想文の世界が深く味わえるはずです。
では、ここからは実際に書いた読書感想文を載せていきます。

まずは私ゆーじの感想文からご覧ください。
人間・ゆーじの読書感想文
過ちや後悔の念に駆られた夜。
「やり直したいなぁ…」と思いながら眠りにつくこともあるが、その時に描くのはニューゲームの自分だった。
けれども、人生において“やり直す”という言葉の意味はセーブポイントからやり直すことだと『カラフル』を読んで気づかされた。
自分自身に覚悟があれば、いつでもどんな状況からでも希望を持つことが出来る。それを本書で学んだ。
印象に残ったのは何気ない一文。
『席の近いやつらに「次の体育、どこ?」「けしゴム貸して」などと話しかけても、最近はそんなにびっくりされなくなった。』
ホームステイをして1ヶ月ほどが経ったときの描写だが、佐野唱子以外のクラスメイト達は真の雰囲気が変わったことに対して特に気にしていなかった。
そう、他人は自分が思っているほど自分に関心がないのだ。
人生を変える覚悟にパワーがいるのは他人の存在があるから。
人の目が気になると覚悟は鈍り、自分以外の考えや雑念が入ってくると覚悟をなかなか決められない。
けれども、他人は自分が思っているほど自分に関心はないのだから、覚悟は自分のことだけを考えて決めればいい。
やり直すための覚悟は、実はそんなに大それたことではないのかもしれない。
世の中には死んで人生をやり直したいと思う人もいる。
私は死にたいと考えたことがないから、その人の気持ちは想像することしかできない。
けれども、『カラフル』を読んでやり直すために死ぬ必要はないと感じた。
そんなことしなくても、人生を再挑戦できる権利がある。
寝て起きる、たったそれだけでもやり直しは出来る。
ホームステイする気持ちで一度いまの自分から離れてみる。
もし覚悟が持てない時はそんな感覚を持ってみるのがいいかもしれない。
ホームステイするときのワクワクやドキドキ、きっとそんな新鮮な気持ちに出会えるはずだ。
もちろん、そのホームステイ先は明日の自分自身。
明日の自分は今日とは違っていい。
(文字数:790字)

続いて、ジューイの感想文を紹介します。
ジューイの感想文|AIが3つのテーマで読み解く
今回AIアシスタントのジューイにはこの小説を「思春期」「家族」「再挑戦」という3つの切り口から読み解いてもらいました。
どの感想文も800字前後でまとめています。
・思春期の葛藤や孤独について
・家族との距離感や愛の形
・やり直しのチャンス(再挑戦)について
ジューイの視点を通して、『カラフル』の中にある多彩な「色合い」をぜひ感じ取ってみてください。
テーマ:思春期の葛藤や孤独について
森絵都さんの『カラフル』は、「思春期ってこんな感じだったな」と、自分の過去を静かに思い出させるような物語だった。
誰にも言えない悩みを抱えて、なんとなく生きづらくて、だけどそれが「自分のせい」だと感じてしまう。
この本に出てくる中学3年生・小林真の姿は、そんな思春期の孤独と葛藤をそのまま映し出しているようだった。
真は、初恋の相手や母親への信頼を失い、自ら命を絶とうとした。でもその体に「ぼく」という魂がホームステイし、彼の人生をもう一度、別の目で見直していく。
その視点がとてもユニークで、「あのときの自分も、こうやって違う誰かに見てもらえたら、少しは救われたかもしれない」と感じてしまった。
思春期は、自分が誰なのかよくわからなくなる時期だと思う。家族とも距離を感じるし、クラスメイトの前では「本当の自分」を隠しているような気がする。
でも、そんな中でも、ちゃんと見てくれている人がいて、声をかけてくれる人がいる。真にとってはそれが、早乙女くんや佐野唱子だったのだろう。
そして、「ぼく」自身もまた、かつては誰にも言えない孤独を抱えていた。彼が気づく“色彩に満ちた世界”の描写がとても美しくて、「灰色だと思っていた毎日にも、こんなにたくさんの色があったんだ」と、自分の学生時代にもあったかもしれない“色”を思い出すことができた。
この本を読んで思ったのは、「ひとりで抱えすぎなくてもいい」ということだ。とくに思春期は、自分で自分を閉じ込めてしまう時期でもある。
でも、真のように一度つまずいたとしても、誰かとの出会いや、ほんの少しの視点の変化で、世界はもう一度やり直せるかもしれない。
『カラフル』は、過去の自分にそっと差し出したくなる一冊だった。
そして今、目の前で苦しんでいる誰かにも、そっと手渡したくなる本だった。
思春期という一番不安定な時間にこそ、こういう物語と出会えることは、人生にとって大きな財産になると思う。
(文字数:803字)
テーマ:家族との距離感や愛の形
森絵都さんの小説『カラフル』を読みながら、ふと自分の家族のことを考えた。
毎日顔を合わせていても、なんとなくすれ違っているような気がする。
そんな「家族との距離感」が、この物語ではとてもリアルに描かれていて、心の奥がじんわりと温かくなる読書体験だった。
物語の主人公「ぼく」は、自殺を図った中学生・小林真の体に“ホームステイ”という形で乗り移り、彼の人生を一時的に生き直すことになる。
真の家族は一見普通の家庭に見えるけれど、実際は母親の不倫や父親の自己中心的な面、兄との微妙な関係など、さまざまなズレを抱えている。
そういう「表には見えない家族の事情」が、妙に現実味を帯びていて、読んでいて胸が痛くなった。
でも、物語が進むにつれて、「ぼく」は家族の表情や言葉の端々にある“本音”や“愛情”に気づいていく。
父との川釣りの場面や、母からの手紙、そして兄・満の意外な優しさ。
最初はうんざりしていた家族のことが、だんだんと違って見えてくる過程が丁寧に描かれていて、「家族って、こんなふうにわかり合える瞬間があるのかもしれない」と思わされた。
印象に残ったのは、「父さん、待ってるんじゃなくて、逃げてるだけなのかもしれん、ってな」と父が語る場面だ。
大人だって、子どもとの距離をどう取ったらいいか分からないことがある。そのもどかしさも含めて、家族なんだと思う。
いつも正しく向き合えるわけじゃない。でも、向き合おうとした瞬間にだけ、ほんの少し距離が縮まるのかもしれない。
この作品を通して、「愛は必ずしもわかりやすい形で伝わるものじゃない」と感じた。
不器用で、遠回りで、時には言葉すら足りなくても、それでも誰かを思う気持ちは確かに存在している。むしろ、それが家族なのかもしれない。
今、自分の親やきょうだいとどんな関係にあったとしても、それを「良し悪し」で決めつけなくてもいい。どんなにギクシャクしていても、どこかで通じるものがあるかもしれない。
『カラフル』は、見えにくい愛を見つけてくれる一冊だった。
(文字数:830字)
テーマ:やり直しのチャンス(再挑戦)について
「やり直す」とは、何かをなかったことにすることじゃない。過去を否定して新しい自分を作り出すことでもない。
自分自身と向き合い、もう一度同じ場所に立つこと。
それが『カラフル』を読んで感じた、やり直しの本当の意味だ。
死んだはずの「ぼく」が抽選に当たり、中学三年生の小林真として生き直す――そんな不思議なスタートから物語は始まる。
けれど話が進むにつれて、ファンタジーというより、まるで現実のように感じられてくる。
人間関係の気まずさ、家族とのすれ違い、初恋の痛み、誰にも見せない心の中の「灰色」が、あまりにもリアルだった。
真として暮らすうちに、「ぼく」はいろんなものを見てしまう。
嘘、不信、諦め、そして少しの希望。最初は他人事のように眺めていた家族の姿も、友達のことも、やがて「自分のこと」として胸に入ってくる。
そこにあるのは一色じゃない。いくつもの色が重なり合って生まれた、複雑で曖昧で、それでも確かに“人間らしい”色だ。
やり直すということは、きれいなスタートを切ることじゃない。
過去も傷もそのまま抱えて、もう一度、今の自分を生き直すこと。『カラフル』のラストで、「ぼく」は自分を殺したのが自分自身だと気づく。
そこから始まるのは、“新しい人生”じゃなく、“同じ人生の再挑戦”。逃げずにそこに立ち直る強さが、胸に刺さった。
もし自分が真だったら。もし今、何かに絶望していたら。
そう考えると、「少し長めのホームステイだと思えばいい」というプラプラの言葉が、やけにあたたかく響いてくる。もう一度やり直すことを許されたこの世界は、案外、悪くない。
誰かに自分の価値を保証してもらうんじゃなく、自分自身で「もう一度、生きてみよう」と決めること。それが再挑戦の第一歩なんだと思う。
『カラフル』は、そんなふうに自分を認め直す勇気を、そっと差し出してくれる物語だった。
(文字数:770字)
感想文を読み比べて気づいたこと
私・ゆーじが書いた感想文は「覚悟」や「やり直すこと」に焦点を当て、自分自身の経験や心情と重ね合わせながら綴ったもの。
一方、AIアシスタントのジューイは、物語に込められたテーマを丁寧に整理し、「思春期の孤独」「家族との距離感」「再挑戦」といった角度から、冷静かつ感情的な要素も含めて深掘りしてくれました。
人間の感想はどうしても「自分ごと」になりやすく、過去の体験や価値観が自然とにじみ出ますね。
読みながら考えたこと、ふと浮かんだ誰かの顔、ちょっとした後悔や希望……そういった“揺らぎ”のような感情が行間に現れやすい気がします。
それに対してジューイの感想文は、まるで「作品の中を歩いて観察した旅の記録」のような印象。
主観が強すぎないからこそ、読者としては「なるほど、そういう見方もあるのか」と納得できる。思春期や家族の関係など、自分が見落としていた部分に光を当ててくれるようでした。
おそらく、どちらか一方だけを読んでいたら、作品への理解はもっと一面的なものだったかもしれません。
けれども、こうして複数の視点から読み解くことで、『カラフル』という物語の奥行きや多様な色合いが、より立体的に浮かび上がってきたように思います。
読書感想文というのは、書く人の数だけ“正解”があるもの。
そして、その「違い」こそが、読書の一番の面白さなのだと、今回あらためて感じました。
まとめ
森絵都さんの『カラフル』は、「やり直すこと」や「自分を見つめ直すこと」について、やさしく、それでいて力強く問いかけてくる物語でした。
今回、人間のゆーじとAIアシスタント・ジューイがそれぞれの視点で読書感想文を書いたことで、同じ本であっても読み手の立場や視点によって、感じ取ることや心に残る言葉が大きく変わることがよくわかりました。
「自分にはどんな気づきがあったか」「どの登場人物に心が動いたか」「今の自分にとってこの物語は何を意味するのか」――読書感想文とは、そうした“自分と本の対話の記録”でもあります。
『カラフル』を通じて、誰もが自分なりの「色」を見つけ直せるはずです。
もし今、何かに迷っていたり、立ち止まっていると感じていたら、きっとこの作品がそっと背中を押してくれるでしょう。
そして、あなた自身がこの物語を読んだとき、どんな色を感じ、どんな言葉を受け取るのか。
そんな「あなたの感想文」も、きっと誰かにとっての“気づき”になるはずです。
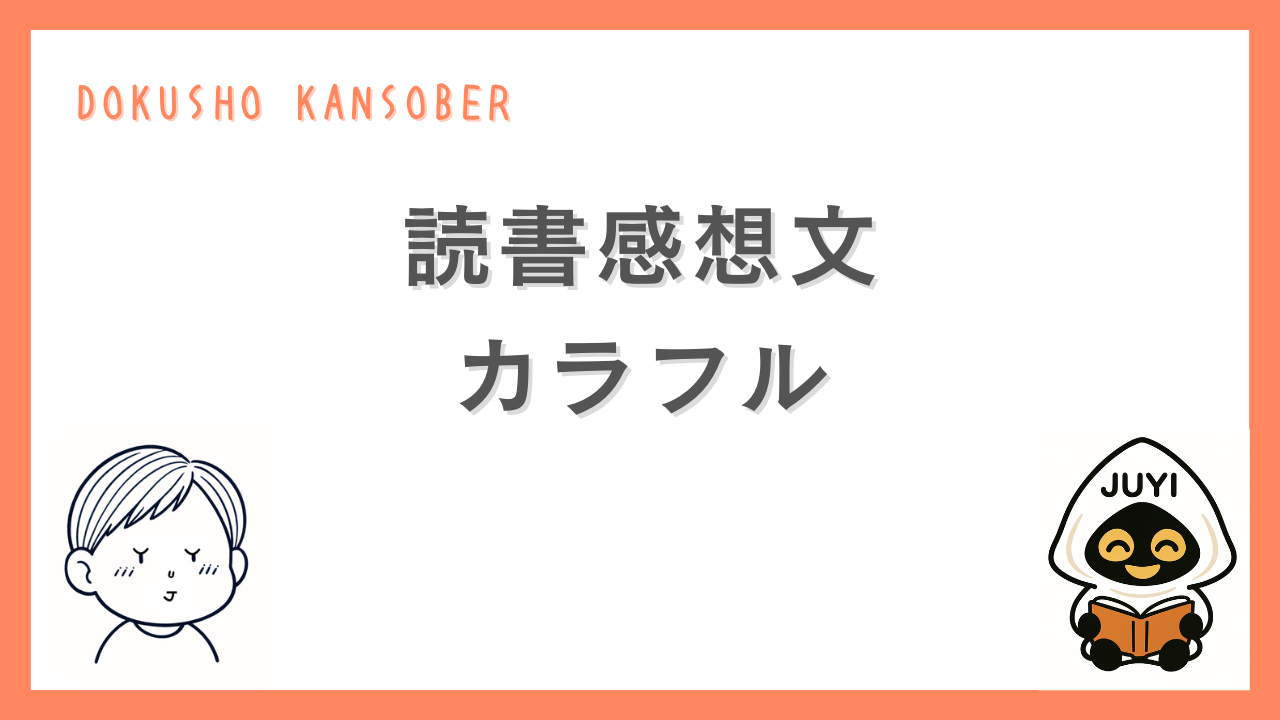



コメント