江戸川乱歩といえば探偵小説の名手として知られていますが、『押絵と旅する男』はそんな彼の作品の中でも、異色ともいえる幻想的な短編。
現実と幻想のあわいで語られる、不気味で、そしてどこか哀しい物語──読んだ後にはきっと、押絵と双眼鏡のイメージが頭から離れなくなるはずです。
この記事では、物語のあらすじをわかりやすくご紹介しつつ、作品の魅力や深いテーマにも触れていきます。
「この話はいったい何だったのか?」とモヤモヤしている方も、「結末だけ知りたい!」という方も、ぜひ最後までお付き合いください。
まずは作品の基本情報から見ていきましょう。
江戸川乱歩『押絵と旅する男』とは?【作品概要と背景】
江戸川乱歩の数ある短編の中でも、『押絵と旅する男』はひときわ異彩を放つ幻想譚。
探偵や推理が主軸となる作品とは異なり、本作は夢とも現実ともつかぬ不思議な世界が、静かに、しかし確実に読者を包み込んでいきます。
では、なぜこの作品は今も読み継がれ、「乱歩作品の中で一番無難な短編」とまで作者自身に評されたのでしょうか?
ここではまず、『押絵と旅する男』がもつ文学的な魅力と創作背景についてひも解いていきます。
幻想文学の傑作として読み継がれる理由
江戸川乱歩といえば「明智小五郎」シリーズや本格ミステリーのイメージが強いですが、『押絵と旅する男』は、推理よりも幻想と怪異の美学が際立った作品です。発表は1929年。雑誌『新青年』6月号に掲載されました。
物語は、蜃気楼を見に訪れた「私」が、帰りの汽車で出会ったひとりの男と語らう形式で進行します。
男が持つ“押絵”と“遠眼鏡”、そこに秘められた不思議な過去。現実と非現実の境界線を曖昧にする構成は、まさに幻想文学の醍醐味そのものです。
幻想的な雰囲気を支えるのは、舞台描写の緻密さと静謐な語り口。
魚津の蜃気楼、浅草十二階(凌雲閣)、そして遠眼鏡が映す“異界”の景色――これらすべてが、まるで夢とうつつの狭間に立たされているかのような感覚を読者に与えます。
また、今なお多くの読者に読み継がれている理由として、「感情的なリアリティ」も挙げられます。
押絵の娘に恋をし、絵の中へ消えていく青年。その姿には、不気味さと同時に、切実な愛や孤独もにじみ出ており、読む人の心に残る余韻を生んでいるのです。
乱歩が語った「一番無難な短編」とは?
江戸川乱歩自身は、作品に対して非常に自己批判的だったことで知られています。ところが、この『押絵と旅する男』については、珍しく次のような肯定的コメントを残しています。
「ある意味では、私の短篇の中ではこれが一番無難だといってよいかも知れない」
“無難”という言葉には少し控えめなニュアンスがありますが、これは乱歩なりの“完成度への自信”とも受け取れる。
実際にこの作品は、ミステリーやホラー、恋愛、幻想といった要素がバランスよく織り込まれた、構成的に非常に整った短編です。
また、当時の乱歩は創作に行き詰まりを感じており、実際に一度書いた初稿を破り捨ててしまったというエピソードもあります。しかしその後、編集者・横溝正史の働きかけで再び筆をとり、現在の『押絵と旅する男』として結実しました。
つまり本作は、“乱歩の幻想文学”の完成形としてだけでなく、作家・乱歩が創作への信頼を取り戻した一作でもあるのです。
『押絵と旅する男』のあらすじを解説【ネタバレあり】
ここからは『押絵と旅する男』のあらすじを物語の流れに沿って詳しく解説していきます。
あくまで作品の構造やテーマを理解するための“ガイド”として書いていますが、結末までの核心にも触れているため、未読の方はご注意ください。
蜃気楼の帰り道、不思議な老人との出会い
物語の語り手である「私」は、富山県の魚津で蜃気楼を見た帰り道、上野行きの汽車に乗ります。
車内はがらんとしており、同じ二等車には、もう一人だけ――年齢不詳の不気味な男がいるだけでした。
ふと見ると、その男は風呂敷から妙な“額縁”のようなものを取り出し、窓辺に立てかけています。不思議に思った「私」はついその男に近づき、会話が始まる。男は、こちらの興味を見抜いたかのように言います。
「これが見たかったんでしょう?」
男が見せたのは、泥絵具で描かれた背景に、白髪の老人と若い娘が立体的に貼りつけられた「押絵」でした。それはあまりにも精巧で、まるで本当に生きているような気配を放っていたのです。
“生きている押絵”と双眼鏡の秘密
「私」が驚いていると、男はさらに一つの道具――古びた遠眼鏡(双眼鏡)を手渡します。「この双眼鏡で押絵を見てみてください」と促す男。ただし、注意があります。
「絶対に逆さに覗いてはいけません」
やや警戒しつつ、言われたとおりに覗いてみると、驚くべきことに押絵の人物がまるで“実在の人間”のように生気を帯びて見えたのです。
白髪の老人は苦しげな表情で、若い娘は妖艶な色香を漂わせている――そんな不思議な映像に、私は思わず息を呑みます。押絵がただの飾りではない、何か“秘密”を抱えていることを確信した瞬間でした。
男が語る兄の身の上話|二次元に恋した青年の行方
この押絵の謎を解く鍵――それは男が語る、“兄”の過去にありました。
今から30年以上前、男の兄は25歳の若者でした。ある日、浅草の観光名所「十二階(凌雲閣)」の上から、双眼鏡を使って下界を眺めていると、人混みの中にひとりの美しい少女の姿を見つけます。
それは一瞬の出来事でしたが、兄はその少女に強く惹かれ、それからというもの、毎日のように双眼鏡を手に浅草を訪れるようになります。
やがて彼は気づきます――その少女は「覗きからくり」の中に登場する押絵の人物だったことに。そして、兄は弟にこう言います。
「たった一度でいい。この娘の隣で生きてみたい」
兄は絵の中へ消えた…押絵になった男の最期
そして迎えた、運命の瞬間。
兄は弟に「自分の姿を遠眼鏡で逆さに覗いてほしい」と頼みます。最初は戸惑った弟ですが、兄の熱意に押されて言われた通りにします。
その瞬間、兄の姿がどんどん小さくなり、ついには闇の中へと消えてしまったのです。
驚き混じりに「覗きからくり」を見直してみると、そこには――
押絵の娘の隣に、兄の姿が加わっていた。
兄は自らの意思で押絵の世界に入り込んだのです。
以後、弟は兄を連れて旅をすることにしました。兄と娘が二人で過ごせる時間を少しでも与えたい――その思いから、押絵を風呂敷に包み、あちこちの景色を見せて回るようになります。
変わらぬ少女と、老いてゆく兄──旅を続ける弟の想い
押絵の中に入り込んだ兄と少女。最初のうちはまさに「新婚旅行」のように幸せそうだったと、男は語ります。
ところが年月が過ぎるうちに、押絵の中の兄だけが老いていくという異変が起こり始めます。
少女は押絵に“最初からいた存在”であるため、年を取りません。しかし兄はあくまで人間――たとえ押絵になったとしても、老いという運命からは逃れられなかったのです。
今では押絵の中で白髪になり、苦悶の表情を浮かべている兄。その姿を、弟は痛ましく見つめながらも、今日もまた旅を続けています。
汽車がとある小駅に停まったとき、男はふと立ち上がりこう告げます。
「今夜はここで兄たちを休ませます」
そのまま額を抱えて車外へと消えていった彼の背中は――押絵の中の老人と、まったく同じ形をしていたのでした。
ここがすごい!『押絵と旅する男』3つの読みどころ
『押絵と旅する男』は、ただの“奇妙な話”ではありません。
幻想と現実が入り混じる世界観の中で、江戸川乱歩ならではの構成力やモチーフの使い方が光ります。
ここでは、特に注目すべき3つのポイントを紹介します。
幻想と現実の境界をぼかす緻密な構成
この物語の最大の魅力は、「現実」と「幻想」の境目がいつの間にか曖昧になっていく構成にあります。
冒頭では「蜃気楼を見に行った記憶が夢だったのでは?」という語りから始まり、次第に「生きているような押絵」「消えた兄」「年老いていく押絵の中の人間」へと展開していきます。
読者は気づけば、どこまでが現実で、どこからが幻想なのか見失っていく。これは単なる奇想ではなく、語りのリアリティを最大限に利用した緻密な仕掛けです。
語り手の「私」すら信じられなくなるような不安定さが、読後もじわじわと余韻を残します。
浅草十二階と蜃気楼──“崩れてゆく世界”の象徴
『押絵と旅する男』には、「崩れてゆく世界」を象徴するふたつの建造物/自然現象が登場します。それが、魚津の蜃気楼と浅草十二階(凌雲閣)です。
蜃気楼は、存在しない景色が空中に浮かび上がる現象。そして浅草十二階は、かつて実在した東京のランドマークでありながら、関東大震災で崩壊した建物。
作中で兄が見た押絵の少女も、実体があるようでいて存在しない――実像と虚像のあいだに揺れる存在です。
これらのモチーフはすべて、“不安定な現実”や“失われるものへの執着”を象徴しており、物語に深い陰影を与えています。
遠眼鏡がつなぐ「絵」と「人間」の禁断の世界
本作において「遠眼鏡(双眼鏡)」は、ただの小道具ではありません。
それは、この世と“あの世”をつなぐ鍵であり、押絵という“二次元”に入り込むための通路として機能します。
兄はこの遠眼鏡を通して押絵の少女に恋し、やがて自らの意志でその中に入り込んでしまう。現実から絵の中へ、三次元から二次元へ――この逆転こそが本作最大の“禁断の跳躍”です。
また、弟が「遠眼鏡を逆さにして兄を覗いた」瞬間に兄が絵の中へ消えるという展開は、まさにレンズによる現実の変容=“境界の崩壊”を象徴するシーンといえるでしょう。
考察|『押絵と旅する男』が語る“永遠の愛”と“老いの残酷さ”
『押絵と旅する男』は、不思議な出会いや幻想的なモチーフの背後に、切実なテーマを内包しています。それは、「変わらぬ愛」への願望と「老いゆく自分」との向き合い方。
現実と幻想のあわいに消えた兄の運命をたどるとき、私たちは「美しさ」「若さ」「愛」の本質について、否応なく考えさせられるのです。
なぜ兄は押絵になったのか?その願いの行方
兄はなぜ“押絵の世界”に入ることを選んだのか?
それは、単なる現実逃避ではありません。兄の願いは「一度でいいから、あの娘の隣にいたい」「吉三になって、お七を抱きしめたい」という、たった一度の強烈な“恋の実現”だったのです。
彼にとって重要だったのは、“現実の女”と付き合うことではなく、遠眼鏡の中に見た幻想の彼女と一体になること。
押絵の世界は、「変わらない姿の彼女」と「触れ合える自分」が共存できる唯一の場所でした。
けれどその代償はあまりに大きく、兄は時間の流れだけを背負って、絵の中でひとり老いてゆくことになります。
絵の中でだけ若くいられるという恐怖
押絵の中の少女は、ずっと変わらない美しさを保っています。
それに対して、兄だけが時間の影響を受け、しわが増え、白髪となり、やせ細っていく――この対比は、“永遠の愛”という理想の裏に潜む残酷さを浮き彫りにします。
相手は変わらない。でも自分だけが老いてゆく。
これは「ずっと好きでいてほしい」という願いが、自分だけ取り残される恐怖に変わっていく過程でもあります。
美しさや若さを“変わらないもの”として理想化することが、どれほど身を削ることか。
兄の押絵の顔が、やがて苦悶と悲しみにゆがんでいくのは、「永遠の愛」の裏側にある苦しみを象徴しているのかもしれません。
あなたなら双眼鏡を覗くか?読者への問いかけ
物語の終盤、「私」が双眼鏡を手にした場面で、読者自身もひとつの選択を迫られているかのような感覚に襲われます。
もし目の前に、生きているような押絵と、世界の真実を映し出す“魔法のレンズ”があったなら、あなたはそれを覗くでしょうか?
逆さに持って、自分自身がその中に吸い込まれる可能性があると知りながら――。
「見たいけれど、見てはいけないもの」。
それがこの作品に通底する恐怖であり、魅力です。
現実の苦しさから逃れたいと願うことは、誰にでもあります。
でも、その先に待っているのが本当に「理想の世界」なのか、それとも「孤独と後悔」なのかは、誰にもわかりません。
それでも、「あの双眼鏡を、もし自分が手にしたら…」という想像をしてしまう。
この物語は、読者にそんな個人的な誘惑と選択の余地を残して、静かに問いかけてきます。
読後におすすめ|『押絵と旅する男』の感想文はこちら
物語を読み終えたあと、「あの押絵は何だったのか?」「兄の選択は本当に幸せだったのか?」と、さまざまな感情が湧いてきた方も多いのではないでしょうか。
江戸川乱歩が描いた幻想世界は、読み手の心の深いところにそっと触れてきます。
そんな余韻の中でこそ読んでいただきたいのが、別記事でご紹介している読書感想文。
読者目線で語られた感想を通して、また違った角度から『押絵と旅する男』を味わっていただけるはずです。
🧭 ▶こちらの記事で紹介しています
👉 『押絵と旅する男』の読書感想文(準備中)
まとめ|『押絵と旅する男』は幻想と現実の“あわい”に迷い込む物語
江戸川乱歩の短編『押絵と旅する男』は、蜃気楼の幻想、押絵の中の人物、そして双眼鏡というレンズを通して、現実と非現実のあわいに立つ不思議な体験を描いた作品。
物語の語り手「私」は、現実の旅の途中で出会った老紳士とのやりとりを通じて、幻想の世界に足を踏み入れます。
けれど、その幻想は決して夢のような幸福ではなく、老い・喪失・永遠への憧れとその代償といった、どこか物悲しく、身につまされるテーマを内包しています。
最後に残るのは、「あの話は本当だったのか?」「押絵の中の兄は今も旅をしているのか?」という、確かめようのない不確かさ。
その曖昧さこそが、本作の魅力であり、読後にじんわりと心に残る感触でもあります。
もしまだこの作品を読んでいない方がいたら、ぜひ原文を読んでみてください。そして読了後には、ぜひ読書感想文の記事もあわせてご覧いただければ嬉しいです。
きっと、あなたの中でも「押絵の中の世界」が、ひっそりと動き出すはずです。
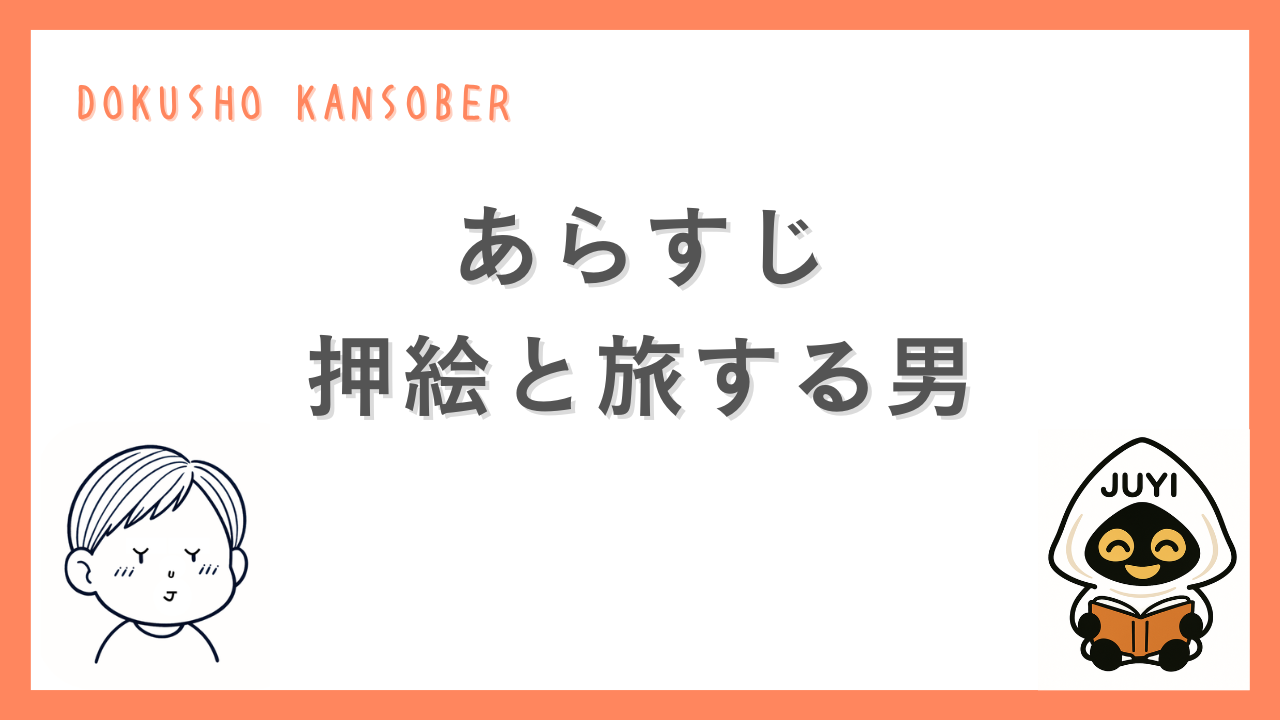



コメント