「読書感想文」と「小論文」、どちらも学校の課
題でよく出される文章ですが、目的や書き方には大きな違いがあります。
感想文は“心で書く文章”、小論文は“論理で伝える文章”と言えるかもしれません。
本記事では、2つの違いをわかりやすく整理し、それぞれの特徴や書き方を比較しながら解説します。
文章を書く前に一度読んでおくと、迷わずに書き進められるはずです。
読書感想文とは?
読書感想文とは、読んだ本の内容について自分が感じたことや考えたことを自由に書く文章です。
学校の宿題やコンクールなどでよく課されるこの課題は「読書を通じて何を感じ取ったか」「どう心が動いたか」を、自分の言葉で表現することを目的としています。
感想文には「正解」や「間違い」がなく、自分の素直な感情や気づきを中心に構成されます。
そのため、他人と同じ本を読んだとしても、まったく異なる感想が生まれるのが特徴です。
目的は「感じたこと」を自由に表現すること
読書感想文の一番の目的は、本を通して感じた自分の気持ちを自由に表現することです。
「面白かった」「悲しかった」「モヤモヤした」など、感情そのものに正解はなく、どんな気持ちでも大切にされます。
たとえば、登場人物に共感したり、物語の展開に驚いたり、価値観を揺さぶられたり──。そうした感情を素直に書き出すことが、感想文の出発点です。
評価されるポイントも、論理性や正確性よりも、「どれだけ自分の言葉で語られているか」にあります。
本のあらすじ+自分の気持ちの流れが中心
感想文には、本の内容をまったく書かないわけにはいきません。
しかし、あらすじはあくまで「自分の感想を伝えるための前提」として必要なだけです。
よくある流れは、以下のようなものです。
- 読んだ本の簡単なあらすじ
- 特に印象に残った場面やセリフ
- その場面で自分が感じたこと・考えたこと
- 読み終えたあとの気持ちや、自分の生活との関わり
このように、あらすじと感情の流れをバランスよく書くことで、読み手にも共感されやすい感想文になります。
共感・感動・気づきが大事なポイント
読書感想文では「どこに心が動いたか」が最も重要なポイントです。
登場人物への共感、物語の展開に対する驚き、あるいは自分の過去と重なる気づきなど──。
そうした“心の動き”を文章にすることで、感想文に深みが出てきます。
たとえば、「主人公の勇気ある行動に感動した」というだけでなく、「自分が同じ立場だったらどうするか」「これまでに似た経験をしたことがあるか」などを交えて書くと、オリジナリティのある文章になります。

つまり、「本の内容」よりも、「それを通して何を感じ、考えたか」が感想文の中心になるのです。
小論文とは?
小論文とは、あるテーマや課題に対して自分の意見を述べ、それを論理的に展開する文章です。
読書感想文と異なり、感情や印象に頼るのではなく、「なぜそう思うのか?」という理由や根拠を明確にしながら書いていく必要があります。
入試や就職活動、大学のレポートなどでも頻繁に求められる小論文は、論理的思考力や表現力、社会的な視点が問われる文章形式です。
自分の意見を論理的に伝える文章
小論文の中心は、自分の意見を相手に納得してもらえるように、論理的に伝えることです。
「私は○○に賛成だ」「○○は改善すべきだ」といった主張を提示し、それに対する理由や具体例を挙げて展開していきます。
ここで大切なのは、感情的な表現ではなく客観性のある伝え方です。
たとえば「私は悲しくなったから反対です」ではなく、「その制度には格差を助長する側面があるため反対です」といったように、筋道の通った主張をすることが求められます。
テーマに対して理由と根拠を明確にする
小論文では、意見だけでなくその理由や根拠を具体的に示すことが重要です。
読者(採点者)は「あなたがそう思うのはなぜか?」を常に見ています。
たとえば「SNS利用は制限すべきだ」という意見を述べる場合は、
- 若者の睡眠時間の減少
- ネットいじめの増加
- 学力への影響に関する調査結果
など、データや事実、実例を挙げながら説得力を高めていく必要があります。
これは、単なる「思いつき」ではなく、情報や論拠に基づいて考えられた意見であることを示すためです。
構成は「序論→本論→結論」が基本
小論文では、明確な文章構成が求められます。
基本的な型は以下の通りです。
| 構成 | 内容の要点 | 説明 |
|---|---|---|
| 序論 (導入) | 問題提起・背景説明・主張の提示 | テーマに関する関心を引き、なぜその話題が重要かを説明します。自分の考え(主張)を簡潔に伝えることもあります。 |
| 本論 (展開) | 主張の理由・根拠・具体例 | 主張を支える理由や根拠を示し、具体的な事例やデータを交えて論理的に展開します。段落ごとにポイントを明確にするのが効果的です。 |
| 結論 (まとめ) | 主張の再確認・印象的な締め | 話の流れを簡潔にまとめ、主張を再度確認します。読者の心に残る言葉で締めくくると効果的です。 |
この流れに沿って書くことで、読み手にとって理解しやすく説得力のある文章になります。
感情を語る感想文とは異なり、論理の流れで「納得してもらう」ことが目的の文章なのです。
読書感想文と小論文の違いを比較しよう
ここまでの内容をふまえて、読書感想文と小論文の違いをあらためて整理してみましょう。
どちらも「自分の言葉で書く文章」ですが、目的や表現方法、構成に大きな違いがあります。
それぞれの特徴を正しく理解することで、書き分けがしやすくなります。
主観と客観のバランスが異なる
最大の違いは、「主観」と「客観」の比重にあります。
読書感想文は自分の感じたこと=主観が中心です。
心が動いた場面や印象に残った言葉など、個人の感情に焦点を当てて書かれます。
一方、小論文は客観的な根拠にもとづいた意見が求められます。
「自分はこう思う」だけでなく、「なぜそう考えるのか」をデータや事例などで裏づける必要があります。
つまり、感想文では「私はこう感じた」でOKですが、小論文では「私はこう考える。なぜなら~だから」と論理がセットで求められるのです。
書き方のルールや構成も違う
書き出しからまとめ方まで、文章全体の構成にも明確な違いがあります。
| 項目 | 読書感想文 | 小論文 |
|---|---|---|
| 目的 | 感じたことを自由に書く | 意見や主張を論理的に述べる |
| 書き出し | 心に残った場面や気持ちから始まることが多い | 問題提起やテーマの説明から入る |
| 構成 | あらすじ→感想→気づき(自由な流れ) | 序論→本論→結論(明確な三部構成) |
| 文体 | 「~と思った」「~と感じた」など主観的 | 「~と考える」「~という見方もある」など客観的な表現が多い |
| 評価のポイント | 感情の深さ・共感性 | 論理性・説得力・根拠の明確さ |
このように、構成・目的・使う言葉のトーンまで、まったく異なる形式であることがわかります。
例文で見る違い
実際に同じテーマに対して「読書感想文」と「小論文」でどう書き分けるかを見てみましょう。
📝テーマ:戦争を扱った作品『かわいそうなぞう』(小学校向け)を読んで
戦争のせいで動物たちが殺されてしまうという話を読んで、とても悲しい気持ちになりました。私は、動物たちには何の罪もないのに、どうしてこんなことが起きるのかと考えました。もし自分がその場にいたら、象たちを守りたかったと思います。戦争は人間にも動物にも、たくさんの苦しみを与えるものだと感じました。
戦争によって人間だけでなく動物の命も奪われるという点は、平和の大切さを再認識させる。『かわいそうなぞう』のような実話に触れることで、子どもたちが戦争の残酷さを身近に感じ、命の尊さを学ぶ機会となる。教育現場では、このような作品を通じて命や平和について考える授業を積極的に取り入れるべきだと考える。

このように同じ本でも「感情を表現する」のが読書感想文、「意見と根拠を述べる」のが小論文だということが、例文からもはっきりとわかります。
まとめ|どちらも「自分の言葉で伝える」ことが大切
読書感想文と小論文は、目的も書き方も大きく異なります。
感想文は「何を感じたか」、小論文は「どう考えたか」。
感情と論理、主観と客観、それぞれに重きを置いています。
しかし共通しているのは、どちらも「自分の言葉で、自分の考えを伝えること」が求められるという点です。
誰かの意見をそのまま写すのではなく、自分なりに本を読み、テーマと向き合い、思ったことや考えたことを表現する──そこにこそ、その人らしい文章の価値があります。
課題として出された文章を書くとき、「これは感想文?それとも小論文?」と迷うこともあるかもしれません。
そんなときは目的や構成の違いを意識しつつ、自分の考えに誠実に向き合う姿勢を忘れなければ、きっと伝わる文章が書けるはずです。
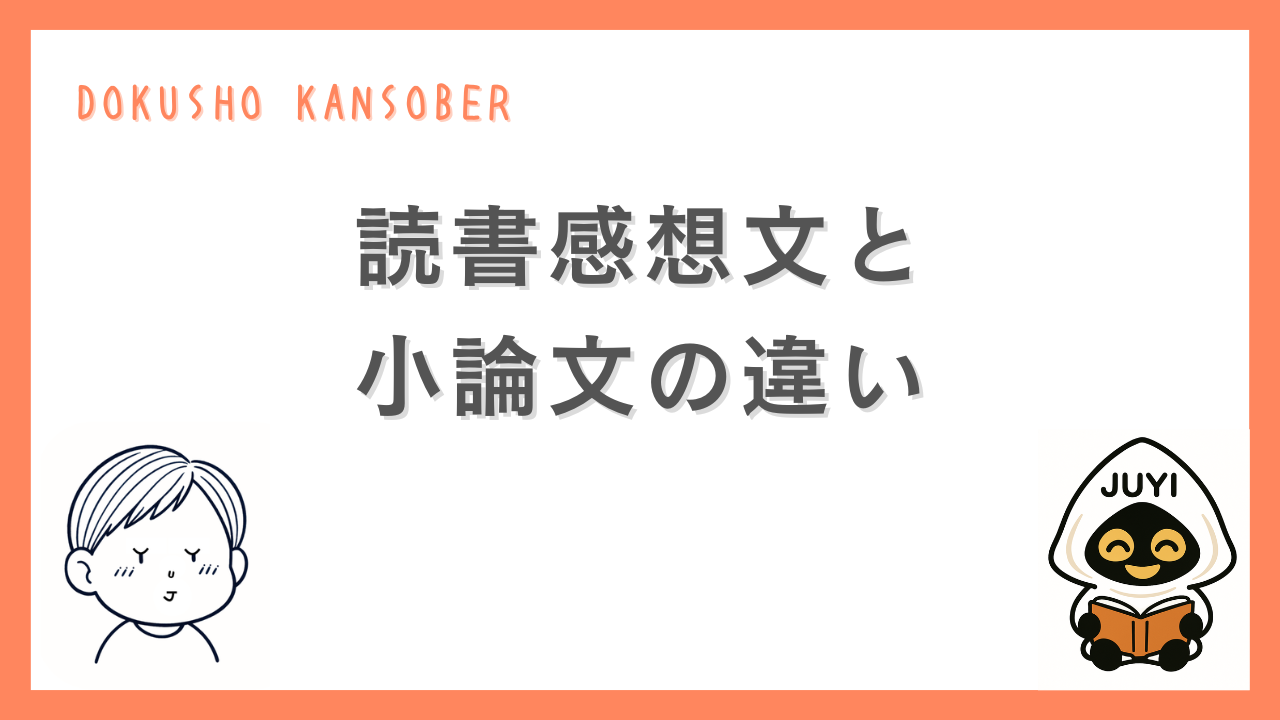

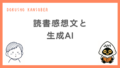
コメント