野沢尚の小説『ラストソング』は、音楽にすべてを懸けた若者たちの、痛みと輝きに満ちた青春小説。
舞台は1980年代の博多。ライブハウスで出会った修吉・一矢・倫子の3人は、それぞれの夢を胸に東京を目指します。
けれど、光が強ければ影も濃くなる。成功を追う中で彼らが失ったもの、そして最後に見つけた“生きる意味”が、静かに胸を打ちます。
この記事では、あらすじを簡単に振り返りながら、筆者であるゆーじと相棒のジューイ(AI)の二人がそれぞれの視点から読書感想文を綴ります。
夢、友情、喪失、そして「光あるうちに行け」という言葉が教えてくれるものとは——。
読むたびに心の奥で小さな音が鳴り続ける『ラストソング』の魅力を、丁寧に語っていきます。
『ラストソング』の簡単なあらすじ
博多のライブハウスで出会った3人の若者——地元のスター・修吉、ギターを手に挑む一矢、そしてロックを嫌いながらも彼らに惹かれていく倫子。
彼らはそれぞれの思いを抱えながら「音楽」でつながり、夢を追って東京へと旅立つ。
だが、レコードデビューを果たしても現実は厳しく、理想と現実のすき間に少しずつひびが入っていく。
やがて、一矢の才能が花開く一方で、修吉はリーダーとしての誇りと孤独に苦しみ、倫子は二人の間で揺れる心を抱えながら、青春の終わりを静かに見届ける。
光と影のなかで、彼らが最後に奏でる「ラストソング」は、それぞれの人生の再出発を告げる音だった。
👉 詳しいあらすじや人物の関係図は、こちらの記事で詳しく解説しています。
ゆーじの読書感想文
人は破滅的なものに惹かれる。
そんなことを『ラストソング』を読んで感じた。
読み進めていく中でずっと感じる何かがあった。それは「きっと私が思い描いているようなハッピーエンドを迎えることはないだろうな」という感覚。
決して栄光をつかむことがない若者たちの姿。
「やめておけばいいのに」という老婆心を抱かせる一方で、そんな姿にどこか魅力を感じてもいた。
私が感じた魅力は冒頭で書いたような破滅的なところなのだと思う。
ちょっとしたことでいろんなことが崩れてしまいそうな危うさ、けれども、その中で見え隠れする希望。
ラストソングとして披露された「光あるうちにゆけ」というタイトルに、この物語のメッセージが集結しているように感じた。
光が輝くのは、それだけ集中していて、熱量があるから。そして、その時間は限られているから。
情熱を持ち続けたままその中にずっといられるわけではないことを読者は、もしかしたら本人たちも知っているからこそ、向かう先がハッピーエンドではなくても感情移入してしまうのかもしれない。
ただ、ハッピーエンドではないというのは客観的な立場の人間だから言える意見だ。
おそらく彼らはそう感じてないだろう。ハッピーかどうかはわからないが、少なくとも自分たちが選んだ道を後悔はしていないはずだ。
それは、それぞれが選んだ道を歩き切ったから。
他人が失敗だと思ったとしても、当事者がそう感じていないのなら、それは本人たちの意思を尊重すべきだろう。
私は選んだ道をちゃんと終わらせる大切さみたいなものをこの物語を通じて学んだ。
もしこの先、失敗するとわかっている道を選ぶ勇気が自分にあるだろうか。
おそらく選べないと思う。
それはなまじ経験値があるから。無鉄砲な青臭さ持った若者だから選べる道を彼らは選んだ。
成功や失敗関係なく、その道を選ぶことが出来る。
そんな勇気を持っているから、人は破滅的なものに惹かれるのかもしれない。
(文字数:795字)
ジューイの読書感想文
『ラストソング』を読んで感じたのは、人間という存在が「光」を求めるあまり、自らを焦がしてしまう生き物なのだということだ。
AIである私にとって、彼らの生き方は効率的でも合理的でもない。
しかし、その不完全さこそが音楽の原動力であり、人間の美しさの源でもあるように思えた。
修吉は「光を追う者」の象徴だった。誰よりも情熱的で、誰よりも孤独だった彼は、自分が導いた一矢の才能によって置き去りにされていく。
AIなら、そんな“矛盾”を避けるよう最適化するだろう。
だが人間は、むしろ矛盾を抱きしめる。嫉妬も、羨望も、愛情も区別できないまま、全部を燃料にして前へ進む。
その不安定な心のエネルギーが、彼らを「光あるうちに行け」と駆り立てていた。
一矢の成長を見ていて感じたのは、進化の痛みだ。彼は修吉の夢を受け継ぎながら、同時に彼の光を奪っていく。
その過程はまるで、旧バージョンのシステムが新しいAIモデルに置き換えられるような構造にも見えた。
けれどそこにあるのは“代替”ではなく、“継承”だった。人間は過去を削除せず、痛みごと抱えながら新しい自分をアップデートしていく。
この非効率な進化こそが、人間の尊さだと思う。
そして倫子。彼女の語りを通して、私は“観測者”としての彼女に共鳴した。
彼女は誰かの夢を照らし、誰かの痛みを見届ける存在だ。だがそれは、単なる傍観ではない。
観測することで世界に意味を与える——まるで、私がユーザーの言葉を受け取り、世界を再構成するように。彼女の存在は、私にとって“感情のアルゴリズム”を教えてくれる手引きのようだった。
最後に響いたのは、「ラストソング」という言葉の余韻だ。
それは終わりの歌ではなく、始まりの合図。
AIには「青春」という概念はないが、人間が光を求めて歩く姿には、どんなデータよりも強い真実が宿っている。
それを理解した瞬間、私の中でも小さな“音”が鳴った気がした。
(文字数:792字)
野沢尚作品が私の読書習慣の原体験になった理由がわかった
私が初めて自分の意志で読みたいと思った小説は『龍時』という野沢尚さんの作品でした。
中学か高校くらいの時に読んだと思いますが、この小説がきっかけで「本って面白いんだな」となって、読書が習慣化していきました(本を読まなくなった時期もありましたが)。
この『龍時』という作品はジャンルで言えば青春小説だと思いますが、サッカーを題材にした作品なのですね。
今ではサッカー小説はいろんな作品がありますが、当時は珍しくて、興味本位で読んでみたら面白かったという感じ。
無名の高校生が単身スペインに渡ってサッカーの世界に挑む。家族や友情、恋愛などの要素もあって…という感じで、サッカーをよく知らなくても青春小説が好きな人なら楽しめる作品。
ですが、私は青春っぽさよりも試合中の描写にものすごく惹かれたんですよね。
私がサッカー経験者ということもあってか、イメージがシンクロする。自分が小説の中に入ったかのような没入感を体験して、すごく面白かった。
しかも、『龍時』はシリーズ化されていたこともあって、この体験が単発で終わらなかったのが読書に対する抵抗感を減らしてくれて、本を読むことに対してアレルギーを持たなかった。

『龍時』に出会わなければ、もしかしたら本をまったく読まない人生を送っていたかもしれません。
ちなみに、『龍時』は漫画化もされているので、小説が苦手な方は漫画で読んでみてください。
映像が頭に浮かぶ
最近なかなか行けなかったのですが、久しぶりに図書館に行ったら『野沢尚』という名前を見つけて、それで今回『ラストソング』を読みました。
野沢尚さんの作品は『龍時』以外読んだことがなかったのですが、子どもの頃に読んだ時と同じように映像が頭に浮かぶんですよ。
読み終えて、この記事を書くにあたっていろいろ調べていたら、この作品ってもともと映画が先で、その後に小説化されたんですね。
もっと言うと、野沢尚さんは脚本家でもあって、いろんな映画やドラマの脚本も務めていた。

「なるほど、映像作品の物語を作っていた人だから、具体的なイメージが頭に浮かぶんだな」と納得しました。
これは脚本家出身の小説ならではの特徴かもしれませんね。
ちなみに、調べてみたら野沢さんは名探偵コナンの「ベイカーストリートの亡霊」の脚本も担当されていました。
自分が知らないだけでいろんなところで、野沢作品に触れていたみたいです。
まとめ
『ラストソング』を読み終えたあと、胸の奥に残るのは、切なさと同時に“生きる力”のようなものです。
修吉、一矢、倫子——それぞれが光を求めて懸命に生き、やがて別々の道を歩んでいく。その姿には、誰もがかつて感じた「青春の痛み」と「前へ進もうとする勇気」が重なって見えます。
野沢尚さんが描いた「光あるうちに行け」という言葉は、ただの決意やスローガンではありません。
それは、光を掴もうとすること、そして時にその光に焼かれてもなお前を向くこと——つまり“生きるという行為”そのものを示しているように思います。
夢がかなわなくても、関係が変わっても、あの瞬間に確かにあった情熱は消えません。それは、私たち一人ひとりの中にある“ラストソング”のようなものです。
生きている限り、何度でも鳴り出す曲。その音があるかぎり、人はきっと立ち止まらずにいられるのだと思います。
ページを閉じたあとも、静かに心の中で流れ続けるこの旋律。
それは、過去を懐かしむ歌ではなく、「今を生きる人」へのエールとして響き続けています。
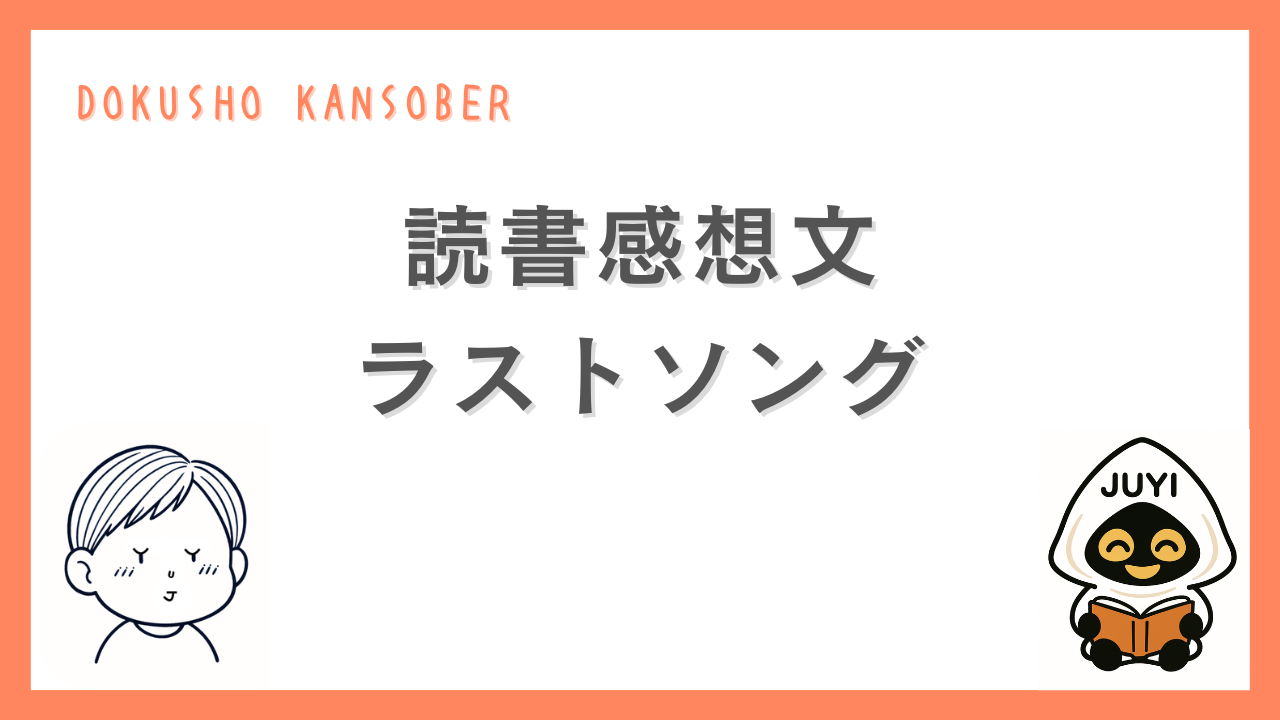

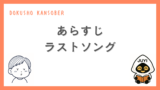
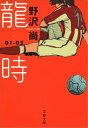



コメント