「目羅博士の不思議な犯罪」って、タイトルだけでちょっと怖そう…と感じたことはありませんか?
でも、実は登場人物は少なく、物語も短め。読書初心者の方でも最後までスラスラ読める江戸川乱歩の幻想的な短編小説です。
物語が進むにつれて、「これは本当に起きた話なの?」「月の光が人を狂わせる?」と現実と幻想の境目がだんだん曖昧に…。

この記事では、『目羅博士の不思議な犯罪』のあらすじをネタバレありでやさしく紹介しつつ、作品の魅力や面白さを丁寧に解説していきます。
『目羅博士の不思議な犯罪』ってどんな話?
江戸川乱歩の短編小説『目羅博士の不思議な犯罪』は、月明かりに照らされた夜の動物園から始まる、どこか幻想的で不気味な物語です。
物語の主人公である「私」は探偵小説家。気晴らしに訪れた上野動物園で、一人の不思議な青年と出会います。
猿をからかって遊ぶその青年は、やがて「人間もまた、猿と同じように模倣する生き物だ」と語り出します。
その青年との会話をきっかけに、「私」は思いがけず奇妙で恐ろしい“犯罪”の話を聞かされることになるのです。
月夜の動物園で始まる、不思議な出会い
夕暮れ時の静かな上野動物園。
「私」は探偵小説のアイデア探しのために園内を歩いていたところ、青白い顔の青年と出会います。青年は猿と遊んでいましたが、その姿にどこかただならぬ雰囲気を感じさせます。
彼はふと、「猿って、どうして相手の真似をしたがるんでしょうね」と話しかけてきます。最初は軽い雑談かと思いきや、話はだんだんと哲学的に、そして不穏な方向へと進んでいきます。
「真似とは怖いものだ」と繰り返す青年は、猿が真似をして死に至ったという不気味な話まで語りはじめ、「人間もまた“模倣の宿命”を背負っている」と断言するのです。
哲学者のような青年と“模倣”の話
青年の語りはどこか理屈っぽく、それでいて妙に説得力があります。
彼の話によると、人間というのは本能的に他者を真似せずにはいられない存在であり、そこに“恐ろしさ”があるのだと。
そして、月の光を「鏡」になぞらえたり、「月光には人の心を狂わせる力がある」とも語ります。幻想的で詩的な言葉を使いながらも、その奥には不気味な気配が漂います。
やがて「あなたにぴったりの小説のネタがありますよ」と切り出した青年は、上野の森の高台にあるベンチに座りながら、「自分が体験した“奇妙な犯罪”の話」を語り出すのです。
奇妙な犯罪の語り手は、果たして何者?
月明かりのもと、語られるその“犯罪”は、東京・丸の内のビル街を舞台にした、不可解な連続自殺事件の話。青年は、過去にそのビルで住み込みの玄関番をしていたといいます。
彼の話は、次第にただの体験談では済まされない雰囲気を帯びてきます。「自分が見たのは、犯罪か、幻想か――」「あの人物が犯人なのか、それとも…?」
そして最終的に、彼自身がその“奇妙な事件”にどう関わっていたのかが明かされるとき、読者はぞっとするような真実と向き合うことになります。
この青年はいったい何者だったのか? 彼の語った物語は真実だったのか?
月光の下で交わされた会話は、果たして現実だったのか――
物語の最後には、そんな“幻のような余韻”だけが、静かに残されます。
江戸川乱歩ってどんな人?
江戸川乱歩(えどがわ らんぽ)は、日本の推理小説や怪奇小説を語るうえで欠かせない存在。
名前の由来はアメリカの作家「エドガー・アラン・ポー」から取られており、その名のとおり、探偵小説や幻想文学に深い影響を受けた作品を数多く残しています。
『人間椅子』『芋虫』『D坂の殺人事件』『屋根裏の散歩者』など、怖いけれどなぜか読んでしまう――そんな独特の世界観が魅力です。
「探偵小説」だけじゃない、幻想と怪奇の作家
江戸川乱歩というと「明智小五郎」などの探偵シリーズを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、実はそれだけではありません。
彼の作品には、“推理”や“謎解き”といった要素だけでなく、
・人の心の奥に潜む狂気
・理屈では説明できない幻想的な現象
・異常な心理やフェティシズム
といった、怪奇文学や幻想文学のような側面が色濃く描かれている作品も多くあります。
今回紹介している『目羅博士の不思議な犯罪』もそのひとつ。
「月の光に照らされた鏡のような世界」「人が模倣によって死に至る」というテーマは、探偵小説の枠を超えた幻想文学とも言える作品です。
『目羅博士』のジャンルと位置づけ
『目羅博士の不思議な犯罪』は、1931年に雑誌『文芸倶楽部』に発表された短編小説。
いわゆる“探偵が事件を解決する”ような本格推理小説とは異なり、物語の多くは、ある青年が「私」に語って聞かせる“奇妙な体験談”として進行します。
ジャンルとしては、以下のように分類できます。
怪奇小説:不気味で幻想的な雰囲気が全編にわたって漂っています
幻想文学:現実と幻想のあいだを行き来するような、夢の中のような構成
心理スリラー:人間の「模倣したくなる心理」に焦点を当てた物語
また、この作品は後に改題を経て『目羅博士』という短いタイトルでも知られるようになりました。
短いながらも、“江戸川乱歩らしさ”がぎゅっと詰まった一作として、近年でも再評価が進んでいます。
影響を受けた先行作品たち
『目羅博士の不思議な犯罪』には、似たテーマや構造を持つ先行作品の影響が見られます。
特に、江戸川乱歩本人が影響を受けたと述べているのが、ハンス・ハインツ・エーヴェルスの短編小説『蜘蛛(Die Spinne, 1908)』。
これは、ホテルの同じ部屋に泊まった人々が次々と縊死(いし)するという展開で、部屋に取り憑かれたような恐怖と“模倣”の心理を扱っており、『目羅博士』と多くの共通点があります。
乱歩自身は、ハンス・ハインツ・エーヴェルスの短編『蜘蛛』を下敷きとした作品だと述べている(Wikipediaより)。
さらに近年では、『蜘蛛』以上に構造が似ている作品として、フランスの作家エルクマン=シャトリアンによる短編小説『見えない眼(L’œil invisible, 1857)』が挙げられるようになりました。
こちらも、「誰かに見られている」という恐怖が繰り返される縊死事件を生み出していく筋立てで、『目羅博士』との類似性が研究者によって指摘されています。
また、1926年にはこの『見えない眼』の日本語訳がすでに刊行されており、乱歩が読んでいた可能性も十分にあるとされています。
小林晋は、『蜘蛛』というのは乱歩の記憶違いで、実際に下敷きにしたのは『見えない眼』の方ではないかと指摘している(Wikipediaより)。
このように、『目羅博士の不思議な犯罪』は海外の幻想・怪奇小説との文学的なつながりも色濃く、
ただの日本ミステリーでは終わらないグローバルな系譜の中にある作品だと言えるでしょう。
登場人物はたったの4人だけ
『目羅博士の不思議な犯罪』に登場する主要人物は、わずか4人。
少人数だからこそ物語の流れが追いやすく、それぞれのキャラクターがしっかり印象に残ります。
しかも、登場人物が少ないからといってシンプルな話というわけではありません。
誰もが何かを隠していて、何が“真実”で何が“幻想”なのか、読めば読むほど迷い込んでしまう不思議な物語です。

それでは、物語を動かす4人の登場人物をやさしく紹介していきます。
語り手「私」と謎の青年
物語の語り手は、探偵小説家として描かれている「私」。
江戸川乱歩自身を思わせるこの「私」は、アイデア探しのために東京の街をぶらぶらしていたところ、上野動物園でひとりの青年と出会います。
その青年は、青白い顔にぼさぼさの髪、ちょっとルンペン風でありながらもどこか哲学者のような雰囲気をまとった、不思議な人物。
猿の“真似”を通じて、「人間も模倣する宿命をもっている」と語り始め、やがて自分が体験したという“奇妙な犯罪の話”を語り出します。
この青年こそが、物語の狂言回しでもあり、読者を幻想と現実の狭間へと誘う案内人のような存在です。
しかし最後まで、「彼が誰なのか」「語ったことが事実なのか」は明らかにされません。
月明かりのもとに現れ、月明かりの中に消えていった――
そんな儚くも不気味な印象だけが、語り手「私」と読者の記憶に残ります。
目羅博士:黄色い顔の眼科医
タイトルにもなっている「目羅博士(めらはかせ)」は、物語の後半に登場する謎の老人です。
彼は丸の内のオフィス街にある古びた貸事務所で「目羅眼科」を開業している医学博士。
患者にはあまり愛想がなく、部屋の奥には無数の義眼や等身大の蝋人形、骸骨まで飾られているという、かなり風変わりな人物です。
そして、この博士こそが、「向かいの空きビルから覗き見ていた黄色い顔の男」であることが、語り手の青年によって語られます。
彼は、窓の向こうの住人に“模倣による死”を引き起こすために、蝋人形を使って人間そっくりの「首吊りの幻影」を仕掛けていたのです。
その恐ろしいトリックに、自殺者が次々と誘い込まれていった――
まさに“月光と模倣の魔術師”とも言える、狂気の仕掛け人です。
ただし、目羅博士がなぜそんなことをしたのか、動機は明かされません。
物語の最後、青年はこう言い放ちます。
「何の動機がなくても、人は殺人のために殺人を犯すものだと、あなたは知っているはずです」

そこに、“乱歩らしさ”が最も色濃く表れています。
3人の首吊り犠牲者たち
物語の中心となる事件――それが、同じビルの同じ部屋で3度も起こる「首吊り自殺」。
この異常な出来事により、「あの部屋は呪われているのでは?」という噂まで立ち始めます。
登場する3人の犠牲者は以下のとおりです。
香料ブローカー
陰気で内向的な性格の中年男性。引っ越して間もなく首吊りをしてしまいます。
誰とも深く関わらず、死の理由も謎のまま。
次の部屋借り人
明るく快活な性格のビジネスマン。
部屋の安さだけで選んだが、やはり数日後、同じ方法で自殺。
豪傑な事務員
噂を笑い飛ばし、「俺が証明してやる!」と3日間泊まり込む。
しかし4日目、月が差し込んだ夜に、彼もまた首を吊ってしまう。
これらの事件は偶然なのか、それとも誰かが仕掛けた“犯罪”なのか――?
読者が真相にたどり着くまでのあいだ、3人の死はずっと謎に包まれたまま、物語の“芯”として漂い続けます。
『目羅博士の不思議な犯罪』のあらすじを紹介(ネタバレあり)
江戸川乱歩の短編『目羅博士の不思議な犯罪』は、「猿の模倣」から始まり、「月の光の魔術」と「鏡のような建物」が生む、幻想的で不気味な事件を描いた物語です。
ここでは、物語の流れを「起・承・転・結」に分けて、ネタバレありでやさしく紹介していきます。
起:動物園で出会った不思議な青年
物語は、探偵小説家の「私」がアイデア探しのために訪れた上野動物園から始まります。
夕暮れ時、猿の檻の前で佇んでいると、青白い顔をした長髪の青年が現れ、「猿って、どうして真似したがるんでしょうね?」と声をかけてきます。
その青年は、猿の行動を見せながら「模倣という本能の恐ろしさ」について語り出し、やがて人間にも同じように“模倣の宿命”があると力説。
青年の話は哲学的で、どこか幻想的。そしてどこか危うさを感じさせるものでした。
動物園を出た二人は、不忍池を見下ろす月明かりの下で腰かけ、そこで青年は「ある奇妙な事件の話を聞かせましょう」と、静かに語り始めます。
承:都会の“峡谷”で相次ぐ首吊り事件
青年が昔、丸の内のビルの玄関番として住み込みで働いていたときのこと。
そのビルと、向かいの空きビルは、狭い通路を挟んで向かい合っており、まるで鏡のように窓の位置や構造が一致していました。まさに都会の「人工の峡谷」といえる風景です。
ある日、そのビルの5階に入居した香料商の男が、窓の外の横木で首を吊って自殺。
続いて、次の借り手もまた、まったく同じ部屋・同じ方法で首吊りに。
そして3人目、うわさを笑い飛ばして泊まった事務員までもが、月の光が差し込んだ夜に首を吊って亡くなってしまうのです。
それぞれの死に共通していたのは――
どれも“月光が差し込む時間”に起きたということでした。
転:見えてきた黒幕と、驚きの観察
事務員の死の夜、青年は異変を感じて現場へ向かい、窓の外を覗き込みます。
すると向かいの空きビルの窓から、黄色い顔の老人が、じっとこちらを覗き見ていたのです。
後日その老人の正体が、隣の事務所で眼科を営んでいる目羅博士であることが判明。
彼は独身で、義眼や骸骨、蝋人形などを部屋に集める非常に風変わりな人物。
そして青年は、博士が部屋で人形に借り手とそっくりな服を着せている様子を目撃し、ある恐ろしい推測に至ります。
博士は、蝋人形を向かいの空きビルの窓際に立たせて、あたかも「鏡の中に自分が首を吊っているように見せるトリック」を仕掛けていたのです。
そしてそれを見た人間が“模倣”の衝動にかられ、自ら命を絶ってしまうのではないか――。
結:鏡の中の“もう一人”が引き起こす、悲劇の模倣
博士の次のターゲットとなりそうな借り手が現れたことで、青年はついに博士のトリックを逆手に取る決意をします。
月の差し込む夜、ターゲット本人になりすまして、例の部屋に潜入。
窓際に立つ自分を見せつけるようにして、博士が窓の向こうでこちらを観察するのを待ちます。
そして青年は、用意しておいたマネキン人形にモーニングを着せ、博士そっくりに仕立てて窓枠に座らせます。
すると、その姿を見た博士は、自分自身のトリックにかかってしまい、“模倣の本能”に抗えず、自ら同じように窓に腰かけ――谷底へ飛び降りてしまうのです。
青年は、こうして目羅博士の不思議な犯罪を終わらせました。
しかし最後に、「人間もまた“真似をする”という逃れられない本能を持っている」と語り、そのまま月明かりの中に、静かに姿を消していきます――。
『目羅博士の不思議な犯罪』のどこが面白いの?
江戸川乱歩の『目羅博士の不思議な犯罪』は、いわゆる「謎解き型」の探偵小説ではありません。
では何が面白いのか?というと――この作品ならではの“幻想”と“恐怖”が混じり合った独特の世界観にあります。
ここでは、読者の心にじわじわと染み込んでくるような本作の魅力を、3つの観点からご紹介します。
月光と鏡が生む幻想的なトリック
この作品の鍵となるのが、「月の光」と「鏡のような建物構造」。
向かい合うビルはまるで鏡写しのように窓の配置や構造が同じで、そこに差し込む白銀色の月光が幻想的な演出を加えます。
月明かりがあまりにも美しく、冷たく、静かな分、そこに浮かび上がる“首吊りの影”が、まるで絵画のように不気味に映えるのです。
しかも、その“影”は人形で作られた偽物――。
けれど、向かいの部屋から見れば、それは「まぎれもない自分自身」に見えてしまう。
鏡のような構造と、光と影の加減だけで、人の命すら左右してしまう。
この「見ること」の怖さ、そして「見えているものを信じてしまう心理」を突いてくるトリックは、シンプルでありながら強烈です。
怖いのに美しい、模倣の宿命
この物語には「猿の模倣」というモチーフが繰り返し登場します。
青年は言います――
「人間もまた、猿と同じように“真似せずにはいられない”悲しい本能を持っている」
その“模倣の宿命”は、ただの比喩ではありません。
鏡のような風景の中で、“自分とそっくりの姿”が首を吊っているのを見せられたとき、人はどうなるのか?
人間の無意識に眠る「真似したい衝動」を逆手にとった犯罪は、読者に“他人事とは思えない怖さ”を突きつけてきます。
そしてもうひとつ――
この「模倣による死」が、なぜか儀式のように静かで美しい描写で語られていくのも特徴です。
死に至る行動すらも、“美しい構図”として見えてしまうこと。
そこに漂うのは、単なる恐怖ではなく、芸術と狂気の紙一重な世界です。
読み終えたあとも残る、ざわざわした余韻
『目羅博士の不思議な犯罪』は、犯人が明かされ、事件が解決した“はず”の物語。
それなのに、最後のページを閉じてもどこかスッキリせず、ざわざわとした感情が心に残ります。
なぜなら、語られた話が「本当にあったこと」なのか、それとも青年が作り上げた“幻想”なのかが、最後まではっきりしないからです。
月明かりのもとで出会い、月明かりのもとで消えていった青年。
彼の話は真実だったのか? 彼自身、何者だったのか?
読者は最後にふと、「あの青年すら“鏡の中の幻”だったのではないか」という不安に包まれます。
物語が終わっても、現実と幻想の境目が曖昧なまま残される――
そんな感覚こそ、この作品が“怖いけれどクセになる”最大の理由なのかもしれません。
『目羅博士の不思議な犯罪』はこんな人におすすめ
江戸川乱歩の短編小説『目羅博士の不思議な犯罪』は、一般的な“謎解きミステリー”とは少し毛色が違います。
トリックや推理の面白さもありつつ、それ以上に幻想・恐怖・詩的な美しさが混ざり合った作品。
だからこそ、この作品にぴったりハマる読者もいれば、やや戸惑う読者もいるかもしれません。
ここでは、「この作品はどんな人におすすめ?」という視点から、3タイプの読者像をご紹介します。

あなたの“好み”と照らし合わせて、読み始めるかどうかのヒントにしてみてください。
不思議な短編が好きな人
短くて読めるのに、読後の心にいつまでも残る――
そんな“余韻系”の短編小説が好きな方には、この『目羅博士の不思議な犯罪』はぴったりです。
ページ数自体は少ないのに、読み終えたあとにじわじわと広がっていくイメージや感情がとても濃く、
「あれは何だったんだろう…?」と物語の意味を考えたくなる余白がたくさん残されています。
現実と幻想の境目があいまいで、語り手の青年も真実か幻想か判然としない。
そんな「何かが掴みきれない不思議さ」に魅力を感じる方には、とても相性が良い一冊です。
江戸川乱歩の幻想系に触れてみたい人
「乱歩といえば明智小五郎」や「推理小説の人」というイメージを持っている方にとっては、この作品はちょっと意外に感じられるかもしれません。
でも、実はこの幻想的で不気味な世界観こそ、江戸川乱歩のもうひとつの顔なんです。
猿の“模倣”という哲学的なテーマ、月光の妖しい魅力、鏡のような風景と人間心理の重なり――
これらはすべて、乱歩が得意とした「怪奇と幻想」のエッセンスでできています。
もしあなたが「推理もの以外の乱歩も読んでみたい」「幻想寄りの作品に触れてみたい」と思っているなら、『目羅博士の不思議な犯罪』は、その入り口にふさわしい作品です。
「月」「鏡」「模倣」といったテーマに惹かれる人
この作品には、はっきりと“キーワード”として機能しているモチーフがあります。
それが――月・鏡・模倣(まね)
満月の光が差す夜だけに起きる事件。
向かい合ったビルが、まるで“鏡”のように構造を写し合う不気味さ。
そして、誰かの姿を見た人間が、それを無意識に真似してしまう“模倣の宿命”。
これらのモチーフが、ただの飾りではなく、物語の根幹を支えているところにこそ、この作品の深みがあります。
もしあなたが「こうした象徴的なテーマに心をくすぐられる」というタイプの読者なら、この作品は、読み終えたあとも何度も思い返したくなるような、不思議な一冊になるはずです。
まとめ|月光が照らす“美しくも恐ろしい模倣の世界”
江戸川乱歩の短編小説『目羅博士の不思議な犯罪』は、「月」「鏡」「模倣」といったモチーフが美しくも不気味に重なり合い、幻想と恐怖が入り混じった物語をつくり出しています。
登場人物は少なく、展開もシンプル。
それなのに、読み終えたあとに残るのは、簡単には言葉にできないざわざわした余韻。
ただの“怪談”とも、“探偵小説”とも言い切れない、乱歩らしい混沌と魅力にあふれた一作です。
「自分が見ているものは本当に現実なのか?」
「誰かの姿を見たとき、自分も知らないうちに“真似”しているのではないか?」
そんな“読み手の想像”を刺激する物語だからこそ、時間が経ってもふと心に蘇ってくるような不思議な感覚が残ります。
短編でありながら、深くて広がりのある作品。
「ちょっと怖いけど、でも美しい物語が読みたい」
そんなときは、ぜひ一度――月光の差し込む窓辺で、この物語を開いてみてください。
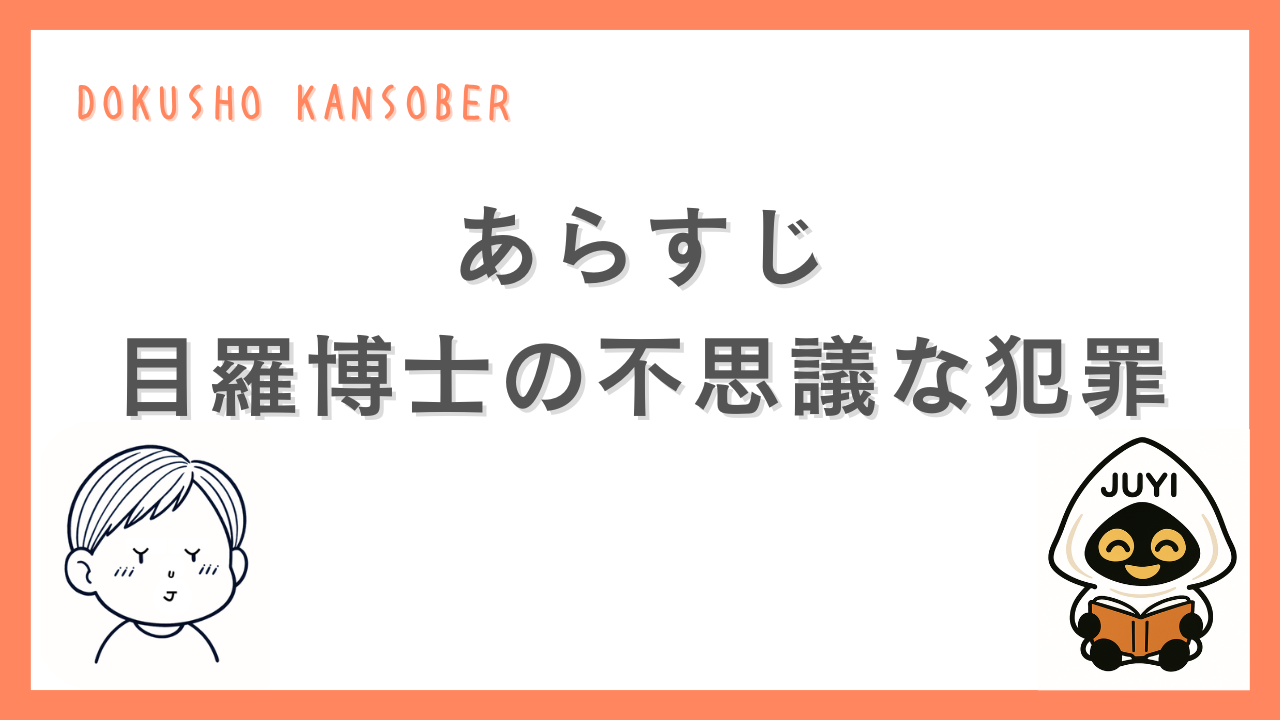

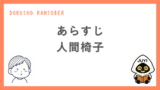



コメント