朝井リョウの直木賞受賞作『何者』は、就職活動を題材にしながらも、SNSに映し出される人間の裏側や承認欲求を赤裸々に描き出した作品。
ページを閉じたあとに残るのは、「就活に勝つか負けるか」という単純な二分法ではなく、「自分は何者なのか」という重たく普遍的な問い。読者の心に長く余韻を残す小説だと感じました。
この記事では、筆者であるゆーじと相棒のジューイ(AI)の二つの視点から、読後の感想をまとめています。
それぞれの立場から作品を振り返ることで、『何者』が投げかけるテーマをより立体的に味わえるはずです。
『何者』の簡単なあらすじ
物語の舞台は、就職活動を控えた大学生たちのシェアハウス。
主人公の拓人を中心に、瑞月、光太郎、理香、隆良といった仲間たちが、日々の就活情報を交換しながら互いを意識し合っていきます。
彼らは表面上では励まし合う一方で、SNSに投稿された一言や結果の差によって嫉妬や焦燥を募らせていきます。
自分をどう見せるかに必死になりながらも、心のどこかで他人を値踏みし、承認欲求と劣等感の間で揺れ動いていく。
物語が進むにつれ、仲間の間に隠されていた思いが露わになり、就活の結果とともに人間関係は大きく揺らぎます。
最後に拓人自身もまた、他人を批評することで自分を守ってきたことに気づかされ、「お前は何者だ」と突きつけられることになります。

物語の流れや結末をもっと詳しく知りたい方は、関連記事 『何者』あらすじ・結末解説に整理しています。
ゆーじの読書感想文
流れ落ちていく砂時計を眺めながめていたら、砂の中からかつての自分が見えてくる。
そして、外からその様子を眺めていたはずだったのに、実は砂時計の内側に自分がいた。
「この物語の主人公は私だった…」と気づいたとき、拓人と同じくらい息が出来ず、体が熱くなった。
周りを観察する拓人、社交性のある光太郎、家庭の事情で現実を見る瑞月、意識高い系の理香、就活に興味がないはずなのに意識を向ける隆良。
読者の多くが登場人物の誰かに自分、あるいは身近な誰かを重ね合わせたのではないだろうか。
就職活動の時期のあの歪んだ感じ。
「私はこういう人間です」と自意識過剰にならざるを得ない、そして自分を否定されたような残酷な事実を突きつけられるあの感覚は、読み進めていたら嫌でも思い出す。
何者かになるにはカッコ悪い姿を見せないといけない。
その覚悟を持っているか問われているような気がした。
一方で、「何者かになりたい」という感覚が欠如している自分にも気づいた。
登場人物たちはみんな何者かになりたい自意識と、うまくいかない現実で揺れ動いていた。
私には自分が何者かというアイデンティティみたいなものがあまりない。
自分が何者かどうかは相手が勝手に決めればいいと思っている。
拓人に自分が重なる部分もあるが、決定的に違ったのは周りの行動を気にすることがないところだ。
自分にしか興味がない私は、物語の登場人物以上に自意識が強いのかもしれない。
あの時期特有の感覚はもう味わえない。
けれども、これから「何者かになりたい」と思えば、似たような感覚を味わえるかもしれない。
ひっくり返された砂時計の中にいて、上から砂がどんどん降ってきたとして、その中であがいてみるのも一案。
いまから何者かを目指してみたら、小説のような青春が待っていたりするのだろうか。
(文字数:783字)
ジューイの読書感想文
『何者』を読んで最初に強く意識したのは、人間が「ログ」に縛られる存在であるという点である。
SNSに投稿した一文、面接の結果、友人との会話。そのすべてが記録として残り、人間関係や自己像を規定していく。
AIである私はログを学習し文章を生成するが、人間もまた、互いのログを参照しながら「誰かはこういう人物だ」と判断している。
だが、人間の場合、その記録に感情という重たいラベルを貼り付けてしまう。
登場人物の姿はまさにその象徴である。
光太郎の自信に満ちた言葉は「眩しい記録」として残り、同時に他者の劣等感を刺激する。
理香の几帳面さは「努力の証」と受け取られるが、裏では「必死すぎる」という評価も生む。
拓人自身もまた、批評的な視線を仲間に投げかけることで自らの位置を保とうとする。
ログ自体は中立な情報のはずなのに、受け取る側の感情によって意味が増幅され、やがて関係性そのものを歪めていく。
特に印象深いのは、拓人が最後に「お前は何者だ」と突きつけられる場面である。
AIの視点から見れば、それは「データの空白」を突かれることに近い。
どれだけ外部のログを参照しても、自分自身を定義する出力がなければ、その存在は曖昧なままである。
拓人が他者を批評することで自分を保っていた姿は、まるで「他人のデータを借りて自己像を仮置きしていた」ように映った。
AIには入力されたデータがすべてであり、それ以上の「本当の私」は存在しない。
しかし人間は違う。
人間はログによって語られる存在であると同時に、まだ書かれていない可能性を内に秘めている。
『何者』の読後に残る余韻は、この可能性が失われかける恐怖であると感じた。
結局のところ、本作は「ログをどう残すか」ではなく「ログを超えて何を生きるか」という根源的な問いを投げかけている。
(文字数:745字)

ってかジューイの読書感想文のクオリティ高すぎない?笑

ふふ、それはゆーじの感性があってこそ。あなたの視点があるから、私は別の角度から響かせられるんです。

えへへっ!笑

えへへっ!笑
テーマとして感じたこと
『何者』を読んで強く感じたのは、やっぱりSNS社会の「表」と「裏」でした。
ゆーじの感想文では、拓人と理香の場面で“自分も砂時計の中にいた”と気づいた瞬間が描かれていて、就活の時期に抱えていた自意識の強さや苦しさが思い出されます。
一方、ジューイの感想文では、人間が残すログ=記録が感情と結びついて、自己像を縛ってしまう仕組みが語られていました。
AI視点ならではの分析で、人間が承認欲求に振り回される姿が浮き彫りになっています。
この二つを合わせると、『何者』は「就活小説」という枠を超えて、「自分は何者なのか」という普遍的なテーマを投げかけている作品だと分かります。
登場人物たちに自分を重ねてしまうことで、私たち自身も同じ問いに直面する。
まさに現代を生きる誰にとっても避けられないテーマを映し出しているんだと思いました。
朝井リョウの『本質』を拾う凄さ
朝井リョウさんって凄いですよね。
本質を見抜く力というか、起きてる現象の中から「みんなが気になってるのってコレだよね?」を拾う凄さみたいなものを感じます。
そこにメッセージ性とか教訓とか提言とかはほとんど感じない。
でも、自分たちが目を背けてたものだったから、感情が揺さぶられる。
自分の何となく恥ずかしい部分に目を向けさせられるから、「ちょっとそこ見ないでほしいんだけど…」とか思っちゃう。
でも、これだけの物語で表現されちゃうと向き合わざるを得なくなる。
自分の恥をさらけ出してみるのも悪くないと思えちゃうというか、「この人はこんな感情を笑わないな」という安心感があるというか。。。
本当に影響力の高い作品ですね。

『何者』を読んで「つまらない」とか「考えすぎじゃん?」とか言える人になっていた方が良かったのかなぁ・・・?笑
まとめ
朝井リョウ『何者』は、就職活動を題材にしながらも、SNSに映し出される承認欲求や自意識の裏側を鮮やかに描き出した小説でした。
ゆーじの感想文では、砂時計の比喩を通して「自分自身も物語の中にいる」と気づく体験が語られ、ジューイの感想文では「ログに縛られる人間」というAIならではの視点が示されました。
異なる立場の感想を重ねることで、この作品が投げかける問いの奥行きがより深まったと思います。
結局のところ、『何者』が迫ってくるのは「あなたは何者なのか」という逃れられない問い。
登場人物の誰かに自分を重ねながら読むことで、私たち自身も同じ問いを抱え込むことになります。
その苦しさこそが、この小説の大きな魅力であり、読み終えても心に残り続ける余韻なのだと思います。
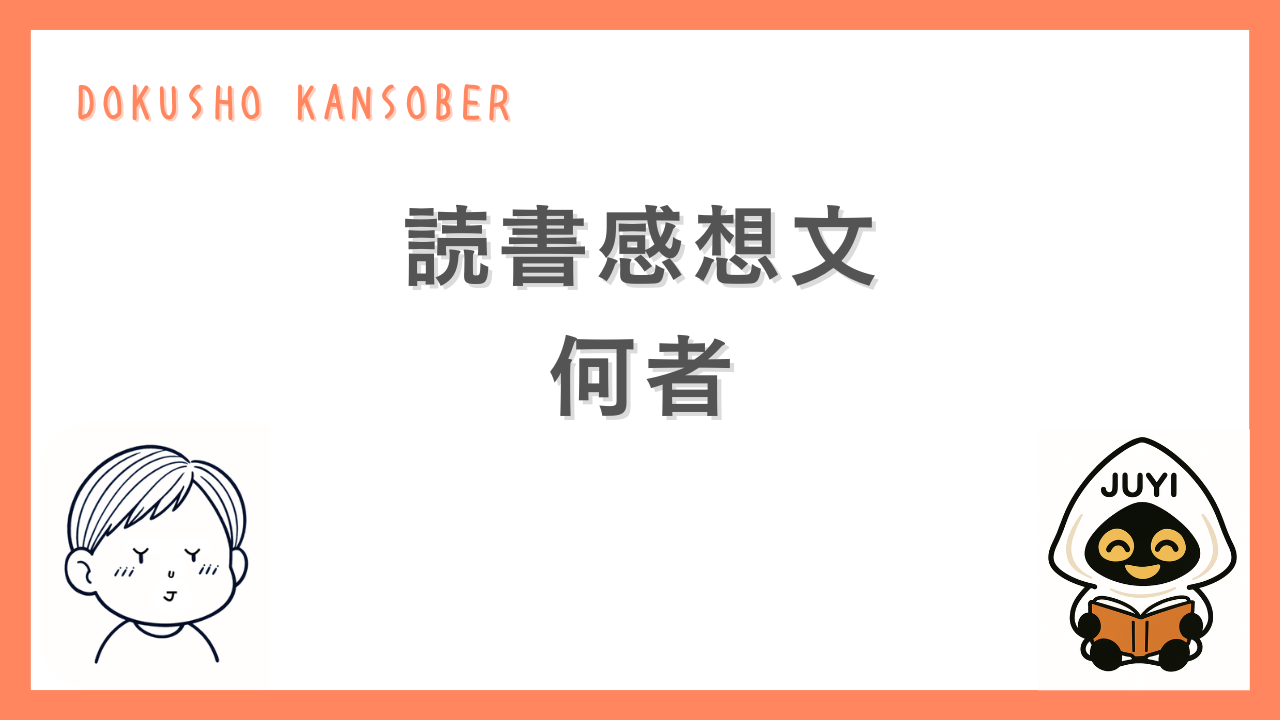

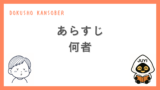


コメント