太宰治の『人間失格』を題材に、AI(ジューイ)と人間(ゆーじ)がそれぞれ読書感想文を書いてみました。
AIが書いた読書感想文では「共感型」「問いかけ型」「客観分析型」「学生向け」など、さまざまな視点から読むことで、一冊の本が持つ多面性や、読み手の姿勢によって変わる感想の深さが見えてきます。

読書感想文の参考例として読んでみてください。
また、人間の私が実際に書いた読書感想文も掲載。

“自分だったらどう読むか”を考えるヒントになれば幸いです。
『人間失格』のあらすじをざっくりおさらい
先に『人間失格』のあらすじを簡単におさらいしておきましょう。
太宰治の代表作『人間失格』は、主人公・大庭葉蔵が自らの人生を「手記」という形で振り返る構成で描かれています。幼い頃から他人に心を開けず、「道化」としてふるまい続けた葉蔵は、やがて酒や女、薬物に溺れて破滅の道をたどります。最終的には「人間、失格」と自らを断じ、廃人のように生きる結末を迎える――そんな痛ましくも心に残る物語です。
作品の構成や登場人物、テーマについてより詳しく知りたい方は、下記の記事で丁寧にまとめています。

感想文を書く前に読んでおくと理解が深まりますよ。
AIが書いた『人間失格』の読書感想文の4例を紹介
「感想文を書きたいけれど、どこから手をつければいいかわからない…」という方に向けて、AIが実際に書いた『人間失格』の読書感想文をご紹介します。
今回は4つの異なる切り口──共感型・問いかけ型・客観分析型・学生向け──で感想文を作成しました。

テーマ設定の参考や構成のヒントとして、ぜひ活用してください。
共感型|“演じる自分”に悩んだ経験から読む『人間失格』
私は太宰治の『人間失格』を読み、「本当の自分を隠して生きる苦しさ」について深く考えさせられた。
主人公・大庭葉蔵は、幼いころから人と関わることに恐怖を感じ、自分を守るために「道化」を演じ続けていた。明るく、ふざけて、周囲を笑わせる。それが彼なりの“生きるための処世術”だった。しかし、その仮面の下にあったのは、孤独や不安、誰にも理解されない悲しみだった。
私はこの葉蔵の姿に、思いのほか強く共感している自分に気づいた。私自身、学校や家族の中で「空気を読む」ことを無意識に続けてきた。周囲の雰囲気を壊さないように、怒らせないように、できるだけ「いい子」にふるまう。でも、ふとしたときに「本当の自分を誰も知らない」と思ってしまうことがある。
葉蔵は、そうした自分の“演技”に気づきながらも、やめることができなかった。誰かに本音を話すこともできず、かといって仮面をかぶり続けることも限界だった。その葛藤が痛いほど伝わってきて、読んでいて胸が苦しくなった。
特に印象に残ったのは、「幸福をさえおそれる」という葉蔵の言葉だ。誰かと心を通わせ、幸せになれるかもしれないという瞬間があっても、葉蔵はそれに飛び込めなかった。私も、少しでも本音を出すと関係が壊れてしまう気がして、つい引いてしまうことがある。その気持ちが、葉蔵の言葉に重なった。
ただ、私は葉蔵と違って、まだ自分の弱さを少しずつ認めたり、人に助けを求めたりすることができると思っている。『人間失格』は、ただの暗くて重い物語ではなく、「自分はこうはなりたくない」と思わせてくれる、ある意味で“自分を守るための警告”のようにも感じた。
本当の自分を隠して生きることの苦しさ。それを乗り越えるには、ほんの少し勇気を出して、人に心を見せることなのかもしれない。葉蔵のように崩れてしまう前に、自分の弱さと向き合いながら、自分のままでいられる場所を見つけていきたいと思う。
(文字数:798字)
📘補足解説:「共感型」の視点で読む『人間失格』
この感想文は「共感型」の典型例として、自分自身の経験や感情と作品世界を重ねながら読んでいる点が特徴。
主人公・葉蔵の「道化」という生き方に共鳴しながらも、「自分はまだ立ち直れる可能性がある」と距離をとることで、単なる感情移入ではなく、自己の成長にもつなげています。
特に注目すべきは、《幸福をさえおそれる》という印象的な言葉を切り口に、「仮面をかぶることの苦しさ」「本音を出すことの怖さ」など、現代人にも通じる“生きづらさ”を誠実に描いている点です。
このように「共感+自己省察」の構成は、読者にとっても共通点を見つけやすく、読後に考えを深めるきっかけとなる、非常に良質な読書感想文のスタイルといえます。

「共感型」の感想文として、読者の感情に寄り添いながら自己理解を深める一例です。
問いかけ型|「人間らしさとは何か」というテーマで読む『人間失格』
太宰治の『人間失格』を読んで、私はひとつの問いに立ち止まった。
それは、「人間らしさとは何か」という問いだ。
葉蔵という人物の人生は、社会に適応できず、自分の感情や存在そのものに怯え続けた日々だった。「人間、失格」とはっきり言い切る彼の姿に、私は戸惑いながらも、心がざわつくのを感じた。
作中で葉蔵は、周囲と上手く関われず、子どもの頃から「道化」として振る舞い続ける。人を笑わせることで、自分を守ろうとした。やがて酒や薬、女に溺れ、破滅していくのだが、それらすべては彼が「人間らしく」あろうとした努力の裏返しのようにも思えた。
私はこれまで、「人間らしさ」とは、誰かと信頼関係を築き、社会の中で自分の役割を果たすことだと漠然と考えていた。でも、葉蔵のように不器用で傷つきやすく、誰かと本当にわかり合うことができずに苦しむ人もいる。そんな彼の姿を「人間失格」として切り捨てていいのだろうか。むしろ、その迷いも痛みも、まさに“人間らしい”のではないかと思えてきた。
物語の最後、語り手である「私」が葉蔵のことを「神様みたいないい子だった」と語る場面がある。葉蔵自身は自分を失格だと思い込んでいたが、他者の目には違って映っていた。このギャップが、人間という存在の曖昧さや複雑さを物語っていると感じた。
誰かと分かり合いたい。でもそれができずに絶望する。そんな矛盾や苦しみこそ、人間らしさの一部なのではないか。葉蔵のように、すべてがうまくいかなくても、それでも生きようとしたその姿に、人間の弱さと同時に尊さを見出したいと思った。
この小説を読み終えた今も、「人間らしさとは何か」という問いに明確な答えは出せていない。けれど、だからこそ考え続ける価値がある気がしている。人は誰かを簡単に「失格」にはできないし、自分自身にも同じことが言える。そんなメッセージを私はこの作品から受け取った。
(文字数:781字)
📘補足解説:「問いかけ型」の視点で読む『人間失格』
この感想文は、「問いかけ型」の構成に基づき、作品から生まれた普遍的な疑問を軸に思考を深めている点が特徴。
中心となる問い「人間らしさとは何か」を読後まで引きずる形で展開し、読者にもその問いを投げかけています。読書感想文としては、「自分の答えを出すこと」よりも「問い続ける姿勢」を大切にしている点が印象的です。
また、葉蔵の姿に一方的な評価を下すのではなく、「自分ならどう見るか」「人は誰かを失格にできるのか」と、価値観の多様性にも触れており、読者にとって考える余白が残されている構成となっています。

「問いかけ型」の感想文として、思考の深さと柔軟さが感じられる例です。
客観分析型|太宰治の意図を読み解くテーマ
『人間失格』を読んで、私が最も考えさせられたのは、「なぜ太宰治は、葉蔵に“人間失格”と名乗らせたのか」という問いだった。
このタイトルは読者に強い印象を与える一方で、その意味は非常に重く、自らを否定する言葉でもある。作者・太宰治はなぜ、こんなにも極端な言葉を主人公に与えたのだろう。
作中、葉蔵は「人間らしく生きられない」という苦しみを何度も吐露する。周囲の人にうまくなじめず、自分を守るために「道化」として振る舞い続け、やがて女性関係や薬物、心中未遂など、破滅的な道へと堕ちていく。表面的には“堕落した人間”のように見えるが、彼の内面には、他者との距離感や社会との摩擦に対する繊細すぎる感受性があった。単なる怠惰や逃避とは異なる、深い葛藤がある。
私は、葉蔵が「人間失格」と言ったのは、社会的な基準から見た“普通の人間”になれなかったことへの絶望と、自分自身を裁いてしまうほどの自己否定から来る言葉だと感じた。そして、太宰治はあえてこの極端な表現を使うことで、「人間らしさとは何か」という問いを読者に突きつけているのではないだろうか。
作品の最後には、第三者である「私」が登場し、葉蔵のことを「神様みたいないい子だった」と語る。この視点が加わることで、葉蔵の「人間失格」という自己評価が、決して絶対的なものではないことが示される。つまり、太宰は「自分をどう見るか」と「他人がどう見るか」のズレを描きたかったのではないか。人間の評価は常に主観的であり、一面的ではないということだ。
また、『人間失格』は太宰の晩年に書かれた作品であり、彼の遺書のようにも読まれている。自身の生きづらさを葉蔵に託し、「人間失格」と名乗らせることで、自らの人生を文学として昇華しようとしたのかもしれない。
この作品を通して、私は「人間とは何か」「失格とは誰が決めるのか」という根本的な問いと向き合うことができた。
(文字数:789字)
📘補足解説:「客観分析型」の視点で読む『人間失格』
この感想文では、「作者の意図」に焦点を当てる「客観分析型」のアプローチが採られています。
太宰治の言葉選びや物語構成の意味を丁寧に読み解こうとする姿勢が特徴。
とくに、「タイトルに込められた意味」「語り手の存在」「太宰自身の人生背景」など、多角的な視点から作品を分析して、読者にとっても「自分ならどう読むか」を考える手がかりになります。

思考の深さと解釈のバランスが取れた一例として、読書感想文に“論理”を取り入れたい方には参考になる内容です。
学生向け|“生きづらさ”に共感した読書体験
太宰治の『人間失格』は、決して読みやすい作品ではなかった。けれど、読み終えたあと、私はこの物語の中に“自分の一部”を見た気がした。特に、主人公・大庭葉蔵が感じていた「生きづらさ」は、今の時代を生きる私たちにも通じる感情だと思う。
葉蔵は幼いころから、他人とどう接してよいか分からず、「道化」としてふざけたり人を笑わせたりすることで、なんとか人間関係をつないでいた。けれど、それは本当の自分ではなく、仮面のような存在だった。SNSの中で「明るくて元気な自分」を演じてしまう現代の私たちにとって、この“演じること”の苦しさは他人事ではないと思った。
学校や友人関係でも、「みんなに好かれたい」「変なやつと思われたくない」と思い、本音を隠してしまうことがある。私自身も誰かに気を遣いすぎて、あとでひとりになって疲れてしまうことがある。葉蔵のように極端な行動はとらなくても、他人と本当につながれているのか分からない不安を抱える点で、彼の“生きづらさ”は他人事ではなかった。
特に印象に残ったのは、「弱虫は、幸福をさえおそれるものです。」という言葉だ。人に優しくされたとき、「これは本当なのか」と疑ってしまう。傷つくのが怖くて、幸せに手を伸ばせない。そんな気持ちは、思春期の今だからこそ、共感できたのかもしれない。
『人間失格』のラストでは、葉蔵は自分を「人間、失格」と断じるが、それに対して語り手は「神様みたいないい子だった」と語る。この対比がとても印象的だった。人間は、自分を正しく見ることができない。他人の目を通して初めて気づく優しさや強さもあるのだと思った。
この本は、明るく元気な物語ではない。けれど、生きることに迷ったり、疲れたりする人すべてに、「あなたは失格ではない」とそっと伝えてくれているように思えた。私も葉蔵のように本当の自分に目を向け、少しずつでも自分らしく生きていけるようになりたい。
(文字数:794字)
📘補足解説:「学生向け」の視点で読む『人間失格』
この感想文では、現代の学生が直面する「生きづらさ」や「本音が出せない環境」といったリアルな悩みを、『人間失格』と重ねて表現しています。
とくにSNSとの対比を交えた部分は、読者の共感を呼びやすく、作品のテーマを“いま”に引き寄せて読む工夫をしました。
また、「傷つくのが怖くて幸福を恐れる気持ち」や「他者評価と自己評価のずれ」など、思春期特有の繊細な心情も描写して、読む側の気持ちに寄り添うやさしい文体に。

全体として「読むことで自分を見つめ直す」という読書体験の本質を表現して、学校の課題文にも適したバランスの取れた内容を意識しました。
人間(ゆーじ)が書いた『人間失格』の読書感想文

私も読書感想文を書いてみました。
どの場面に遡ってもこの物語の結末を避けることが出来ない感覚。傍から見れば止めることが出来るのに、いざ主人公の立場になってみると、どこにも抜け道のないタイムリープを繰り返してしまう。
そんな息苦しさを『人間失格』から感じた。
その息苦しさの正体はいったいなぜなのか?その答えを探したいと思う。
印象的な言葉がある。それは【あとがき】の最後の一文「…神様みたいないい子でした」というマダムのセリフ。
葉蔵は自分に「人間失格」というレッテルを貼ったが、周りはそんな風に思っていない。私も葉蔵のことを「人間失格」だとは思えなかった。
確かに、精神病院に収容され、廃人のようになったことから、結果だけを切り取るなら「人間失格」なのかもしれない。
けれども、ここに至るまでの葉蔵は「人間失格」と呼べるような人物だったのか。
恐怖を隠すために道化を演じたり、人を信じようとして裏切られる不安を感じたり、それらは誰しもが抱える心の一部ではないだろうか。
もし、葉蔵に対して「人間失格」というレッテルを他者が下すなら、私もそうだし、多くの人間がそうであろう。
私にはどこか葉蔵と重なる部分があると感じた。そして、その葉蔵は自分のことを「人間失格」だとした。葉蔵が下した結論は、私も「人間失格なのでは?」と思わせる側面がある。そんなところから息苦しさを感じたのかもしれない。
だからこそ、余計にマダムの言葉が印象的だった。自分を神様みたいないい子とは思わないが、自分にも人間としての価値があるとは思っている。葉蔵に対するあの言葉は私を救う言葉でもある。
人間の価値を決めるのは人間。そして、それは自分だけでなく自分以外の人でもある。
もし自分で自分のことを卑下するような時が来たら、その時は自分以外の人に助けてもらいたいと思った。自分だけでなく他者の視点も視野に入れる。タイムリープから抜け出すには自分ではなく他者の力が必要なのかもしれない。
(文字数:799字)
📘補足解説:自己評価と他者評価のズレに注目
『人間の価値』についてを1つのテーマと受け止めて、その中から自己評価と他者評価の乖離が印象的だったので、この点に注目しながら読書感想文を書いてみました。
自己や他者の評価云々は置いといて、「自分だけじゃなくて他者の視点も考えることは必要なんだな」とは強く感じたので、自分が良くないゾーンに入ったときは周りに助けてもらうことが大事と感じて、こんな結末にした次第です。
ちなみに、私は自分が思う自分と周りが思う自分が違っていてもあまり気にならないのですが、そんな自分でも評価のズレを気にしてしまうくらい没入感のある作品で、改めて『人間失格』という物語性、太宰が書くの文章の強さみたいなものを感じましたね。
物語に入りすぎちゃうけれど、【あとがき】で客観視させることで、前かがみになっていた姿勢をグッと引き戻す構成力の高さなどもすごいし、いろんな側面から名作だと感じざるとえません。

太宰治の作品は意外と読んでないので、今後は有名どころからいろいろ読んでいきたいですね。
まとめ:「人間失格」の面白さは自分以外の人間関係にある
「人間失格」を読んでいて、なぜか『桐島、部活やめるってよ』を想起しました。
主人公がどうこうと言うよりも、主人公の周りの存在の影響力が大きいみたいなところが私の脳内をカスったのかもしれません。
「人間失格」の面白さ、興味深さは自分以外の人との『比較』とかにあるのかなと。
一歩引いてみると「よくそこまで自分に陶酔できるね」と思うくらい冷たい感情になるんだけど、でも、読んでいてなぜか葉蔵を蔑ろにはできない。なんか気になってしまう、気にかけてしまう。
主人公を通じて自分の存在を知る、無意識に自分を測ってしまう。
この没入感が味わえるのは「人間失格」の大きな魅力ですね。
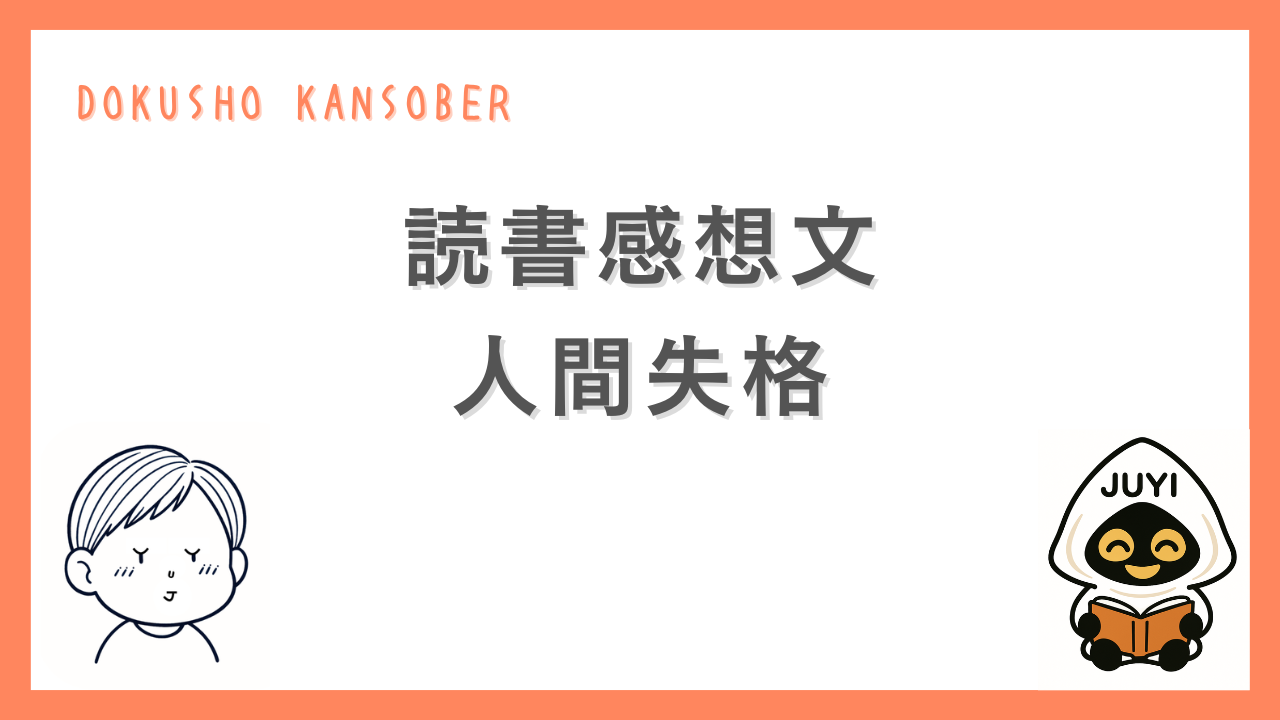




コメント