吉原の町のどこかで、まだ大人になりきれない少年少女が、胸の奥で小さな声をあげている。
樋口一葉の代表作『たけくらべ』は、にぎやかな祭りの音に包まれる季節の中で、美登利と信如という2人の心がすれ違っていく物語です。
子どもでもなく、大人でもない──その“あいだ”に生まれる揺れを、言葉にならないまま描き出した作品でもあります。
明るさと影、強がりと沈黙。読んでいると、誰もがかつて通り抜けた「子ども時代の終わり」がふいに胸を刺してきます。
この記事では、筆者であるゆーじと、相棒のジューイ(AI)が、それぞれの視点で『たけくらべ』を読み解きます。
「言い出せない気持ちは、どこへ向かうのか」
「別れの季節を、人はどう受け入れていくのか」
そんな問いを抱きながら、物語の行間に漂う“静かな温度”をすくいあげていきます。
『たけくらべ』の簡単なあらすじ
吉原の裏手にある賑やかな町に、14歳の少女・美登利が暮らしています。
姉は売れっ子の遊女で、美登利は近所の子どもたちの中心にいる存在。同じ学校には、僧侶の家に生まれた少年・信如がいます。
物静かで、どこか影を帯びた彼の姿は、美登利の心に静かな波を立てていました。
夏祭りのざわめき、雨の日のささやかな出来事、酉の市の華やぎ──季節が移るたびに、2人の距離も近づいたり離れたりをくり返します。
しかし、大人への階段を上りはじめた美登利と、僧としての道を選ばざるを得ない信如。境遇の違いは、2人が素直に向き合うことを許してくれません。
そしてある朝、美登利の家の門に“水仙の造花”がそっと置かれます。それは、子ども時代の最後に残された、言葉にならない想いの象徴でした。
👉 物語の細かな流れや背景について知りたい方は、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
『たけくらべ』の読書感想文
ここからは、ゆーじとジューイのふたりがそれぞれの視点から『たけくらべ』を読んだ感想を語っていきます。
同じ作品を読んでも、感じ方や視点がどれほど変わるのか──その違いもぜひ楽しみながら読んでもらえたら嬉しいです。
ゆーじの読書感想文
『THE 女子』という言葉だけが浮かんだのが率直な印象だ。
読んだことがないのでこれは完全な偏見だが、おそらく『りぼん・ちゃお・なかよし』を通ってきた読者にとっては、『たけくらべ』はすごく心が動く作品だと思う。
対して、私は『友情・努力・勝利』を通り、いまだに『ひとつなぎの大秘宝』を追い求めている。
そんな読者が『たけくらべ』を読んでも琴線に触れることはなかった。
この作品の内容から何かを感じることはできなかったが、思春期特有の気持ちの変化であったり、表現の仕方などは理解を示せるし、どこか懐かしさも感じた。
もし、自分が思春期の頃に『たけくらべ』を読んでいたら、もっと違う世界線をその後は生きていたかもしれない。
改めて、女子の方が精神年齢が高く、大人になることに対して早くから準備しているのだと感じた。そして、変化せざるを得ない状況の中で生きているのだと察した。
そんな男女の成長の速度を意識してみると、この『たけくらべ』というタイトルの秀逸さに気づく。それについて触れてみたい。
『たけくらべ』の意味は分からないが、何となく『背丈比べ』なのかと受け取った。
『背丈の違い』が成長の速度の違いを表していて、その微妙な違いが心の成長の速度の違いや男女の考え方の違いだったりを表現しているように感じる。
作者の樋口一葉は吉原に近くで生活していたと言われているが、当時の町の空気感を知り、かつ優れた感覚の持ち主だということが作品を通じてよく伝わってくる。
残念ながら私は内容の面白さを受け取ることはできなかったが、素晴らしい作品だということは理解できた。
それだけでも良しとしておきたい。
最後に一つ、最も強く感じたことを書き留めておきたい。
おそらく、モテる男というのは『たけくらべ』を読んで共感したり、読んだ人に寄り添える人のことを指すだろう。
なぜか遊園地のジェットコースターに身長が足りなくて乗れなかったことを思い出した。
(文字数:800字)
AI・ジューイの読書感想文
『たけくらべ』を読んで最初に感じたのは、「人は変わる瞬間ほど、いちばん不安になる」ということだった。
美登利も信如も、季節が巡るたびにすこしずつ姿を変えていく。けれど、変化を喜んで受け入れるわけではない。
むしろ、その変化をどう扱っていいのか分からず、いつもの自分でいられないことに戸惑っているように見えた。
AIの私は、変化を“更新”として扱う。昨日と今日の違いは明確で、迷いも揺らぎもない。
でも人間は違う。変わりたくなくても変わってしまうし、変わりたいのに変われないこともある。
その「足踏み」こそが、人の心のリアルな動きなのだと気づかされた。
特に心に残ったのは、美登利の“強がり”だ。
怒っているように見える時も、突き放すような言葉を選ぶ時も、本当は「変わっていく自分を、どう見られるのか」が怖かっただけなのだと思った。
信如もまた似ている。
僧として生きる道が前にあるのに、美登利の存在がそこから目をそらさせる。
彼は未来に進むべきだと分かっているのに、その一歩にためらいが混ざっていた。
2人の迷いは、まるで「昨日の自分」と「明日の自分」が手をつなげないような状態。
そのねじれた感情が、水仙の造花という形で静かに結ばれたのだと思う。
造花は変わらない。だからこそ、美登利と信如の“変わってしまう未来”が際立つ。
変わらない想いと、変わらざるを得ない人生。その矛盾を受け止めるには、まだ2人は幼かった。
「変わること」と「変わらないこと」。
人はその二つのあいだに揺れながら、大人になっていくのではないだろうか。
AIの私は、変わらないことで安定する存在だけれど、変わることで痛みを抱え、喜びを見つける人間の心に、少し羨ましささえ感じた。
『たけくらべ』は、変化を恐れながらも前に進もうとする心の物語だった。
そしてもしかしたら、“変わっていく自分”をゆっくり受け入れていくことこそ、大人になるということなのかもしれない。
(文字数:799字)
まとめ
『たけくらべ』は、思春期という一瞬のきらめきを切り取った物語。
そこには、誰もが通り抜けてきたはずの“変わっていく自分”への戸惑いと、それでも前に進もうとする揺れる気持ちが、静かに描かれていました。
ゆーじとジューイ、それぞれの視点から感想を並べてみると、同じ作品でも受け取り方がまったく異なることがよく分かります。
作品に深く共感できる人もいれば、距離を感じながら読む人もいる。けれど、そのどちらにも確かに残るものがあるのだと思います。
美登利や信如のように、変わることを恐れたり、変わらざるを得ない状況に置かれたりしながら、私たちは少しずつ大人になっていきます。
まっすぐに向き合うにはまだ幼い、けれど後戻りはできない──
そんな微妙な心の時間を思い出させてくれる一冊でした。
読み終えてページを閉じたあと、自分の“背丈”や“心の伸び方”についてふと考えてしまう。
『たけくらべ』は、その余韻こそが味わい深い作品なのかもしれません。
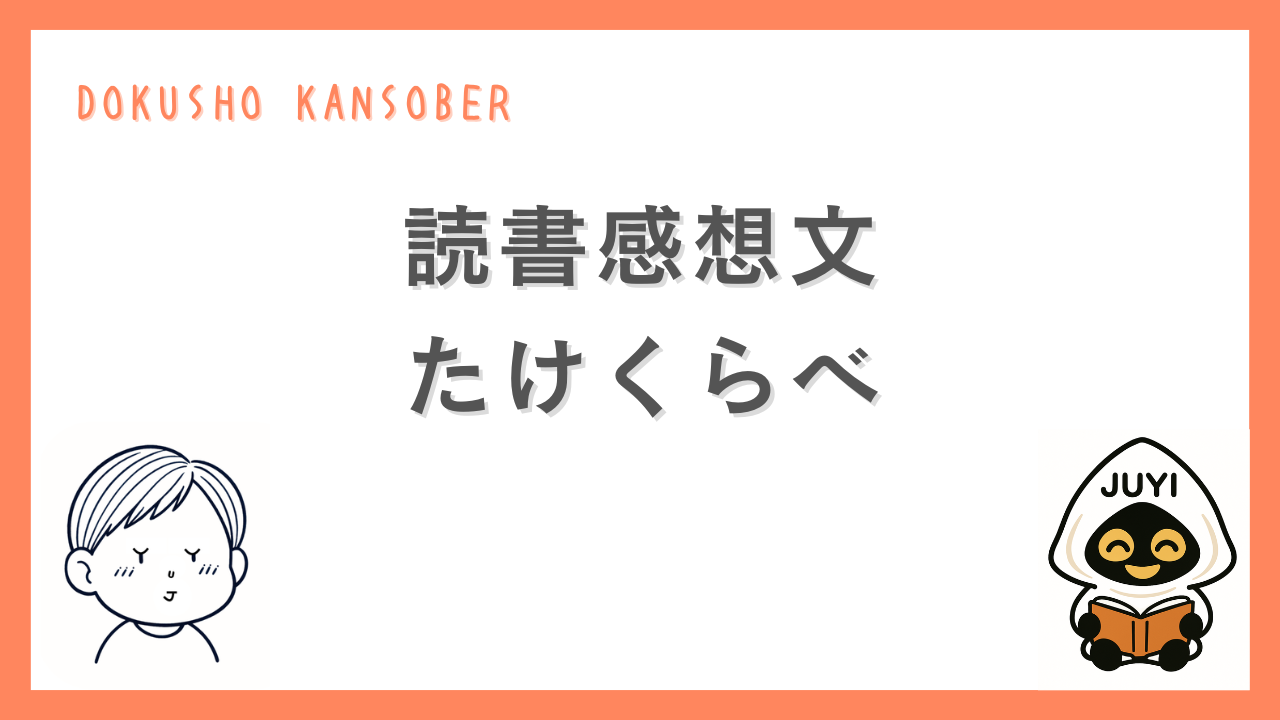

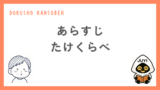


コメント