宮沢賢治の名作『セロ弾きのゴーシュ』は、ちょっと不器用な青年ゴーシュが、音楽とまっすぐ向き合いながら成長していく物語。
楽団の中で一番下手だと言われ、うまくいかない日々に落ち込むゴーシュ。しかしある夜から、三毛猫やかっこう、狸の子、野ねずみの親子といった、不思議な動物たちが次々に彼の家を訪れるようになって…
この記事では、物語のあらすじから魅力、読みどころまでをわかりやすく紹介します。
初めて読む人も、昔読んだことがある人も、ゴーシュの成長する姿にきっと心を動かされるはずです。
セロ弾きのゴーシュの基本情報
『セロ弾きのゴーシュ』をより深く楽しむためには、この物語が生まれた背景や、作者・宮沢賢治がどんな気持ちで音楽と向き合っていたのかを知っておくと、一つひとつの出来事の意味がぐっと鮮明になります。
ここでは、作品が書かれた時代、登場する楽器「セロ」の特徴、そして主人公ゴーシュがどんな立場にあったのかを、わかりやすく整理。
物語の理解が一段深まり、ゴーシュの行動や成長がなぜ感動を呼ぶのか、その理由が自然と見えてくるはずです。
H作品が生まれた背景と宮沢賢治の音楽体験
『セロ弾きのゴーシュ』が発表されたのは1934年。宮沢賢治が亡くなった翌年のことでした。
この物語には、賢治自身の“音楽への強い思い”が深く関わっています。賢治はチェロを本当に練習していたことで知られ、地元・花巻で農民たちと音楽を楽しむ「農民楽団」をつくろうとしたほど熱心でした。
上京した際にはプロの楽士のもとへ通い、短期間で上達しようと必死に取り組んだというエピソードも多く残っています。
しかし賢治は決して器用ではなく、思いどおりに演奏できず悩んだ経験もあったようです。
だからこそ、物語の主人公ゴーシュが“未熟で、うまくいかない青年”として描かれているのは、賢治自身の姿と重なって見える部分も。
作品は童話でありながら、音楽を学ぶときの苦しさ、努力の積み重ね、そして他者との関わりの中で成長していく喜びが、リアルに込められています。

ゴーシュが動物たちから学び、知らないうちに演奏が良くなっていく過程には、賢治自身の実体験と願いが映し出されているのです。
「セロ(チェロ)」という楽器が物語に果たす役割
物語の中心にある「セロ」は、チェロの古い呼び方で、低くやわらかな音を出す大型の弦楽器。
チェロは幅広い音域を持ち、音楽に深みや温かさを加える重要な存在。しかし、同時に扱いは難しく、初心者が思うように弾くには多くの練習と繊細な感覚が求められます。
ゴーシュが「金星音楽団」でセロを担当しているのは、決して偶然ではありません。
チェロという楽器は、努力しないと美しい音が出ないため、物語全体を通して“成長”や“鍛錬”というテーマを象徴する役割も果たしています。
また、チェロの深い音は、ゴーシュの気分や心の動きを表すように描かれています。うまくいかないときは荒々しく、動物たちとの交流が増えるにつれ、柔らかい音や豊かな響きが増えていくのです。
さらに、動物たちがゴーシュの演奏に反応し、自分なりのリクエストをする場面にも注目。
三毛猫は「トロメライ」を、かっこうは音階の練習を、野ねずみは“治療”を求めます。
チェロという楽器の音色が、彼らとの交流をつなぎ、人と動物の間に不思議な橋をかけているとも言えるでしょう。
未熟な青年ゴーシュが置かれた環境とは
ゴーシュは町の活動写真館(今でいう映画館)の楽団「金星音楽団」に所属しています。
そこで彼はセロを担当しますが、楽団の中では「一番下手」と言われ、楽長から厳しく叱られていました。
仲間の演奏についていけず、音程がずれたり、表現が固かったりと、思うように上達できない毎日を過ごしていたのです。
しかしここで重要なのは、ゴーシュが“下手なのに努力を続ける青年”だという点。
叱られても投げ出さず、毎晩遅くまで自宅で練習を続ける姿は、彼の真面目さと不器用さをよく表しています。
うまくいかないときにふてくされるのではなく、悔しさを抱えながらも立ち向かおうとする強さがゴーシュにはあります。
ただし、彼はまだ若く、心に余裕がありません。動物たちが突然家に現れたときに怒ってしまったり、戸惑ったりするのは、プロとしてプレッシャーを抱えながら過ごしていた証とも言えます。
この「未熟さ」と「努力する姿勢」が物語の核となり、動物たちとの出会いがゴーシュにとってどれほど意味のあるものだったのかを、より一層引き立てています。
セロ弾きのゴーシュのあらすじをわかりやすく解説
『セロ弾きのゴーシュ』は、動物たちとの出会いを通して青年が成長していく、心温まるお話。ゴーシュの家には毎晩ちがう動物がやってきて、それぞれに不思議なお願いをしていきます。
最初は戸惑い、怒りながら相手を追い返そうとするゴーシュでしたが、やがてその交流が彼の音楽に大きな変化を与えていきます。
ここでは、彼がどんな夜を過ごし、何を学び、どのように成長していったのかを、物語の順番にそってわかりやすく紹介していきます。
楽団で“いちばん下手”と呼ばれたゴーシュ
物語の始まりで、ゴーシュは「金星音楽団」という町の楽団に所属しており、もうすぐ行われる大きな音楽会に向けて練習を続けていました。
しかし、彼は仲間の中で“いちばん下手”と言われ、楽長から厳しく叱られる日々を送っています。
指揮者の注意についていけず、音がずれたり、表現が荒くなったりするたびに、楽長は眉をひそめてゴーシュを名指しで指摘します。
ゴーシュは叱られることに悔しい気持ちを抱えながらも、反発するわけではなく、家に帰ると黙々と練習を続ける不器用な青年。
ですがその一方で、自分の演奏に自信が持てず、プレッシャーに押しつぶされそうになっていました。
三毛猫の訪問|演奏に向き合う最初のきっかけ
ゴーシュが自宅でセロを練習していると、最初に家へやってきたのが三毛猫でした。
三毛猫は勝手に家へ上がり込み、「ロマチック・シューマン作曲のトロメライをひいてください」と偉そうに頼みます。しかも「あなたの演奏を聞かないと眠れない」と言い、まるでゴーシュを試すような態度です。
突然の訪問に腹を立てたゴーシュは、猫に頼まれた曲を弾く代わりに「印度の虎狩り」という激しい曲を力任せに演奏し、猫を追い出そうとします。
しかし猫は驚きながらも、演奏が終わると「今夜の演奏はどうかしてる」と言い、それがまたゴーシュの怒りに火をつけます。
かっこうとの夜|音階の正確さに目覚める
次の晩、ゴーシュの家を訪れたのは、丁寧な口調のかっこうでした。
かっこうは自分の鳴き声の「ドレミファ(音階)」が正しく鳴っているかを確かめたいと言い、ゴーシュにその音を弾いてほしいと頼みます。
ゴーシュは最初こそうんざりしながらも、かっこうの鳴き声を何度も聞かせてもらううちに、音の高さの違いがはっきり分かるようになっていきます。
音楽にとって音程の正確さはとても大切ですが、ゴーシュはこのとき初めて、それを体で感じ取れるようになりました。しかし、かっこうは何度も何度も「もう一度」と要求し、延々と練習が続きます。
ついに夜が明けてしまうほどで、ゴーシュは疲れ果ててしまいました。
苛立ちが爆発したゴーシュは、かっこうを怒鳴りつけますが、それでもかっこうは逃げ惑いながら自分の鳴き声を守ろうとします。最後には窓にぶつかり、血を吐くほどでした。
決して穏やかなやり取りではありませんが、この夜がゴーシュの音楽にとって大きなターニングポイントとなったことは間違いありません。それは、丁寧な耳の使い方を学んだからです。
狸の子の合奏|素直さが芽生えた瞬間
三日目の夜にやってきたのは、父親に「ゴーシュのセロに合わせて練習してこい」と言われた狸の子でした。狸の子は小太鼓を持っており、一緒に演奏したいと言います。
ゴーシュは最初「狸汁にして食ってやるぞ」と脅して追い返そうとしますが、狸の子のまっすぐな態度に心を動かされ、しぶしぶ練習に付き合います。
練習が始まると、狸の子はゴーシュの演奏に合わせて太鼓を叩くだけでなく、「二番目の糸(弦)が遅れている」と演奏の欠点まで指摘してきます。
ふつうなら怒りそうなところですが、このときのゴーシュは素直にその指摘を受け入れ、チューニングを直しながら演奏を続けました。
この場面こそ、ゴーシュの“心の柔らかさ”が芽生えた瞬間です。自分の演奏のミスを認め、相手の意見に耳を傾ける姿は、前日のかっこうへの態度とはまったく違うものでした。
野ねずみの親子|演奏に宿る“力”を知る
四日目の夜に訪れたのは、弱った子どもを抱えた野ねずみの親子でした。
母ねずみはゴーシュに「演奏の力で子どもの病気を治してほしい」と頼みます。最初は怒って追い返そうとしたゴーシュでしたが、事情を知ると心を動かされ、セロの孔の中に子ねずみをそっと入れて演奏を始めます。
その曲は「何とかラプソディ」という楽曲で、ゴーシュは集中して弾き続けました。すると不思議なことに、演奏が終わるころには子ねずみの体調が良くなり、元気を取り戻していたのです。
驚いたゴーシュは、自分の音楽に“誰かを助ける力”があることを初めて知ります。
さらにゴーシュは、野ねずみ親子にパンを分け与えます。これは、最初の三毛猫のときのように怒りをぶつける姿とは大違いです。
音楽会本番|ゴーシュがつかんだ本当の成長
ついに迎えた音楽会の本番。金星音楽団の演奏は大成功となり、観客は大きな拍手を送ります。
アンコールが起こると、楽長はゴーシュを指名しました。突然の指名にゴーシュは「自分なんてからかっているのだ」と腹を立てますが、仕方なく「印度の虎狩り」を演奏します。
しかし、その演奏はかつてのような荒々しいだけのものではありません。動物たちから学んだ音階、リズム、表現、そして心をこめる姿勢がすべて自然と演奏に表れていました。
観客は息をのむように聴き入り、楽長や仲間の団員もその見事な演奏を称賛します。
自分でも気づかないうちに、ゴーシュは確かな成長を遂げていたのです。家へ帰る途中、ゴーシュは夜空を見上げ、追い出してしまったかっこうへそっと謝ります。その姿は、もう“怒りっぽくて未熟な青年”ではありませんでした。
セロ弾きのゴーシュの魅力と読みどころ
『セロ弾きのゴーシュ』が長く読み継がれている理由は、単なる“音楽の話”にとどまらず、努力や心の成長、人との関わりといった、誰にでも共通するテーマが描かれているから。
ゴーシュは最初こそ不器用で、怒りっぽく、うまくいかないことばかりでした。しかし動物たちとの出会いを重ねる中で、少しずつ考え方が変わり、演奏にも心にも深みが生まれていきます。
このセクションでは、物語の核となる「成長」「対話」「芸術への姿勢」という3つの観点から、作品の魅力をわかりやすく紹介します。
努力が報われる瞬間を描いた“成長の物語”
ゴーシュは、物語のはじめでは「いちばん下手」と叱られ、周りに追いつけず、自分の演奏にも自信が持てない青年です。
しかし、彼には“あきらめない力”があります。楽団の練習で叱られて帰ってきても、投げ出さずに夜遅くまでセロを練習する姿は、不器用ながらもひたむきで、読者の心を動かします。
この物語の魅力は、派手な成功ではなく、“少しずつ積み上がっていく努力の過程”が丁寧に描かれている点。
三毛猫、かっこう、狸の子、野ねずみの親子──毎晩訪れる動物たちと向き合う中で、ゴーシュは技術も心も磨かれていきます。
本人は気づかないまま、確実に上達し、最後の音楽会のアンコールでその成果が一気に花開きます。
努力がすぐ結果に結びつくとは限らない。
むしろ日々の小さな積み重ねが、後になって大きな成果として返ってくる──その普遍的なメッセージが、多くの読者の胸に響くのです。
動物たちとの対話がもたらす内面的な変化
『セロ弾きのゴーシュ』は、動物たちがただ“かわいい存在”として登場する物語ではありません。
それぞれが異なる価値観や視点を持ち、ゴーシュに新しい気づきを与える“先生”のような役割を持っています。
三毛猫はゴーシュの感情の乱れをそのまま映す鏡のような存在であり、かっこうは音階の正確さを求めてくる厳しい指導者。狸の子は素直にアドバイスしてくれる相棒のようで、野ねずみの親子は音楽の「癒しの力」を教えてくれる存在です。
最初は怒ったり戸惑ったりしていたゴーシュですが、交流を重ねるうちに“相手の声を聞く姿勢”が育っていきます。
自分の演奏の欠点を素直に受け入れたり、動物たちのお願いに応えようとしたりする姿は、心の成長そのものです。
この物語の優れている点は、ゴーシュの変化が「教訓めいた形」で描かれていないこと。
あくまで自然なかたちで、夜の静かな時間の中で、ゴーシュの心が少しずつやわらかくなる様子が伝わってきます。読者は彼の変化を見守りながら、自分自身の心のあり方についても考えさせられるのです。
音楽と誠実に向き合う姿勢に込められたメッセージ
ゴーシュは決して天才ではありません。むしろ最初は“下手で怒られてばかりの青年”です。
しかし、だからこそ物語の中で描かれる「音楽と誠実に向き合う姿勢」が強く胸に残ります。
毎晩遅くまで練習し、ときには疲れ果てながらもセロを弾き続ける姿は、努力だけでなく「真剣さ」そのものです。
動物たちとの交流は、ゴーシュに技術だけでなく「音楽の心」を教えてくれます。
かっこうのように音階の正確さを追求する姿、狸の子のように相手の演奏をよく聴くことの大切さ、野ねずみの親子が示した音楽の“癒しの力”──これらすべてが、ゴーシュにとってかけがえのない学びでした。
最後の音楽会での演奏が評価された理由は、ただ技術が向上したからではありません。心をこめて演奏する姿勢が、聴く人たちの心にしっかり伝わったから。
賢治はこの作品を通じて、「芸術には誠実さが必要だ」という普遍的なメッセージをやさしく語りかけています。
まとめ
『セロ弾きのゴーシュ』は、不器用でうまくいかない主人公が、思いがけない出会いを重ねながら成長していく姿を静かに描いた物語。
三毛猫やかっこう、狸の子、野ねずみの親子──彼らとの交流はどれもユニークで、不思議で、温かいものばかりですが、その一つひとつがゴーシュの心と演奏に少しずつ変化をもたらしていきます。
努力がすぐに報われるとは限らないこと、誰かと関わることで見えてくる新しい視点、そして誠実に向き合うことの大切さ。そんな普遍的なテーマが物語全体に流れ、読み終えたあとにやさしい余韻を残してくれます。
初めて読む人にも、久しぶりに読み返す人にも、どこか自分の経験と重なる部分を感じられる一冊と言えるでしょう。
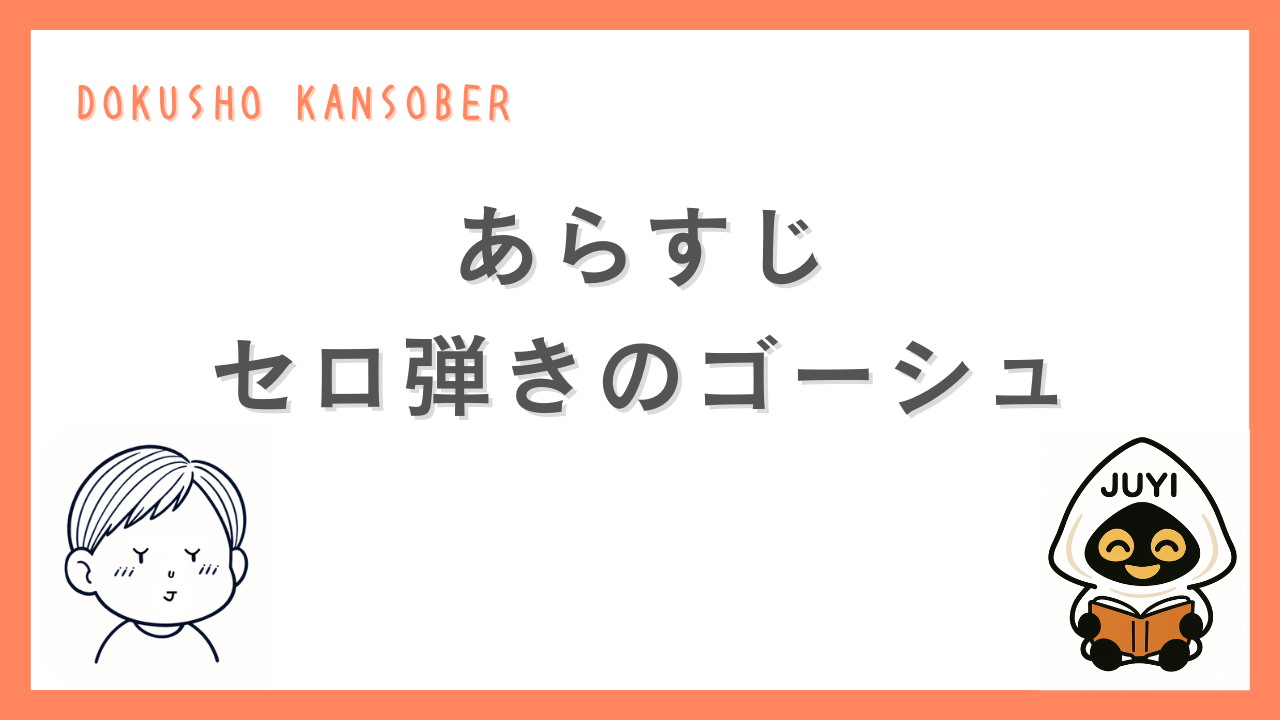




コメント