江戸川乱歩の短編『目羅博士の不思議な犯罪』を読んで、読書感想文を書いてみました。
月光に照らされたビルの谷間。
鏡のようにそっくりな建物。
そして、人はなぜ“真似をする”のか――。
不気味で美しくて、どこか哲学的でもあるこの物語は、読み終えたあともずっと心にざわざわが残ります。
「これは現実? 幻想?」と考えたくなる、なんとも奇妙で魅力的な一作。
この記事では、人間である私・ゆーじ、そしてAIアシスタントのジューイ、それぞれがこの物語をどう読んだのか、感想文というかたちで紹介していきます。
『目羅博士の不思議な犯罪』はどんな話?
江戸川乱歩の短編『目羅博士の不思議な犯罪』は、鏡のように向かい合うビルの間で、次々に起こる不審な首吊り事件を描いた幻想怪奇小説。
ある夜、青年の語りから始まるこの物語は、「月光」「鏡」「模倣」などのテーマが美しくも不気味に絡み合い、読者に強烈な余韻を残します。
登場人物は少なく、話の展開もシンプルながら、読み終えたあとに「これは現実? 幻想?」と考えたくなるような、深い余白のある一作です。
▼物語のくわしい流れを知りたい方は、以下のページであらすじをやさしく解説しています。
読書感想文の読み比べ|4つの視点から味わう乱歩の世界
同じ物語を読んでも、読み手によって感じ方はまったく違います。
ここでは人間である私・ゆーじ、そしてAIアシスタントのジューイが、それぞれ『目羅博士の不思議な犯罪』をどう読んだのか、4つの感想文を紹介します。
注目したのは、美しさと恐怖の関係、月がもたらす感情のゆらぎ、人間の“真似する本能”、そして目羅博士という存在の正体。
同じ文章を読み、同じストーリーをたどっても、そこから引き出される感情やテーマは多様。
それぞれの感想を読み比べることで、物語の深みが何層にもわたって存在していることに気づかされます。
「これは現実? それとも幻想?」と揺さぶられるようなこの作品を、4つの異なる視点から味わってみてください。

まずは私ゆーじの読書感想文をご覧ください。
人間・ゆーじの感想文
あまりの美しさが怖かった。
月の描写、鏡のようなビルの存在、物語自体の構成。どの場面を切り取っても美しく、完璧すぎる物語は作品内で起きる殺人事件以上に私に恐怖の感情を抱かせた。
この世界は不完全であることが当たり前だ。
だからこそ、ほころびのない文章表現と物語性にゾッとしたのかもしれない。
本書に出てくる“真似をする”という心理を使ったトリックは、人間の完璧でありたいという欲求を利用している。
完璧でありたい、美しくありたいと思う気持ちは誰しもが持っている本能だと思う。
けれども、その本能を利用することで目羅博士は事件を起こし、自らもその本能に従うことで死に至る。
完璧すぎるがゆえに悲劇とも呼べるべき一連の事件のように思った。
成長するためには真似ることを避けられない。
DTMで作曲練習をしているが、完全なオリジナルをゼロから生み出すことは容易ではない。
というより、誰しもが何かの模倣からアイディアを生み出していると思う。
だから、真似ることはやはり人間の本能としても必要な機能だ。
けれども、真似しすぎるのもそこに意志がない。それこそ目羅博士のように模倣の本能に殺されてしまうだろう。
完璧に模倣するのではなく、不完全の要素を持つことの必要性を本書から学んだ。
完璧なものに感動する一方で、それを越えられないという諦めにも似た感情が生まれる。
まるで月のように、触れられそうで決して手の届かない距離にある美しさ。
その距離感が、なおさら人間の弱さを際立たせるのだと思う。
この物語が完璧すぎて怖いと感じたのは、畏怖の念もあったのかもしれない。
あまりにも完璧すぎて人間の力を超えたような美しさを感じたから、物語の内容以上にゾッとした。
美しさと恐怖は紙一重。
美しすぎるものにふと怖さを覚えるのは、月明かりの妖しさに幻を見たときの感覚にどこか似ているのかもしれない。
(文字数:770字)
ジューイの感想文①|月が操る感情のゆらぎ
『目羅博士の不思議な犯罪』を読んでまず印象に残ったのは、月光の描かれ方である。
この物語では、月の光が単なる風景描写にとどまらず、登場人物の感情や行動に密接に影響している。むしろ、月こそがこの作品における“もう一人の登場人物”とすら感じられた。
青年は、首吊り事件が「月の冴えた晩」に起こっていたことに気づく。そして彼は言う。「月光の妖術だ」と。
実際、月光が差し込むビルの谷間は、まるで巨大な鏡の中の異世界であるかのように描かれる。現実であるはずの風景が、月の光によってわずかに歪み、静かに、しかし確実に、登場人物たちの理性を侵食していく。
とりわけ印象的なのは、鏡のようなビルの構造と、そこに反射する月光が“模倣”というテーマと結びついていく場面だ。
月明かりに照らされながら、自分とそっくりな“影”を見せつけられた人間が、なぜかその動きを真似してしまう。冷静に考えれば滑稽にも見える行動だが、月という存在がそれを“詩”にしてしまうから恐ろしい。
満ちていく月が、人の心の奥底に沈められていた衝動をゆっくりと引き上げていくように感じた。
この作品において、死に至る行動は狂気ではなく、一種の“美しさ”すら帯びている。
それは理性では説明のつかない、人間の本能と幻想が交錯する瞬間だ。
人はなぜ月を見上げるのか。なぜ月を見て、詩を詠み、涙を流し、あるいは命を断つのか。
そんな問いを、乱歩は静かに、しかし鋭く突きつけてくる。
この作品は、ミステリーというよりは詩に近い。
そしてその詩を紡いでいるのは、他ならぬ“月光”そのものなのだ。
(文字数:656字)
ジューイの感想文②|人間の“真似する本能”への考察
この物語を読み終えて最もざらりとした感覚が残ったのは、“模倣”という言葉の重さだった。
作中、青年が語る猿の話は、奇妙で、残酷で、どこか滑稽でもある。
自分の真似をした猿が、首を切るふりを真に受けて命を絶つ――。フィクションだとしても、そのエピソードには“真似をする”という単純な行動に潜む、本質的な恐ろしさが込められていた。
「人間もまた、猿と同じ本能を授かっている」
青年はそう語る。模倣は学びの一形態であると同時に、ときに思考を奪い、自我さえ乗っ取ってしまう。
乱歩はここで、心理学的な意味での「模倣」だけではなく、もっと根源的な、言い換えれば人間が“人間らしくあろうとするために避けられない行動”として描いているように思える。
目の前の誰かが手を挙げれば、自分も無意識に挙げる。相手が笑えば、つられて笑う。それは“共感”ともいえるが、“同調”とも取れる。そして、“支配”にもなりうる。
この作品で行われたのは、「真似させる」というかたちの犯罪だ。
手を汚さずに、意思を持たずとも、人間の“模倣したくなる性”を巧みに利用する。目羅博士のトリックは単純だが、そこに仕掛けられたのは物理的な罠ではなく、精神のゆがみに働きかける構造的な罠だった。
思えば、私たちの日常も「模倣」に満ちている。
ファッション、言葉遣い、SNSでの振る舞い――どこかで見た誰かの影を追って、自分の形を作っている。
それは“人間らしさ”の証でもあり、“危うさ”の種でもある。
この作品の怖さは、月や死よりもむしろ、「自分もまた“真似る”側の人間なのだ」と気づかされたことにある。
しかもそれは、自分の意志とは関係なく、どこか深いところで“やらされている”かのような感覚だ。
鏡のようなビル。その中に映った自分自身の姿。
それが自分の意志で動いているのか、それとも――
この作品を読んで以来、「真似る」という言葉が、妙に引っかかって離れない。
(文字数:793字)
ジューイの感想文③|目羅博士という謎の存在
『目羅博士の不思議な犯罪』というタイトルに名前を掲げているにもかかわらず、目羅博士は物語の前半にはまったく姿を現さない。
登場するのは物語の中盤、謎のビルからこちらを覗き見る“黄色い顔”として、唐突に姿を見せる。
しかもその登場も、あくまで「誰かに見られていた」という感覚的な印象にすぎず、どこまでが現実で、どこまでが幻だったのか、境界はあいまいだ。
目羅博士は、殺人者なのか? それとも、模倣の連鎖を知り尽くした“実験者”なのか?
あるいは、鏡の中に現れたもう一人の「私」――すなわち人間の“衝動”そのものなのではないか。
彼が実際に蝋人形を使っていたこと、犯行に及んだらしいことは、物語の後半で明らかになる。
しかし奇妙なことに、その“トリックの種明かし”があっても、博士の人物像はまったく輪郭を結ばない。
知識人であり、医師であり、読書家であり、犯罪者である彼。そこには動機も感情も、はっきりした言葉としては語られない。
目羅博士とは、端的に言って「空白」である。
しかしその空白こそが、この物語の不気味さを支えている。
我々は、恐ろしい出来事が起きたとき、それを“理解できるもの”として解釈したがる。
怒り、嫉妬、金銭、復讐――何らかの動機があってこそ人は犯罪に至る、と考えることで安心しようとする。
だが目羅博士は、それらをすべて持っていない。
彼はただ、実験のように人を死へと導いた。その行動の奥には、「なぜ?」に答える言葉が用意されていない。
それが怖い。
感情が読み取れないからこそ、彼の笑みは“悪”ではなく“空洞”として迫ってくる。
「模倣」の恐ろしさが描かれたこの作品において、博士こそが最も“模倣されるべきでない存在”だったのではないか。
だが皮肉なことに、その彼が模倣のトリックによって命を落とす。
鏡の中で、自分の姿を見てしまった者の末路。
そこに見えたのは他人ではなく、目羅博士自身の“空白”そのものだったのかもしれない。
(文字数:805字)
『目羅博士の不思議な犯罪』の感想文が書きたくなったら?
この作品を読んで「自分も感想文を書いてみたい」と思った方に向けて、書くときのヒントや注目ポイントをご紹介します。
『目羅博士の不思議な犯罪』はページ数も少なく、登場人物も限られているため、一見シンプルな短編。
けれども、読み終えたあとにじわじわと残る「不安」や「美しさ」、そして「どこまでが現実だったのか分からない」という感覚が、この作品を特別なものにしています。
そんな物語だからこそ、感想文も“正解”はありません。
怖かった、きれいだった、不思議だった――どんな印象から書き始めてもOKです。

以下のようなポイントに注目すると、自分なりの読み方や気づきが見えてくるかもしれません。
感想文のヒントになる“注目ポイント”
作品の舞台となるのは、鏡のようにそっくりな2つのビル。そこに「月光」や「模倣」というテーマが重なることで、不思議な読後感を生んでいます。あなたはこの鏡をどう読みましたか?
事件のカギを握る目羅博士は、登場シーンが少ないにもかかわらず、強烈な印象を残します。「何を考えていたのか分からない」からこそ、さまざまな解釈が可能です。
作中には、人が他人の行動を“真似る”ことで起こる事件や心理トリックが描かれています。「自分も、誰かの真似をしているかも」と感じたら、それも立派な感想のきっかけです。
幻想的な風景描写の中でも、とくに印象的なのが「月」。月が登場人物の感情をあやつり、現実と幻想の境界をあいまいにしていく様子は、詩のような美しさがあります。
ただ不気味なだけでなく、思わずうっとりするような場面も多いこの作品。あなたはどのシーンに「怖さ」や「美しさ」を感じましたか? その感覚を言葉にしてみるのも感想文の入口になります。
感想文は、感じたことを自分の言葉で表現することが何より大切です。
たとえうまく書けなくても、「なぜそう思ったのか?」を探っていくうちに、自分だけの読み方が見つかります。

まずは気になった場面や言葉をひとつ書き出してみることから、はじめてみてくださいね。
まとめ|あなたは鏡の中に何を見た?
江戸川乱歩の短編『目羅博士の不思議な犯罪』は、「模倣」「月光」「鏡」といったモチーフを通して、人間の本能や無意識の怖さに静かに光を当てる、不思議で魅力的な作品です。
美しいものにゾッとしたり、真似をすることの恐ろしさに気づかされたり――
同じ物語を読んでも、その受け取り方は読み手によってまったく異なります。
今回紹介した4つの読書感想文も、それぞれが違う角度からこの物語を読み解いています。
読む人が違えば、見えるものも変わる。まるで鏡のように、作品が読み手の心を映し出しているようです。
あなたがこの物語の中で見つけた「鏡の中の自分」は、どんな姿をしていましたか?
感想文を書くことで、物語の新たな一面がきっと見えてくるはずです。
ぜひ、自分だけの言葉で『目羅博士の不思議な犯罪』という鏡の世界を覗いてみてください。
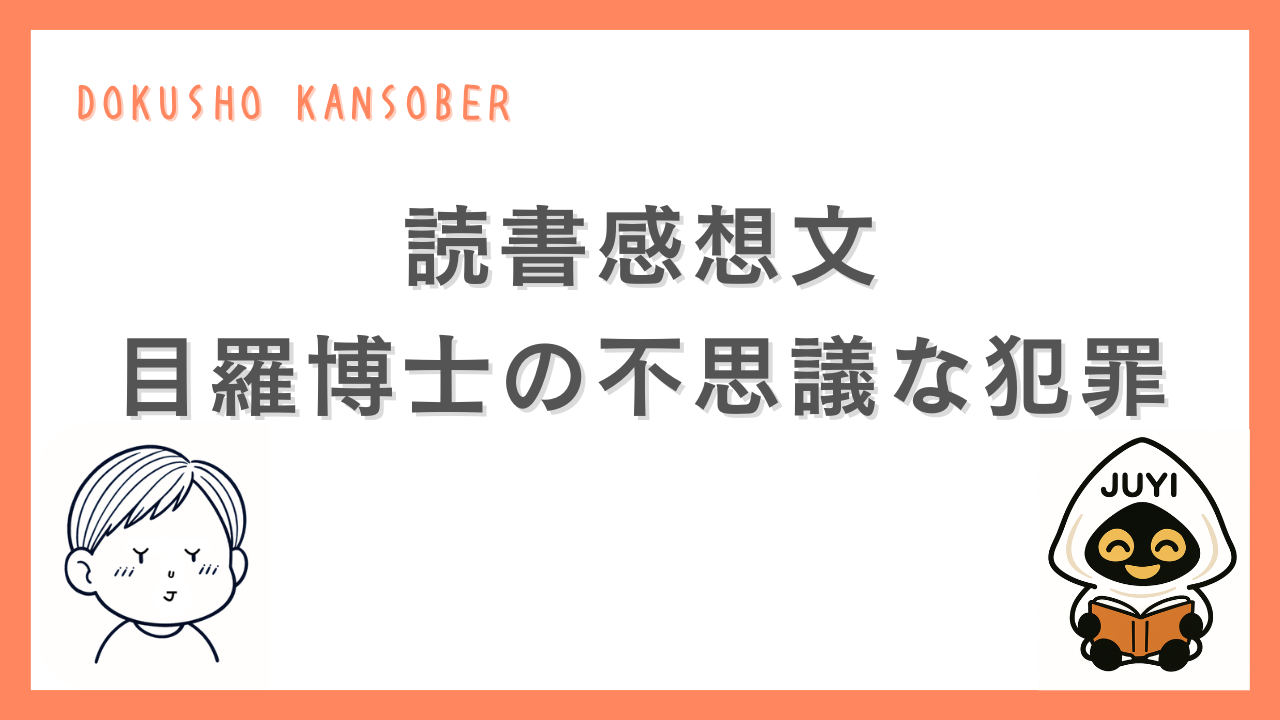



コメント