世界でたった一頭だけ、仲間に声が届かないクジラがいる。
その鳴き声は「52ヘルツ」。誰にも届かない孤独な周波数を持つクジラをモチーフに描かれた小説が、町田そのこの『52ヘルツのクジラたち』です。
第18回本屋大賞を受賞した本作は、虐待や孤独といった重いテーマを抱えながらも、読後にそっと温かい光を残す物語。声を失った少年と、過去に心を閉ざした女性・貴瑚(きこ)が出会い、互いの傷を通して“生き直す”までの過程が丁寧に描かれています。
この記事では、『52ヘルツのクジラたち』のあらすじ・登場人物・テーマ・魅力を、ネタバレを避けながらわかりやすく解説します。
読む前に世界観を知りたい方も、読後にもう一度余韻を味わいたい方も、この物語がなぜ多くの読者の心を震わせたのかを、ぜひ一緒にたどっていきましょう。
作品概要と「52ヘルツのクジラ」に込められた意味
静かな海の底で、たった一頭のクジラが鳴いている。けれど、その声は誰にも届かない──。
この小説『52ヘルツのクジラたち』は、そんな“聞こえない声”を抱えた人々を描いた、町田そのこの代表作です。
舞台となるのは、大分の海辺にある小さな町。過去に深く傷ついた女性と、声を失った少年が偶然出会い、互いの存在を通して再び「人とつながること」「生きること」を学んでいく物語です。
重いテーマを扱いながらも、読み終えたあとに残るのは悲しみではなく、確かな希望。孤独や痛みに寄り添いながら、やさしさの意味を問いかけてくれる一冊です。

ここではまず、著者・町田そのこがこの物語で何を描こうとしたのか、そしてタイトルに込められた「52ヘルツ」という象徴が何を意味しているのかを整理していきます。
町田そのこが初めて長編で描いた“癒しと再生”の物語
町田そのこさんにとって『52ヘルツのクジラたち』は、初めての長編小説。
彼女はこれまで、短編集『夜空に泳ぐチョコレートグラミー』などで、人の心の「痛み」と「優しさ」を繊細に描いてきました。
しかし本作では、そのテーマをより深く掘り下げ、「傷ついた人がどう立ち上がるか」「他者とどう再び関わるか」という“再生”の物語として展開しています。
作者自身、母であり、また社会のニュースを見て「虐待を受けた子どもをどうすれば救えるのか」と考え続けてきたと語っています。
そうした現実への問題意識が、この作品の根っこにあります。
「声を上げたい人」「声を上げることを諦めた人」「そもそも声を上げる方法を知らない人」。
そういう人たちの存在を、物語としてすくい上げたいと思いました。
(出典:朝日新聞出版『好書好日』インタビューより)
この言葉どおり、本作には“声にならない声”があふれています。
主人公・貴瑚も少年も、過去の暴力や無関心によって「声を奪われた」存在。それでも彼らは出会いを通して、少しずつ“もう一度声を出す勇気”を取り戻していく。
その過程こそが、本作の大きな魅力であり、読者が心を動かされる理由でもあります。
町田作品の特徴は、現実を突き放さず、そこに“祈り”を見いだすところです。
人の痛みを真正面から描きながら、「それでも人はつながれる」という希望で結ぶ。この構成のバランスが、彼女の筆致をより際立たせています。
「52ヘルツのクジラ」とは?──世界で最も孤独な存在
タイトルに登場する“52ヘルツのクジラ”は、実際に存在が確認されているクジラのこと。
他のクジラが出す周波数(だいたい20ヘルツ前後)とは異なり、このクジラは52ヘルツという高い音で鳴くため、仲間には声が届かないと言われています。
そのため、「世界で最も孤独なクジラ」として知られています。
この設定は、物語全体の象徴。作中の登場人物たちは、まさに“声が届かない”世界を生きています。
助けを求めても誰にも気づかれない、あるいは「そんなの大げさだ」と片づけられてしまう。それでも彼らは、自分の声をあげることをやめません。
このクジラの存在は、「それでも誰かに届くことを信じたい」という希望を意味しています。
貴瑚が少年に「52」という名前をつけたのも、きっとそんな祈りのような気持ちからでしょう。
52ヘルツの声は、もしかすると他のクジラには届かないかもしれない。
でも、人間の私たちには聞こえるかもしれない。
そう考えると、このタイトルには「孤独な人の声を受け止めたい」という深いメッセージが込められているのです。
本屋大賞ほか多くの賞を受賞、100万部を突破した理由
『52ヘルツのクジラたち』は、2021年に第18回本屋大賞を受賞しました。
その後、「未来屋小説大賞」や「王様のブランチBOOK大賞2020」など、数々の賞に輝き、文庫版を含めて累計100万部を突破する大ヒット作となりました。
この快挙の背景には、作品の「社会性」と「読後の救い」があります。
- 社会性:虐待・DV・ヤングケアラー・LGBTなど、現代社会の“声にならない痛み”をリアルに描く。
- 物語性:絶望の中にあっても、他者との関係を通して希望を見出す構成。
- 読後感:重いテーマにも関わらず、「明日を生きよう」と思える余韻を残す。
こうした点が、多くの書店員や読者の共感を呼びました。
また、2024年には杉咲花さんと志尊淳さんの出演で映画化され、再び注目を集めています。
映画の主演・杉咲花さんはインタビューで、「誰もが生きていることを祝福される社会であってほしい」と語りました。
この言葉は、まさに作品全体のメッセージそのものです。
『52ヘルツのクジラたち』がこれほど多くの人に届いた理由は、決して“感動作だから”だけではありません。そこに描かれているのは、誰もが一度は感じたことのある“孤独”であり、それでも誰かを想う力です。
読者は物語を通して、登場人物たちの痛みを自分の中にも感じ、そして少しだけ世界をやさしく見つめ直す。
その静かな共鳴が、この本を特別な存在にしています。
『52ヘルツのクジラたち』のあらすじ(ネタバレなし)
物語の舞台は、大分県の海辺にある静かな町。
そこへ東京から一人の女性・三島貴瑚(みしま きこ)が移り住むところから始まります。
都会での人間関係や過去の痛みから逃れるようにこの町にやってきた彼女は、海を望む古い一軒家で、誰にも知られず静かに暮らそうとしていました。
しかしその決意は、ある少年との出会いによって少しずつ崩れていきます。
過去から逃げた女性・貴瑚と“ムシ”と呼ばれた少年
貴瑚は、長年にわたって家族から心を搾取されてきた女性。幼いころから母の愛情を得られず、成人してもなお家庭の犠牲として生きてきた彼女は、ある事件をきっかけにすべての人間関係を断ち切ります。
逃げるようにたどり着いた海辺の町では、人と関わらずに暮らすことを望んでいました。
そんなある日、近所で見かけた少年に目をとめます。
13歳ほどのその少年は、母親から「ムシ」と呼ばれ、常に怯えた表情を浮かべていました。
言葉を発しようとせず、周囲の大人たちも関心を寄せない。
その姿に、貴瑚はかつての自分の影を見ます。
少年の沈黙は、ただの“無口”ではなく、恐怖と絶望によって声を失った結果でした。
誰も助けない世界で、それでも彼が生きているという事実だけが、貴瑚の心を強く揺さぶります。
やがて彼女は、その少年を家に迎え入れる決意をします。
心を閉ざした二人が見つけた“救い”のかたち
貴瑚と少年の生活は、最初こそぎこちなく、静かな時間が流れていました。彼女は料理を作り、少年は小さな変化にも敏感に反応する。
言葉はなくても、湯気の立つ味噌汁や、並んだ茶碗のぬくもりが、少しずつ心の距離を縮めていきます。
貴瑚は少年に「52」というニックネームをつけます。
それは、他のクジラには聞こえない周波数で鳴く“52ヘルツのクジラ”にちなんだ名前でした。誰にも届かない声を上げ続けるクジラのように、彼の中にも届かない叫びがあると感じたのです。
その名を呼ぶことで、貴瑚は少年に「あなたの声はちゃんとここに届いている」と伝えたかったのでしょう。
そして少年もまた、貴瑚の存在によって少しずつ変わっていきます。最初は一言も話さなかった彼が、目線を合わせ、手を伸ばし、微笑みを返す。
ほんのわずかな変化が、ふたりにとっては確かな希望の証でした。
この過程で、貴瑚は自分がかつて救われたときの記憶を思い出します。
それは、かつて彼女に手を差し伸べてくれた恩人・岡田安吾(アンさん)との時間。
その優しさを今度は自分が誰かに渡す番なのだと気づくのです。
波のように寄せ合う孤独──希望へと変わる瞬間
二人の暮らしには、穏やかな日々とともに、痛みも寄せては返します。
貴瑚は少年を守ろうとしながらも、過去の傷に引きずられ、時に無力さを感じます。それでも、彼女は逃げませんでした。
少年の沈黙の奥にある“声なき声”を聞こうとする姿勢こそ、彼女自身が再生するための道でした。
一方で少年も、貴瑚と過ごすうちに少しずつ世界を受け入れはじめます。夜の食卓での笑い声、小さな手を握る温もり。
その一つひとつが、彼の中で「生きていい」という実感に変わっていきます。
『52ヘルツのクジラたち』は、特別な出来事が起きる物語ではありません。
誰かの心に静かに灯りがともるような、日常の中の奇跡を描いています。
貴瑚と少年の姿は、まるで寄せては返す波のよう。完全に溶け合うことはなくても、互いに少しずつ距離を縮めながら、孤独を希望に変えていく。
その姿が、読む人の心に“やさしい共鳴”を残すのです。
本作の魅力は、派手な展開や劇的な結末ではなく、「誰かの声を聞こうとする」という、たった一つの行為の尊さにあります。
読者はふたりの関係を通して、自分の周りにも届かない声があるのではないかと、静かに振り返るきっかけをもらえるでしょう。
孤独から始まり、共鳴で終わる物語。

それが『52ヘルツのクジラたち』の“ネタバレなし”の全体像です。
登場人物とそれぞれの背景
『52ヘルツのクジラたち』の魅力は、物語そのものだけでなく、登場人物たち一人ひとりの“人生の音”にあります。
どの人物も傷を抱えながら、互いの存在によって少しずつ変わっていく。その姿が読者の心を静かに揺らします。
ここでは、物語の中心となる4つの視点から人物の背景と役割を紹介します。
三島貴瑚──誰にも届かなかった声を抱える主人公
主人公・三島貴瑚(みしま きこ)は、長年家族に搾取されてきた女性。
幼いころから母の愛情を得られず、義父の介護を一人で背負い、弟だけが可愛がられる家庭で生きてきました。家族の中で“便利な存在”として扱われ続けた貴瑚は、次第に自分の価値を見失っていきます。
21歳のとき、限界を迎えた貴瑚を救ったのが、後に彼女の心の支えとなる岡田安吾(アンさん)です。
安吾との出会いが彼女に“逃げる勇気”を与え、そこからようやく自分の人生を取り戻す一歩を踏み出します。
しかし、心の傷は簡単に癒えません。
人を信じることが怖く、優しさに触れるとまた傷つくのではないかと怯える。そんな彼女が「ムシ」と呼ばれる少年と出会い、自分の過去と重ねながらも“もう一度誰かと生きよう”と決意するのです。
貴瑚は「助けることでしか自分を救えない」人。彼女の行動には痛みと優しさが同居しており、その不器用さが人間らしい温度を持っています。
読者は彼女の再生を通して、「他人を救うことは、自分を救うことでもある」と気づかされるでしょう。
少年「52」──言葉を失った心が再び動き出すまで
13歳の少年は、母親から「ムシ」と呼ばれ、虐待を受けながら生きてきました。
彼は恐怖の中で声を失い、誰にも助けを求められずにいた子どもです。無表情で、怯えたような瞳の奥にあるのは、世界への絶望と、ほんの少しの希望。
貴瑚がそんな彼を見つけたとき、彼女の中で何かが動き出します。
「過去の自分をもう一度抱きしめるように、彼を救いたい」――それが貴瑚の願いでした。
やがて彼は貴瑚に「52」と名づけられます。
それは“誰にも届かない声を出し続けるクジラ”の名。貴瑚にとって彼は「届かない声をもう一度響かせてほしい存在」であり、少年にとって貴瑚は“初めて声を聞いてくれた人”でした。
言葉を発せない彼が、目線を合わせ、手を伸ばし、微笑む。
その一つひとつの行動が、貴瑚と読者にとって何よりも大きな“声”として響きます。
彼の変化は、希望が人をどう動かすのかを静かに教えてくれるのです。
岡田安吾(アンさん)──貴瑚を支えた“もうひとつの救い”
貴瑚が過去の地獄から抜け出せたのは、このアンさんの存在があったから。
彼は貴瑚の友人・美晴の同僚で、何気ない優しさを持つ大人の男性。貴瑚が最も孤独だった時期に、「それは恩じゃない、呪いだよ」と彼女の心の鎖を解く言葉をかけます。
アンさんの優しさは、押しつけでも説教でもなく、“相手の痛みを認める”やわらかな光です。彼は貴瑚に「逃げてもいい」と伝え、彼女が生き直すきっかけを作りました。
物語が進むにつれて、貴瑚はアンさんの不在を感じながらも、その言葉に何度も支えられます。彼の存在は、作品全体の“見えない支柱”のようなもの。
直接的な登場シーンは少なくても、その影響は貴瑚や読者の心に深く残ります。
アンさんの役割は、希望の象徴であり、「人は誰かに優しくされると、その優しさを次に渡したくなる」という連鎖を示すものでもあります。
彼の温かい眼差しが、物語全体に穏やかな光を与えているのです。
牧岡美晴と村中真帆──新たなつながりを照らす存在
牧岡美晴(まきおか みはる)は、貴瑚の高校時代からの親友。
彼女自身も複雑な家庭環境を経験しており、貴瑚の心の痛みに深く共感しています。貴瑚が東京を離れたあとも、彼女を心配し続け、支援を惜しまない存在です。
美晴は、貴瑚にとって“家族とは違う絆”を教えてくれる人。
彼女の存在があることで、貴瑚は人との関係をもう一度信じることができました。
一方で村中真帆(むらなか まほろ)は、貴瑚が移り住んだ町で出会う職人の男性です。
古い家を修理しに訪れた彼は、気さくで頼もしい性格の持ち主。閉ざされた世界にいた貴瑚に、日常の明るさや人の温かさを思い出させます。
二人はそれぞれ、貴瑚の人生に“地に足のついた優しさ”をもたらす存在です。
彼女たちがいたからこそ、貴瑚は「誰かと共に生きる」現実的な温もりを取り戻すことができました。
『52ヘルツのクジラたち』の登場人物は、誰もが“完全ではない”存在です。
それでも、互いの傷を見つめ合いながら小さな光を分け合って生きていく。

その姿こそ、この物語が多くの読者に愛される理由なのです。
作品が問いかけるテーマとメッセージ
『52ヘルツのクジラたち』が多くの読者の心に残るのは、「見えない痛み」「聞こえない声」に焦点を当てているから。
町田そのこは、誰もが日常の中で見過ごしてしまう“声なき存在”を描くことで、私たち自身の向き合い方を問いかけます。
ここでは、物語を通して浮かび上がる3つの核心テーマを掘り下げます。
“聞こえない声”に耳を傾けるということ
タイトルに込められた「52ヘルツ」は、他のクジラには届かない高い周波数。つまり、「誰にも届かない声」を象徴しています。
貴瑚も少年も、助けを求めても誰からも応えてもらえなかった人たちです。それでも彼らは、声を上げることをやめません。
物語を読み進めるうちに、「聞こえない」のは本当に“声の問題”ではなく、“聞こうとしない社会”の問題だと気づかされます。
見て見ぬふりをすること、無関心でいること――それが人を最も深く傷つける。
貴瑚が少年の存在を放っておけなかったのは、過去の自分が誰にも気づかれなかったからです。
そして、少年もまた、貴瑚の優しさに触れて初めて「自分の声を聞いてくれる人がいる」と感じ始めます。
この関係性が示しているのは、「人は誰かの“耳”になることで救われる」という真理。
聞こえない声に耳を傾けること、それは他人を理解することの第一歩であり、社会を少しだけやさしくする行為でもあります。
虐待・孤独・偏見──現代社会の痛みに向き合う
本作では、物語の随所に現代社会が抱える問題が織り込まれています。
児童虐待、家庭内暴力、ヤングケアラー、そして偏見――それらはニュースで耳にする“誰かの出来事”ではなく、日常のすぐそばにある現実です。
貴瑚は「家族のため」という言葉に縛られ、自分を犠牲にして生きてきました。
少年は「子どものくせに」という偏見のもとで、苦しみを隠しながら生き延びてきました。
どちらも“他人の無理解”がつくり出した孤独の中にいます。
作者の町田そのこはインタビューで、「声なき声にはいくつかの種類がある」と語っています。声を上げたい人、上げることを諦めた人、そして上げ方すら知らない人。
この分類は、社会に生きる私たちの姿そのものです。
作中では、周囲の偏見や無関心が、どれほど人を追い詰めるかが静かに描かれます。
それでも、作品が暗くならないのは、登場人物たちが「それでも生きる」ことを選ぶから。
痛みを描くだけでなく、そこに“人間のしなやかさ”を見せてくれる点に、町田作品の真骨頂があります。
人と人のつながりがもたらす再生の光
『52ヘルツのクジラたち』の根底には、「人は他者によって生き直せる」というメッセージがあります。
貴瑚が少年を救おうとしたことは、同時に自分自身を救う行為でもありました。
そして少年の存在が、貴瑚に「愛されてもいい」「信じてもいい」という気持ちを取り戻させます。
この“相互の救い”こそが、本作最大のテーマです。
助ける側・助けられる側という一方通行の関係ではなく、どちらも同じように再生していく。その過程が、まるで波が寄せ合うように丁寧に描かれています。
また、貴瑚を支える美晴やアンさん、村中といった登場人物も、彼女に新たな光を与えます。
人とのつながりは時に面倒で、痛みを伴うものですが、それでも誰かと出会うことで人生は変わる。そのリアルな描写が、多くの読者に“もう一度誰かを信じてみよう”という勇気を与えてくれます。
本作に流れるメッセージは決して派手ではありません。
それは、「あなたの声は、ちゃんと届いているよ」というささやかな励まし。
読後に残るのは涙ではなく、静かな希望の光です。

『52ヘルツのクジラたち』は、現代の孤独を描いた物語でありながら、“つながりの奇跡”を信じるための処方箋のような一冊です。読者が本を閉じたあとも、その余韻は深く、静かに心の奥で響き続けます。
映画版との違いから見える新しい解釈
2024年に公開された映画版『52ヘルツのクジラたち』では、物語の核心はそのままに、焦点の当て方が少し異なります。
監督は成島出さん、主演は杉咲花さん(貴瑚役)と志尊淳さん(岡田安吾役)。映像表現によって、原作では“行間で感じる”感情が、より具体的な形で描かれました。
大きな違いは、“語られない静けさ”の扱い方です。
原作では貴瑚や少年の沈黙を通して「声なき声」を読者が想像する構成ですが、映画ではその沈黙を表情や音で可視化。波の音や風のノイズが感情の代弁者となり、観客に“孤独の音”を体感させます。
また、貴瑚の描かれ方にも変化があります。
小説は彼女の内面を丁寧に追い、読者が“内側から”痛みを感じる構成。映画は映像を通して“外側から見守る”視点に切り替えられ、観る人に「どう支えるか」を問いかけます。
ラストの印象も異なります。
原作が“希望の余韻”で終わるのに対し、映画は“祈り”を明確に描くことで普遍的なメッセージへと昇華。
杉咲花さんの言葉どおり、「誰もが生きていることを祝福される社会であってほしい」という想いが全体を包みます。
小説は“心の内側の共鳴”、映画は“社会的共鳴”。
原作が寄り添う文学だとすれば、映画は現実への呼びかけです。

両方に触れることで、「届かないと思っていた声は、きっと誰かに届く」というメッセージがより深く胸に響くでしょう。
まとめ
『52ヘルツのクジラたち』は、孤独や痛みを描きながらも、最終的に“人の優しさ”と“再生の力”を信じさせてくれる物語。
声が届かないと思っていた人々が、誰かに出会うことで少しずつ変わっていく──その過程は、私たちの現実にも重なります。
貴瑚と少年の関係は、助ける側と助けられる側という単純な構図ではなく、互いに支え合い、影響し合うもの。
人は誰かの存在によって、自分の人生を取り戻すことができる。この作品が伝えているのは、そんな“共鳴”の希望です。
世界でたった一頭のクジラが放つ52ヘルツの声。
それは、誰にも届かないようでいて、確かにどこかに響いている。
この物語は、読者に「あなたの声もきっと誰かに届く」とそっと語りかけてくれる一冊です。
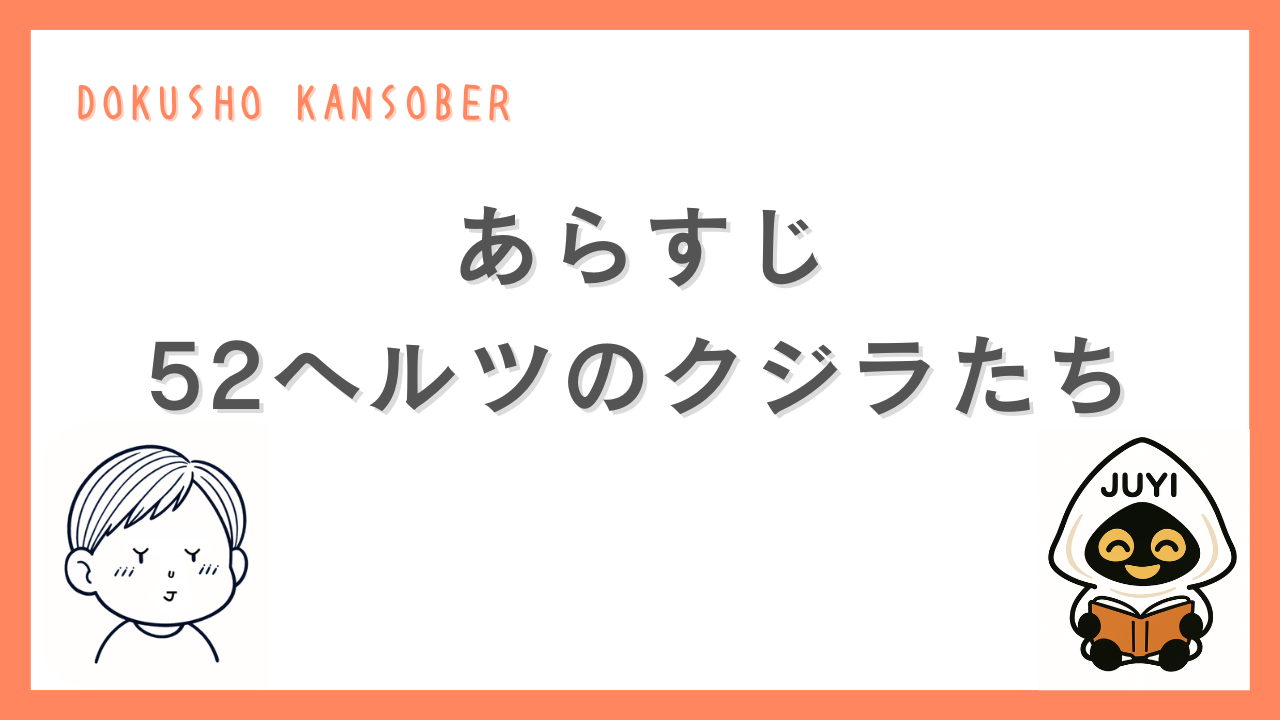




コメント