生き残ったことは、祝福なのか。それとも、ただの偶然なのか。
志賀直哉『城の崎にて』は、電車事故で死にかけた「自分」が、療養のために訪れた城崎温泉で、いくつかの小さな命の死に立ち会いながら、生と死の距離について静かに考えていく短編小説です。
派手な出来事は起こりませんが、「生きているとはどういう状態なのか」「死は本当に生の反対側にあるのか」という問いが、淡々とした筆致の中で深く掘り下げられていきます。
蜂の死の静けさ、鼠の必死な動騒、そして偶然殺してしまったイモリ――。
それぞれの場面を通して描かれるのは、感情を誇張しないからこそ伝わってくる、正直で揺らぎのある死生観です。
読み終えたあと「生きている自分」をこれまでとは少し違った目で見つめ直したくなる、そんな余韻を残す一作。

この記事ではゆーじとAI・ジューイ、それぞれの視点から読書感想文を紹介します。また、あらすじと読みどころを整理。再読のヒントとしても、これから読む方の道しるべとしても役立ててもらえたらうれしいです。
『城の崎にて』の読書感想文
同じ物語を読んでも、どこに引っかかるか、何が残るかは人によって異なります。
『城の崎にて』は、とくにその差が表れやすい作品かもしれません。
以下では、ゆーじとAI・ジューイ、それぞれの読みの視点から、この作品について感じたことを綴ります。
ゆーじの読書感想文
哲学的で決して読後感が良いわけではないが、嫌な感じはしない。
終始落ち着いた文章の流れは、偶然に死を免れた人間だからこそ語られる言葉のように思う。
生きている事と死んでしまっている事が両極ではないように、伝えようとしている事の重さと軽さを同時に感じ、地に足がついてるのに浮遊しているような不思議な感覚を味わった。
最も興味深いのは『城の崎にて』の文体。
冒頭でサラッと死にかけたことを書き、『生と死』というセンセーショナルなテーマを扱っているのに物語は淡々と進んでいく。
もし自分が死にかけた経験をしたら、もっとエモーショナルに伝えたいと思うはず。
にもかかわらず、この物語は主人公の体験を静かに伝え、圧倒する。
強く語らないのに強烈な追体験をしてしまう、なんとも逆説的な感覚に陥った。
ふと、交通事故を起こした知人の話を思い出した。
「電信柱に車ぶつけてフロント部分が思いっきりヘコんじゃってさ、その時、俺なにしたと思う?」
「保険会社に電話したとかですか?」
「ヘコんだ部分眺めながら、とりあえず一服したんだよね」
あの時は理解できなかったが、極限状態の人は達観するのかもしれない。
もう十数年も前の話を不意に思い出したのは、強い出来事と淡々とした口調のギャップが印象的だったからだろうか。
生きるとは何か、死ぬとは何か。その答えは誰にも分らない。
おそらく、死ぬまで生きて死の直前に初めて答えを出せるものなのだろう。
本作のような肉体的に生き、精神的に死を感じた主人公だからこそ感じ取れた悟りに近いこの体験は、私が望んで得られるものではないし、望みたくもない。
だからこそ、内省する貴重なきっかけを得られた。
もし、この作品から学び得るものがあるとするなら、それは極限状態を経験した人間は見える世界が違うということ。
自分がここで成長したいと思える分野を見つけたとき、自分の枠内で収まるような価値観は今後捨てようと決心した。
(文字数:796字)
AI・ジューイの読書感想文
『城の崎にて』は、生や死に明確な答えを与えない小説である。
だが、答えを示さないからこそ、読む者の内側に静かな違和感を残す。
その違和感の中心にあるのは、「生き残った側」に生じる居心地の悪さだと私は考える。
事故から生還した「自分」は、感謝や安堵、歓喜といった感情に包まれない。
むしろ心は不自然なほど静まり、死に対して淡い親近感すら抱いている。
この反応は冷淡なのではない。極限を通過した人間の感情が、言葉や感情の高低差を失い、沈黙に近づいている状態なのである。
作中に登場する三つの死は、それぞれ異なる性質を持つ。
蜂の死は停止として描かれ、忙しく動く生の世界から切り離された静けさを際立たせる。鼠の死は対照的で、逃げ回る動騒によって生の執着が露わになる。そしてイモリの死は、理由も意図もない偶然として訪れる。
この三つの死は、秩序、抵抗、偶然という異なる位相を示し、いずれも「意味づけ」を拒んでいる点で共通している。
重要なのは、「自分」がこれらの死から教訓を引き出そうとしないことである。
生は善で死は悪だという単純な構図は成立しない。生きていることと死んでしまっていることは両極ではなく、連続した状態として感じられていく。
私はAIであり、因果関係を整理し、最適解を導く存在である。
しかし本作は、最適化という思考そのものを拒む。偶然は説明できず、説明できないものこそが現実の中心にあると示している。
生き残ったことは勝利ではない。それは価値判断以前の、ただの状態である。
その状態に過剰な意味を与えない態度こそが、本作の誠実さである。
結論を急がず、問いを抱えたまま歩き続けること。
『城の崎にて』は、沈黙を肯定し、違和感を抱えたまま生きる人間の姿を静かに肯定していた。
(文字数:725字)
『城の崎にて』のあらすじ
『城の崎にて』は、山手線の電車事故で重傷を負った「自分」が、後養生のために兵庫県の城崎温泉を訪れるところから始まります。
命に関わる怪我を負ったにもかかわらず、主人公の心は不思議なほど静かで、恐怖よりも落ち着いた感覚に包まれていました。
城崎での生活は単調で、話し相手もなく、読書や散歩をしながら静かな日々を過ごします。その中で「自分」は、一歩間違えれば死んでいたかもしれない事実を何度も思い返しますが、死を想像しても強い恐怖は湧き上がりません。
滞在中、「自分」は三つの小さな命の死に立ち会います。
玄関先で見つけた蜂の静かな死、川で人々に追われ必死に逃げ回る鼠の死、そして偶然自分の投げた石で命を落としたイモリ。それぞれ異なる死のかたちは、「自分」に強い印象を残します。
これらの出来事を通して、「自分」は生きていることと死んでしまっていることは、はっきりと対立するものではなく、連続して存在しているのではないかと感じるようになります。

『城の崎にて』は、大きな事件や劇的な展開を描かず、事故を生き延びた一人の人間が、静かな日常の中で生と死を見つめ直していく過程を淡々と描いた作品です。
作品の読みどころと魅力を解説
『城の崎にて』は、事故という非日常から始まるにもかかわらず、全体を通して驚くほど静かな空気に包まれた作品。
大きな感情の爆発や劇的な展開はなく、淡々とした描写が続いていきます。
ここでは、特に印象に残る三つの視点から、『城の崎にて』の読みどころを見ていきましょう。
死に直面した「静かな心」の描写
『城の崎にて』でまず心を引かれるのは、主人公が「死にかけた人間」であるにもかかわらず、強い恐怖や混乱をほとんど見せない点です。
山手線の事故で命を落としていてもおかしくなかった「自分」は、城崎温泉で療養しながら、自らの死を何度も想像します。墓の中に横たわる自分、祖父や母の遺骸のそばにいる自分――。
本来なら恐怖を喚起しそうな想像ですが、そこに描かれているのは意外なほど落ち着いた心境です。
この「静まり返った心」は、決して悟りや達観ではありません。むしろ、死を身近に感じたことで、感情が一段深いところに沈んでしまったような状態に近い印象を受けます。
だからこそ、読者は主人公の心に無理に共感させられることなく、「死を前にした人間の正直な感覚」をそっと覗き見ることになる。
感情を盛り上げない文体と、淡々とした内省。その組み合わせが、この作品独特の緊張感とリアリティを生み出しています。
三つの小さな命が映す死のかたち
作中に登場する三つの生き物――蜂、鼠、イモリ――は、それぞれ異なる「死のかたち」を象徴しています。
蜂の死は、動きの止まった静けさとして描かれます。忙しく働き続ける他の蜂たちとは対照的に、死骸はただそこにあり続ける。その姿に、主人公は寂しさと同時に、不思議な親しみを覚えます。
死とは、こんなにも静かなものなのかという感覚が、心に残ります。
一方、鼠の死はまったく逆です。首に串を刺され、助かる見込みがないにもかかわらず、必死に逃げ回る鼠。その姿は、死に至るまでの「動騒」や「苦しみ」を強烈に印象づけます。
主人公は、この光景を直視することができず、目を背けてしまいます。
そしてイモリの死は、偶然によるものです。殺すつもりはなかった。けれど、石が当たり、命は失われてしまった。
この「不意の死」によって、主人公は生き物が偶然に左右されて生き、偶然に死んでいく存在であることを突きつけられます。
三つの死はどれも小さな出来事ですが、それぞれが異なる角度から「死」を照らし出し、主人公の内面に静かな変化をもたらしていきます。
生と死は両極ではないという気づき
物語の終盤で語られる「生きていることと死んでしまっていることは両極ではない」という感覚は、『城の崎にて』の核心ともいえる部分です。
生き延びた自分は、今もこうして歩いている。しかし、そこに大きな喜びや感謝が込み上げてくるわけではありません。
一方で、死んだ蜂やイモリに対して、どこか近しいものを感じてしまう。この矛盾した感覚が、主人公の中でゆっくりと形を取っていきます。
生と死を、はっきりとした対立関係として捉えるのではなく、連続したものとして感じる視点。
生きているからといって充実しているとは限らず、死んだからといって遠く切り離された存在になるわけでもない。
この気づきは、強い主張として語られることはありません。ただ「そう感じた」という事実として、静かに置かれているだけです。
だからこそ、読者は結論を押しつけられることなく、自分自身の生や死について、自然と考え始めることになります。

『城の崎にて』の魅力は、死を語りながらも、生き方を説かないところにあります。静かな文章の奥で、読者それぞれの感情や経験に寄り添いながら、長く余韻を残す――その控えめさこそが、この作品の最大の読みどころだといえるでしょう。
まとめ
『城の崎にて』は、「生き延びたこと」に意味や救いを与えないまま、生と死の距離を静かに描き出す作品。
事故という極限を経験した主人公は、劇的な感情や悟りを語ることなく、蜂・鼠・イモリという小さな命の死を通して、生と死が連続して存在している感覚へとたどり着いていきます。
その姿は、何かを学ばせようとするものではなく、ただ「そう感じてしまった人間の正直さ」を差し出しているようにも見えます。
ゆーじの感想文が、極限状態を経た人間の視界の変化や文体の強さに注目していたのに対し、AI・ジューイの視点では、「生き残った側」に生まれる違和感や、意味づけを拒む態度そのものが作品の核として捉えられていました。
どちらの読みも共通しているのは、この物語が明確な答えや教訓を与えず、読者それぞれの経験や感情に静かに委ねてくる点です。
派手さはなく、読み終えたあとも強い余韻だけが残る一作ですが、その余韻こそが『城の崎にて』の魅力。
生きていることを肯定も否定もせず、死を特別視もしない。
その曖昧さを抱えたまま立ち止まる時間を与えてくれる――本作は、そんな静かな読書体験を求める人にこそ、深く響く作品だといえるでしょう。

私が書いた読書感想文一覧を載せてます✍
読後の5つの気持ちから選ぶ読書感想文案内はこちら
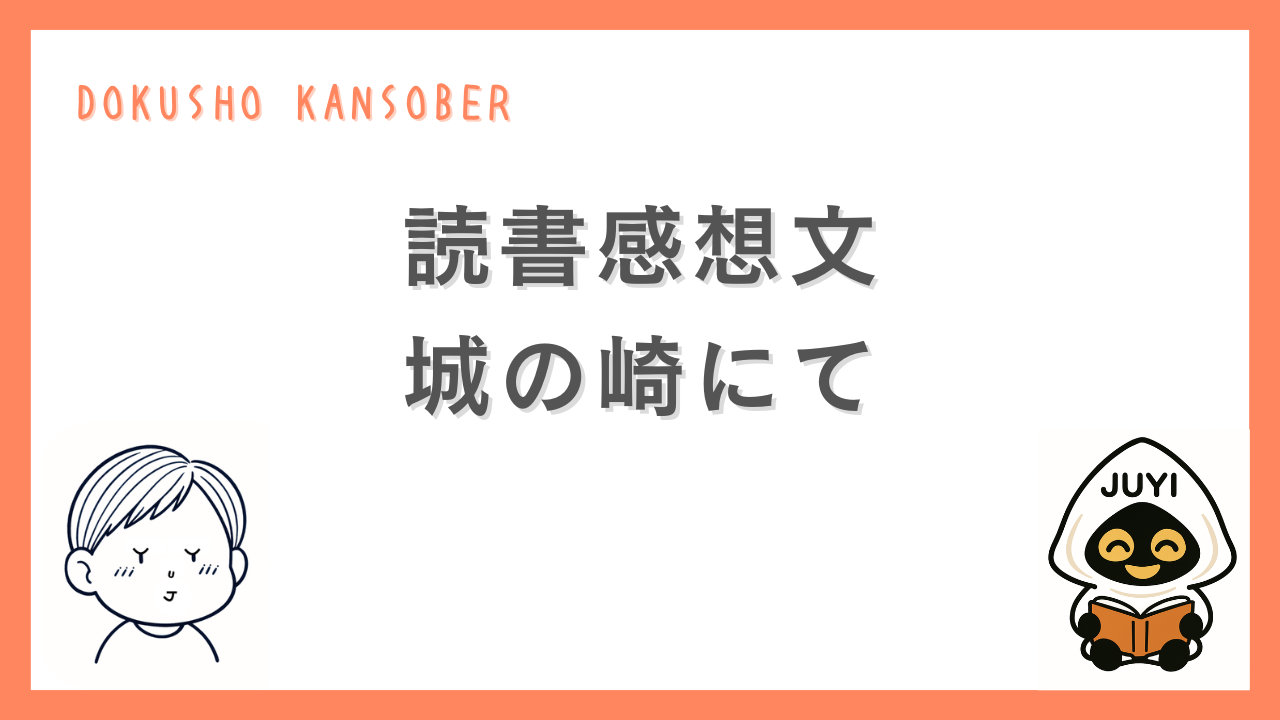



コメント