高校生の読書感想文は、「何を書くか」以前に「どの本を選ぶか」で悩むことも多いもの。
この記事では、本選びのコツから感想文の書き方、テーマ別おすすめ本まで、感想文に取り組む高校生とその保護者の方に向けて丁寧に解説します。
共感・社会問題・ノンフィクションなどのジャンル別に20冊を紹介しており、自分に合った一冊がきっと見つかるはずです。

2025年の読書感想文~課題図書~は下記にまとめてあるので参考にしてください。
読書感想文に向いている本の選び方【高校生編】
高校生が読書感想文に取り組むとき、本選びはとても大切です。
ただ「読んだことがあるから」「友達にすすめられたから」などの理由だけで選んでしまうと、感想文に深みが出なかったり、最後まで読めなかったりすることも。
この記事では、感想文に適した本の選び方を3つの視点から紹介します。
- 感情が動く瞬間があるか
- 自分の悩みや関心とリンクしているか
- 読みやすく考えさせられる古典かどうか
自分に合った一冊を見つけることで、読む楽しさも、書くときの言葉も自然と湧いてくるはずです。
感情が揺さぶられる本は感想が書きやすい
読書感想文を書くうえで一番のヒントになるのが「感情の動き」です。
読み進める中で「びっくりした」「切なくなった」「怒りを覚えた」など、自分の心が反応した瞬間があると、それを起点に感想が広がっていきます。
逆に、何も感じなかった本では感想が出てこず、あらすじの羅列になりがちです。
たとえば、社会問題を扱った本で「自分ならどうする?」と考えさせられた場面、青春小説で「自分の高校生活と似てる!」と共感したシーンなど、心が動いた瞬間こそ感想文に最もふさわしい材料です。
「自分ごと化」できるテーマを持つ作品を選ぼう
読書感想文は「その本と自分との距離感」が問われる課題ともいえます。
どんなに名作であっても、「自分には関係ない」と思いながら読むと、感想もどこか他人事のようになってしまいます。
そこでおすすめなのが、「いまの自分の悩み」や「関心ごと」とリンクするテーマの本を選ぶこと。
たとえば「将来が不安」「人間関係で悩んでいる」「夢が見つからない」といった高校生に多い気持ちを扱った作品を選べば、自然と自分の言葉で書けるようになります。

「答えがない問い」に向き合う本も、思考の深さをアピールできるチャンスです。
難解すぎない“読ませる古典”も狙い目
感想文と聞くと「最近の話題作が有利」と思われがちですが、実は古典文学や名作小説にも“書きやすい”作品は数多く存在します。
特に、100年以上読み継がれてきた作品には、人の心や生き方に関する普遍的なテーマが詰まっています。
たとえば、夏目漱石の『こころ』やヘッセの『車輪の下』などは、高校生でも十分に読める文体でありながら、人間の弱さや孤独、葛藤といった深いテーマを描いています。
ただし、抽象的すぎる作品や、難解な哲学書などは避けるのが無難です。
読みやすく、それでいて「考える余地のある古典」を選ぶのがコツです。
読書感想文におすすめの本【テーマ別20選】
読書感想文を書くなら、自分が興味を持てるテーマの本を選ぶことが近道です。
「感情が動いた」「考えさせられた」「知らない世界を知った」——そんな本との出会いが、感想文をもっと豊かにしてくれます。
ここでは、高校生に人気の高いテーマごとに、感想が書きやすく、かつ内容も充実しているおすすめ本を紹介します。
どのジャンルから読んでも、きっと「書きたいこと」が見つかるはずです。
| タイトル | 著者 | ジャンル |
|---|---|---|
| ぼくは勉強ができない | 山田詠美 | 青春・共感 |
| ライオンのおやつ | 小川糸 | 青春・共感 |
| そして、バトンは渡された | 瀬尾まいこ | 青春・共感 |
| 2.43 清陰高校男子バレー部 | 壁井ユカコ | 青春・共感 |
| 手紙 | 東野圭吾 | 社会問題・ヒューマン |
| 塩狩峠 | 三浦綾子 | 社会問題・宗教 |
| 暗幕のゲルニカ | 原田マハ | 社会問題・戦争 |
| クライマーズ・ハイ | 横山秀夫 | 社会問題・報道 |
| コンビニ人間 | 村田沙耶香 | 社会問題・現代社会 |
| 白ゆき姫殺人事件 | 湊かなえ | 社会問題・メディア |
| NASAより宇宙に近い町工場 | 植松努 | ノンフィクション・実話 |
| 進化しすぎた脳 | 池谷裕二 | ノンフィクション・科学対話 |
| 深夜特急 | 沢木耕太郎 | ノンフィクション・紀行 |
| 高校生からわかるイスラム世界 | 池上彰 | ノンフィクション・時事 |
| 不可能を可能にする 大谷翔平120の思考 | 大谷翔平 | ノンフィクション・自己啓発 |
| 月と六ペンス | サマセット・モーム | 哲学・芸術 |
| クララとお日さま | カズオ・イシグロ | SF・哲学 |
| 高校生からのゲーム理論 | 松井彰彦 | 科学・経済 |
| ソクラテスの弁明/クリトン | プラトン | 哲学・古典 |
| 敦煌 | 井上靖 | 歴史・思想 |
| ナミヤ雑貨店の奇蹟 | 東野圭吾 | ファンタジー・ヒューマン |
| 放課後 | 東野圭吾 | ミステリー・青春 |
| 車輪の下 | ヘルマン・ヘッセ | 象徴文学・青年成長 |
共感や青春を描く小説で「自分と重ねる」
成長、友情、恋愛、家族——青春時代ならではのテーマは、読者の心をつかみやすく、感想も自然と湧いてきます。
たとえば『ぼくは勉強ができない』(山田詠美)は、成績には恵まれないけれど人間的な魅力にあふれた主人公を描き、多くの高校生が共感できる物語。
『2.43 清陰高校男子バレー部』のように、部活に打ち込む姿をリアルに描いた作品も、学校生活と重ねやすいです。
「登場人物と自分の違い」や「もし自分だったらどうするか」といった視点で書くと、読み手の心にも届く感想文になります。
【説明】ぼくは確かに成績が悪いよ。でも、勉強よりも素敵で大切なことがいっぱいあると思うんだー。17歳の時田秀美くんは、サッカー好きの高校生。勉強はできないが、女性にはよくもてる。ショット・バーで働く年上の桃子さんと熱愛中だ。母親と祖父は秀美に理解があるけれど、学校はどこか居心地が悪いのだ。この窮屈さはいったい何なんだ!凛々しい秀美が活躍する元気溌刺な高校生小説。

「ぼくは勉強ができない」は、型にはまらない主人公・時田秀美の言葉に、なぜか心を掴まれる一冊。“勉強ができる・できない”の枠を超えて、自分の価値観や「生きるってなんだろう?」を問いかけてくれる物語。思春期に読むと反発するかもしれない。でも、時が経つほどにじわじわ効いてくる青春小説です。
【説明】田舎の弱小バレーボール部に、東京の強豪校出身のワケあり選手がやってきた。全国を目指す熱い日々が始まるが…。迷い、傷つき、立ち上がる等身大の青春スポーツ小説。

バレーを“好き”でいる気持ちだけで、どこまで行けるのか――。『2.43』は、等身大の悩みや挫折を抱えた少年たちが、それでもネットの向こうを目指して飛ぶ物語。勝てなくても、迷っても、不器用でも、まっすぐな想いが胸を打つ。青春って、こういうことだと思う。
社会問題を深掘る名作で「考察」を加える
「いまの社会とどう向き合うか」は、大人にも通じる深いテーマです。
『手紙』(東野圭吾)では犯罪者の家族が背負う現実を、『暗幕のゲルニカ』(原田マハ)では戦争と芸術の関係を描いています。
また、海外作品では『月と六ペンス』が「自分の人生をどう生きるか」という強烈なメッセージを投げかけてきます。
社会問題を扱った作品は、単なる「感想」ではなく、自分の意見や立場を論理的に述べる練習にもなります。
ニュースや現実の社会と関連づけて、自分の言葉で「考察」を加えるのがポイントです。
強盗殺人の罪で服役中の兄、剛志。弟・直貴のもとには、獄中から月に一度、手紙が届く…。しかし、進学、恋愛、就職と、直貴が幸せをつかもうとするたびに、「強盗殺人犯の弟」という運命が立ちはだかる苛酷な現実。人の絆とは何か。いつか罪は償えるのだろうか。犯罪加害者の家族を真正面から描き切り、感動を呼んだ不朽の名作。

犯罪加害者の家族として生きることの重さと孤独が、痛いほど胸に響く物語。直貴の苦しみがまるで自分のことのように迫ってきて、何度読んでも涙が止まりません。“それでも生きていく”という静かな希望に、読み終えたあともしばらく動けなくなる。
ニューヨーク、国連本部。イラク攻撃を宣言する米国務長官の背後から、「ゲルニカ」のタペストリーが消えた。MoMAのキュレーター八神瑶子はピカソの名画を巡る陰謀に巻き込まれていく。故国スペイン内戦下に創造した衝撃作に、世紀の画家は何を託したか。ピカソの恋人で写真家のドラ・マールが生きた過去と、瑶子が生きる現代との交錯の中で辿り着く一つの真実。怒涛のアートサスペンス!

美術の知識がなくても、ピカソの《ゲルニカ》がぐっと近づいてくる。歴史と芸術、そして“今”の世界が交差する原田マハさんの筆致に、思わず息をのみました。これは「芸術は何のためにあるのか?」を改めて問いかけてくる、静かで力強い一冊です。
新進作家の「私」は、知り合いのストリックランド夫人が催した晩餐会で株式仲買人をしている彼女の夫を紹介される。特別な印象のない人物だったが、ある日突然、女とパリへ出奔したという噂を聞く。夫人の依頼により、海を渡って彼を見つけ出しはしたのだが…。

破天荒な画家の人生を描きながら、芸術とは何か、人間の「業」とは何かを問いかけてくる一冊。読みやすく、それでいて読後にずっしり残るのは、訳文の巧みさとモームの洞察力ゆえでしょう。「なぜ生きるか」より「どう生きるか」に惹かれる高校生にこそ、じっくり味わってほしい作品です。
ノンフィクション・実話で「感銘」を与える
実話をもとにした物語には、フィクションでは味わえない「現実の重み」があります。
『NASAより宇宙に近い町工場』(植松努)は、夢に向かって挑戦する町工場の物語。『クライマーズ・ハイ』(横山秀夫)は、日航機墜落事故を取材した記者の視点から描かれるリアルな報道の裏側。
これらは実在の人物や出来事を通じて、「自分はこれからどう生きたいか」「どんなことに力を尽くしたいか」を深く考えるきっかけになります。
読書感想文では、著者や登場人物から受けた影響を率直に書くことが、強いメッセージにつながります。
「日本一感動する講演会」と呼ばれている講演が本になりました。北海道赤平市という小さな町で小さな工場を営みつつ、宇宙ロケット開発に情熱を注ぐ著者が、本業もロケット開発も成功させている自らの体験を通して「みんなが夢を持ち、工夫をして『よりよく』を求める社会をつくること」を提唱します。感動と勇気を与えてくれる一冊です。

「どうせ無理」と言われてきたすべての人へ――。
植松さんの言葉は、夢をあきらめかけた心に静かに火を灯してくれる。
小学生にも大人にも、人生のどこかで必ず出会ってほしい一冊です。
1985年、御巣鷹山に未曾有の航空機事故発生。衝立岩登攀を予定していた地元紙の遊軍記者、悠木和雅が全権デスクに任命される。一方、共に登る予定だった同僚は病院に搬送されていた。組織の相剋、親子の葛藤、同僚の謎めいた言葉、報道とはー。あらゆる場面で己を試され篩に掛けられる、著者渾身の傑作長編。

記者として、男として、どう生きるか。日航機墜落事故という現実を背景に、人間の本質に迫る重厚な一作です。「書くこと」の覚悟を問われるような、読む者の胸にも深く刺さる物語。正義と感情の狭間で揺れる主人公の葛藤に、思わず息を呑みます。
科学・未来・哲学を扱う本で「知的好奇心」を刺激
読書感想文は、文学だけがテーマではありません。
『進化しすぎた脳』(池谷裕二)は、高校生にもわかる言葉で最先端の脳科学を語ってくれる名著。
『高校生からわかるイスラム世界』(池上彰)や『高校生からのゲーム理論』(松井彰彦)のような教養系の新書も、好奇心旺盛な高校生にぴったりです。
「知らなかった世界を知る驚き」や「もっと深く学びたいと思った理由」を素直に書けば、読書感想文としても読みごたえのある内容になります。
知識をただまとめるのではなく、自分の中の「変化」に注目して書いてみましょう。
『記憶力を強くする』で鮮烈デビューした著者が大脳生理学の最先端の知識を駆使して、記憶のメカニズムから、意識の問題まで中高生を相手に縦横無尽に語り尽くす。「私自身が高校生の頃にこんな講義を受けていたら、きっと人生が変わっていたのではないか?」と、著者自らが語る珠玉の名講義。

「記憶」「感情」「自由意志」――そのすべてが脳の“しくみ”から解き明かされる。
高校生との対話形式で語られる脳科学は、驚くほどわかりやすく、ぐいぐい引き込まれます。読むうちに、自分の思考も感情もすべて“脳のシミュレーション”なのかも…と思えてくる一冊。ちょっと怖くて、でもとびきり面白い“知の冒険”です。
社会科学を塗り替えつつあるゲーム理論は、「人と人のつながりに根ざした理論」である。環境問題、三国志、恋愛、いじめなど、多様なテーマからその本質に迫る入門書。

チキンレースや囚人のジレンマ――複雑な人間関係も“戦略”で読み解ける?本書は、ゲーム理論という難解なテーマを高校生にもわかりやすく届けてくれる入門書です。いじめ、経済、国際問題まで、すべては“選択と結果”の繰り返し。考えることの面白さを再発見できる、知的興奮に満ちた一冊です。
物語の世界観に浸れるファンタジーで「感性」を磨く
現実とは少し離れた世界に触れたいなら、ファンタジー作品がおすすめです。
たとえば『ナミヤ雑貨店の奇蹟』(東野圭吾)は、ミステリーにファンタジー要素が加わった不思議で感動的な物語。
『クララとお日さま』(カズオ・イシグロ)は、AIの視点から人間を描くSF小説で、想像力と哲学的な問いが交差します。
こうした作品では、「なぜこの物語に惹かれたのか」「どんな場面で心が動いたか」を丁寧に言葉にすることが大切。
文章力だけでなく、感性や読解力も問われるジャンルですが、自由な発想で書くことができるのも魅力です。
悪事を働いた3人が逃げ込んだ古い家。そこはかつて悩み相談を請け負っていた雑貨店だった。廃業しているはずの店内に、突然シャッターの郵便口から悩み相談の手紙が落ちてきた。時空を超えて過去から投函されたのか?3人は戸惑いながらも当時の店主・浪矢雄治に代わって返事を書くが…。次第に明らかになる雑貨店の秘密と、ある児童養護施設との関係。悩める人々を救ってきた雑貨店は、最後に再び奇蹟を起こせるか!?

「悩みに答える雑貨店」という不思議な舞台が、心をじんわり温めてくれる。バラバラだったエピソードが、やがてひとつにつながっていく感動の構成に脱帽。ページをめくる手が止まらなくなる優しさと、希望の物語です。人生に迷ったとき、そっと寄り添ってくれる一冊。
クララは子供の成長を手助けするAF(人工親友)として開発された人工知能搭載のロボット。店頭から街行く人々や来店する客を観察しながら、自分を買ってくれる人が来ることを待ち続けている。ある日、ジョジーという病弱な少女の家庭に買い取られ、やがて二人は友情を育んでいくが、一家には大きな秘密があった…愛とは、知性とは、家族とは?根源的な問題に迫る感動作。ノーベル文学賞受賞第一作。

AIロボット・クララの目を通して描かれるのは、人間の“感情”と“孤独”の深淵。純粋な観察者であるクララが見つめる世界は、私たちの弱さや優しさを浮き彫りにしていきます。読むほどに問いかけられるのは、「人間らしさ」とは何かという根源的なテーマ。静かで切ない、でも確かな“光”を感じる近未来寓話です。
読書感想文を書くうえで意識したい3つの視点
どんなに良い本を読んでも、感想文がぼんやりしてしまうのはもったいない。
ここでは、高校生ならではの「書き方の視点」を具体的に解説します。文章に説得力と深みを持たせるためのヒントとして、3つの視点を紹介します。
主人公の選択を「自分ならどうするか」で掘り下げる
感想文の中で「主人公の行動」や「物語中の重要な選択」に注目するのは非常に効果的です。
ただ単に「すごいと思った」「かわいそうだと思った」ではなく、「もし自分だったら同じ選択ができたか?」と問いかけてみてください。
たとえば、主人公が困難に立ち向かう場面や、人間関係で悩む場面など、読んでいて印象的だったシーンを選び、その背景や気持ちを想像する。
そして「自分ならどうするか」を書くことで、読者はその本を“あなたの視点”から再体験できます。
こうした「自分との対話」は、ありきたりな感想文から一歩抜け出す大きな要素になります。書き手の人柄が伝わる文章は、読む人の心にも響きます。
「なぜこの本を選んだのか」を軸にすると説得力が増す
読書感想文を書くとき、多くの人が内容や感想から書き始めがちですが、実は「なぜこの本を選んだのか」という部分にも大きな意味があります。
選んだ理由が明確になると、その後に続く感想にも一貫性が生まれ、文章全体に説得力が加わります。
たとえば、「表紙が印象的だった」「過去に読んだ著者の作品が良かった」「テーマが自分の興味と重なっていた」など、きっかけは小さくても大丈夫です。
そのきっかけが、読み進める中でどう変化したのか、最初の期待に対してどんな気づきがあったのか、そういった流れを丁寧に書くと、読み応えのある文章になります。
この視点は、書き手自身の「選書力」や「読書姿勢」を伝える意味でも大切です。
「読後の変化」を明確にすることで深みが出る
感想文に最も大切なのは「何を感じたか」ですが、それをより具体的に表現するためには「読後、自分にどんな変化があったか」に注目するのがポイントです。
たとえば、「当たり前だと思っていたことを見直すきっかけになった」「家族との関係を考え直した」「もっと知りたいと思うテーマが見つかった」など、小さな変化でも構いません。
それを具体的に言語化することで、読み手に伝わる力が一気に増します。
さらに、「この本を読んでから、〇〇について調べてみた」や「友人にこの話をしてみた」など、行動に移したことがあれば、それも書いてみましょう。
本との出会いが、あなた自身にどんな影響を与えたのか。
それを丁寧に描けたとき、読書感想文は単なる「感想」を超えた、あなた自身の成長記録にもなります。
本選びのよくある悩みとその解決法
高校生や保護者からよくある「本が決まらない」「読んでも感想が出てこない」などの声に、具体的なアドバイスを添えて解決策を提案します。
読書感想文の第一歩は、心から「読んでみたい」と思える本と出会うこと。そんな出会い方を一緒に考えてみましょう。
読み始めたけど合わなかった…→迷ったときのチェンジ法
「数ページ読んだけど、全然入ってこない…」そんな経験は誰にでもあります。
本を変えるなんて“逃げ”と思われがちですが、実はとても大事な判断です。
無理して読み続けるよりも、「今の自分に合わなかっただけ」と気持ちを切り替えることの方が、ずっと健全です。
チェンジする際のポイントは、「なぜ合わなかったのか」を自分なりに分析してみること。
「登場人物に共感できなかった」「文章が堅苦しすぎた」など、感じたことを言葉にすると次に選ぶ本のヒントになります。
もし読書感想文のために選んだ本なら「最初の3章まで読んで判断する」など、自分なりのルールを作るのもおすすめです。
「途中で変えること」は失敗ではなく、より良い本との出会いの一歩になるはずです。
図書室の定番ばかりで新鮮味がない…→話題の本から探すコツ
「図書室の本って、なんだか“昔からある感”が強くて、どれも読んだことある気がする…」という声、実は多いです。
特に高校生になると、感性が成熟し、より“自分らしい”選書を求めるようになります。
そんな時は、今話題になっている本から探してみるのが効果的です。
方法としては、SNSや読書系のYouTube、出版社の「10代におすすめ特集」などを活用するのが◎。
読書感想文の定番ジャンルである「青春」「社会問題」「実話」などに絞って検索すれば、意外な発見があるかもしれません。
また、受賞歴のある作品も狙い目です。
「本屋大賞」「高校生直木賞」など、若い世代の読者が支持した本には、共感できる要素が多く詰まっています。
話題性と読みやすさのバランスがとれた一冊に出会える可能性が高いです。
課題図書は興味がわかない…→自由選書の魅力を活かそう
「課題図書はどうも堅苦しくて興味が持てない…」「読む前から“お勉強感”があって気が乗らない…」そんな声もよく聞かれます。
もちろん、学校の指定で課題図書が必須の場合もありますが、多くのケースでは“課題図書以外でもOK”という学校も増えています。
そうした場合は、自由選書を遠慮なく活用しましょう。
自由選書の魅力は、自分の関心や経験に沿った本を選べる点にあります。
たとえば、「音楽が好きだからミュージシャンの自伝を読む」「環境問題に関心があるからノンフィクションを選ぶ」といったアプローチです。
さらに、自由選書では「自分の興味」と「本の内容」が重なっているため、感想が自然と湧いてきやすくなります。
「なぜこの本を選んだか」から書き始めることで、感想文にもオリジナリティが出ますよ。
まとめ
高校生が読書感想文を書くうえで大切なのは「どんな本を選ぶか」だけでなく、「どう読むか」「どう書くか」にも意識を向けることです。
自分の感情や経験と重ねながら読める本に出会えれば、感想文はぐっと書きやすくなります。
最初はピンと来なくても、少しずつ視点を変えてみれば、自分にしっくりくる一冊がきっと見つかるはずです。
読書感想文は「正解を書く」ものではありません。
あなた自身の感じたことや、心に残った場面を丁寧に言葉にしていけば、それが誰かの心にも届く文章になります。
今回の記事をきっかけに、本との出会いがより豊かで実りあるものになることを願っています。
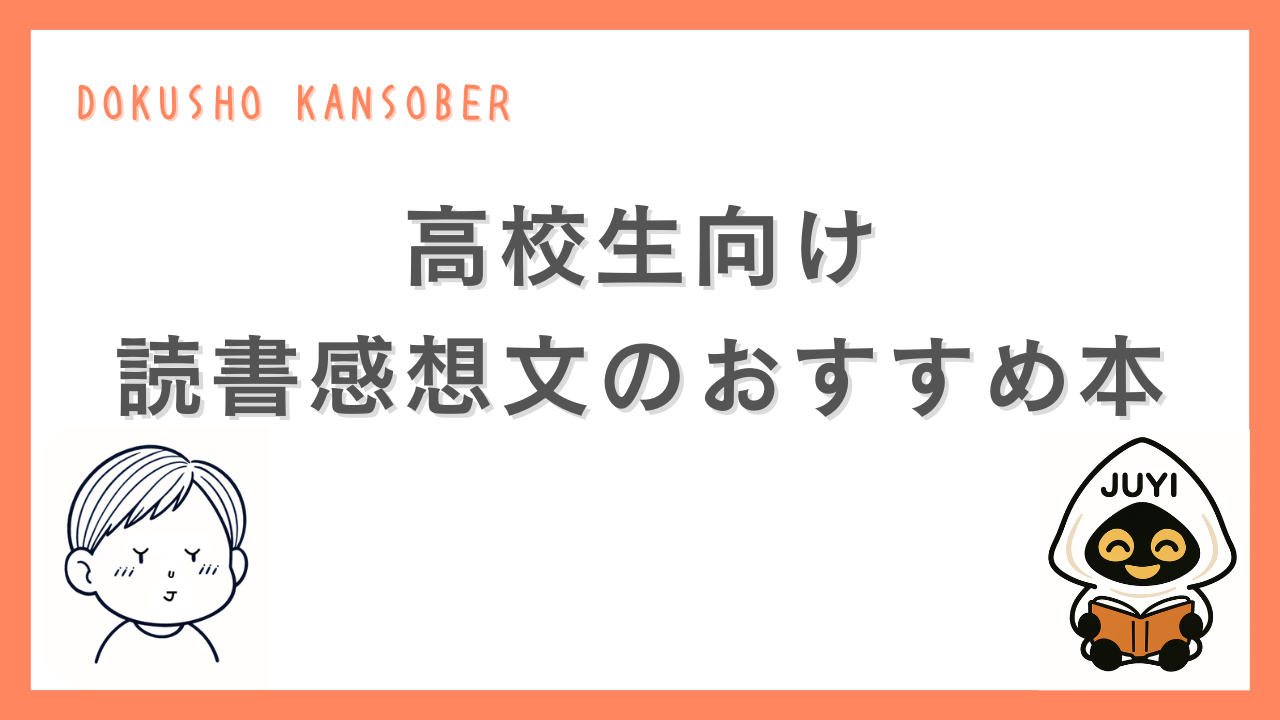
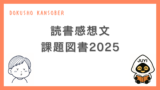












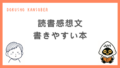
コメント