「どの本を選べば、読書感想文が書きやすくなるの?」
そんな悩みを持つ小学生の保護者の方へ向けて、本記事では「本の選び方」と「学年別おすすめ作品」、そして感想文を書くための具体的な工夫を紹介します。
ただ有名な本を並べるのではなく、“感動・共感・考察しやすいか”という視点からセレクト。
親子で一緒に本を選び、感想を語り合う――そんな体験を通じて、読書がもっと楽しくなるヒントが詰まっています。

2025年の読書感想文~課題図書~は下記にまとめてあるので参考にしてください。
読書感想文に向いている本の選び方とは?
読書感想文を書くとき、本の選び方ひとつで「書きやすさ」は大きく変わります。
特に小学生の場合は、まだ語彙力や構成力が十分ではないことも多いため、「感想が自然に出てくる本」を選ぶことがとても大切です。
ここでは、読書感想文にぴったりな本を選ぶための3つの視点をご紹介します。
感動・共感・考察できる本かどうか
登場人物に共感したり、自分の体験と重ねられることで、感想が自然と浮かびやすくなります。
ジャンルよりも“読後感”を重視すること
感想文に必要なのは「何を感じたか」。名作や人気作よりも、「読んだあとに心に残るかどうか」がポイントです。
親子で一緒に選ぶこと
保護者が一緒に選ぶことで、お子さんの関心に寄り添った本選びができ、感想も引き出しやすくなります。
選ぶポイントさえ押さえれば、お子さんが自分の言葉でのびのびと感想をつづることができるようになりますよ。
また、保護者の方が一緒に選ぶことで、子ども自身が本に親しみをもちやすくなり、感想文への意欲も高まります。
作文が苦手なお子さんにも役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。
感動・共感・考察できる本を選ぶのがコツ
読書感想文で大切なのは「感じたことを言葉にできるかどうか」です。
そのためには、ストーリーに心が動かされることが前提になります。
たとえば、登場人物の気持ちに共感できたり、自分の経験と重なる場面があったりすると、自然と「このとき自分だったら…」「なんでこうなったんだろう?」と考えるようになります。
そうした気持ちや問いかけが、感想文の核になります。
逆に、どんなに名作でも、お子さんの興味関心とかけ離れていたり、登場人物の心情が理解しにくかったりすると、感想が書きにくくなってしまいます。
選書のコツとしては、「感動できた!」「この登場人物の気持ちがわかる!」「この話の意味を考えてみたい!」と思えるような本を選ぶこと。
読後に何か心に残る“余韻”があるかどうかを目安にしましょう。
「ジャンル」よりも「読後感」で選ぼう
読書感想文に向く本というと、「名作」や「感動もの」「冒険ファンタジー」などのジャンルで選びがちですが、実はそれだけでは不十分です。
ジャンルで分類された本のなかにも、感想を書きやすいものと書きにくいものが混在しています。
たとえば、同じファンタジーでも「設定が複雑すぎて話についていけない」ような本だと、子どもはストーリーを追うのに精一杯で、感想を書く余裕がなくなってしまいます。
一方、リアルな日常を描いた物語でも、「自分の学校生活と重なる」「登場人物の悩みに共感できる」など、深く感情移入できれば感想はスラスラと出てきます。
つまり、感想文においては“どんなジャンルか”よりも“どんな気持ちが残ったか”が大切です。
「読んだあとに何かを感じた」「考えさせられた」そんな“読後感”を重視して選ぶことで、お子さんにとって書きやすい1冊が見つかるはずです。
親子で一緒に選ぶことで、作文のヒントも得られる
「どの本を選んだらいいの?」と悩んでいるときこそ、親子で一緒に選ぶチャンスです。
お子さんが今どんなことに興味をもっているのか、何に心を動かされるのかを知る機会にもなります。
たとえば書店や図書館で、「どれが気になる?」「これは面白そうだと思う?」と声をかけながら一緒に本を選んでみましょう。
このとき、あえて自分が読んだことのない本を選ぶのもポイントです。
読み終わったあとに「どんな話だったの?」「どう思った?」と聞くことで、子どもの感情が言葉になりやすくなります。
実際に親子で感想を話し合う中で、「あのセリフが印象に残った」「なんでこうなったんだろう?」といった会話が生まれ、作文の材料が自然と集まっていくケースもよくあります。
親が先回りして「この本がいい」と決めるのではなく、一緒に選び、一緒に感じること。

それが感想文づくりにおいて、いちばんの近道かもしれません。
小学生に人気の本から選ぶ【学年別おすすめ】
本選びの最大のポイントは「お子さんが無理なく読み進められること」。
読書感想文では、物語をしっかり理解し、心が動いた経験を言葉にする必要があります。そのためには、まず「読めた」という成功体験がとても大切です。
ここでは、小学1〜6年生を3つの学年帯に分け、それぞれに合った本を厳選して紹介します。
選定基準は「文字量・言葉のやさしさ・ストーリーの理解しやすさ・感情の動きやすさ」の4点。そして、読書感想文に落とし込みやすいかどうかも重視しました。
本好きなお子さんはもちろん、普段あまり本を読まないお子さんでも取り組みやすいラインナップになっています。
小学1〜2年生におすすめの読書感想文向け本3選
1年生・2年生では、文章量が少なめで、絵や余白が多い本が理想的です。
お話の内容がシンプルでも、子どもが共感しやすいテーマが含まれていると、自然に感想が出てきます。
【説明】ある朝、テキトーさんは目覚まし時計の音で目をさましました。けれど、なぜだかもう遅刻の時間です。それでもテキトーさんは「ま、いっか!」。次から次へと失敗を繰り返すテキトーさん。「ま、いっか!」とやり過ごしていくうちに思いもよらない場所にたどり着いて…。

「うまくいかないことがあっても、“ま、いっか”って思えることも大事なんだよ」と教えてくれる絵本。小さな失敗を笑って受け入れる主人公の姿に、親子でクスッとしながら温かい気持ちになれます。
【説明】大好きなおばあちゃんと、少しの間いっしょに暮らすことになったはなちゃん。優しいおばあちゃんと過ごす時間はとても楽しかったけれど、いつもと違う生活にだんだんもやもやがたまってきて…。「おばあちゃんなんて、きらい!」と言ってしまったはなちゃんは、「ごめんね」が言えるのでしょうか。

おばあちゃんとの生活の中で起きる“もやもや”と、言ってしまった「ひどい一言」。謝ることの難しさと大切さを丁寧に描いた作品で、小さな心の動きを感想にしやすい一冊です。
【説明】幼なじみのかおるに背中を押され、プールが苦手な「ぼく」が水泳大会を目指してクロールに挑戦する物語。少しずつできることが増えていく中で、努力することの大切さを学んでいく。運動が苦手な子にも寄り添った、成長と友情のストーリー。

水泳が苦手な主人公が、練習を通じて前向きになる物語。運動が苦手なお子さんにも響く内容で、「がんばるって気持ち、ちょっとわかったかも」と素直に書けるテーマです。
小学3〜4年生におすすめの読書感想文向け本3選
中学年になると、少し長めの物語にも挑戦できるようになります。
この時期は「自分だったらどうする?」「登場人物の気持ちがわかる」など、心の動きに注目して感想が書けるようになってきます。
【説明】たいくつなアリスの前を「たいへん! たいへん! 」といいながら、白ウサギが走っていきます。ウサギを追いかけ、いっしょにあなの中へ。そこは、ありえないおかしなことが次々に起こるふしぎなふしぎな世界でした!

言わずと知れた名作ですが、イラスト付きの児童版は読みやすく、自由な発想や「夢の世界」をテーマにした感想文が書きやすいのが特徴です。
【説明】どうしても捨てられないもの、守りたいもの、そして遠ざけたいもの。そんなお品がございましたら「十年屋」の時の魔法をご用命ください。小さなころからずっと大事にしていたぬいぐるみ、大好きなひとからもらった写真、会えなくなった友だちに見せたかった雪だるま。忘れたくても忘れられない大切なもの、思い出と一緒に、魔法でお預かりします――。

思い出と一緒に大切なものを預かってくれる「十年屋」。不思議な世界観と心温まるストーリーで、「自分だったら何を預けたいか」など、自分に引きつけた感想が書きやすい作品です。
【説明】おなじみズッコケ三人組が、お弁当会社を設立した。会社は順調にすべりだしたかにみえたが……。さて、三人の努力はむくわれるか?

ズッコケ三人組が会社を作ってお金を集める!というユニークな設定で、子どもでも“ビジネス”の面白さを感じられます。楽しく読めて、感想にも個性が出せる作品です。
小学5〜6年生におすすめの読書感想文向け本3選
高学年になると、長編にもチャレンジできる読解力がついてきます。
感情の機微や社会的なテーマにも関心が向く時期なので、「生き方」「時間」「命」など深いテーマにふれる本を選ぶのもおすすめです。
【説明】不世出の児童文学作家、松谷みよ子がつづる、戦争、そして原爆と子どもたちの、今なお新しい物語。

戦争の記憶と不思議な椅子の物語が交錯する、心に残るファンタジー作品。子どもの視点で進むストーリーの中に、原爆や家族の喪失が静かに描かれており、読後に「平和とは?」「記憶とは?」と深く考えさせられます。怖さや切なさもあるけれど、感想文にしやすい問いが自然に生まれる1冊です。
トットちゃんがユニークな教育のトモエ学園で、友達とのびのび成長していく自伝的物語。深い愛情で子どもたちの個性を伸ばしていった校長先生が、トットちゃんに言い続けた言葉「きみは、本当は、いい子なんだよ」は、今も黒柳徹子さんの宝物です。

実話ベースの物語で、子どもの個性を受け入れる学校が舞台。感情移入しやすく、自分と比べて感じたことを素直に書きやすい作品。トットちゃんの自由な発想に励まされる子も多いはずです。
【説明】多くの伝記では「英雄」「成功者」として紹介されている、いわゆる偉人たち。
でも、彼らは、ずっと成功し続けてきたわけではありません。今に名を残すすごい人も、たくさん失敗をしてきました。だから、「失敗しないと人生損だよ! 」くらいの気持ちでどんどん新しいことにチャレンジしてほしい。そのための「勇気の書」が本書です。「最近新しいこと試してなくてつまらないな」と感じている大人の方にもおすすめです。

偉人たちの“失敗エピソード”を集めた一冊。「失敗しても大丈夫」「最初から完璧じゃなくていい」という前向きなメッセージが込められており、感想文でも「自分も頑張りたい」といった視点で書きやすいです。
テーマ別に選ぶ!感想文が書きやすい本
本の選び方にはいろいろなアプローチがありますが、「テーマ別」で考えると、感想文を書きやすいかどうかがぐっと明確になります。
「この話を読んで、自分はどう感じたのか」「登場人物に共感したのか」「なぜそう思ったのか」といった感情や思考が自然に引き出されるのは、そのテーマが子ども自身に近いときです。
ここでは、感情を揺さぶる【感動系】、楽しく読める【ユーモア系】、深く考えさせられる【ノンフィクション】の3つの切り口から、読書感想文に向いた本をご紹介します。
ジューイ独自の視点で、感想にしやすいポイントも添えてお届けします。
感動できる物語ならこれ!心が揺れる作品3選
【説明】母はその子犬を見て「犬を飼う時には、犬と10の約束をして」と幼いあかりに約束をさせた。「1.私と気長につきあってください。」「2.私を信じてください。それだけで私は幸せです。」(中略)「10.私が死ぬとき、お願いです、そばにいてください。どうか覚えていてください、私がずっとあなたを愛していたことを。」犬と人の触れ合いを描いた感動作!

命の大切さ、動物との絆、家族のつながりなど、読んだあとにじんわりとした余韻が残る物語。ペットを飼っている子はもちろん、動物と関わる経験のある子なら感情移入しやすく、感想も書きやすいです。
【説明】年取ったのらねこからどうぶつ島に囚われているりゅうの子どもの話を聞いたエルマーは、りゅうの子どもを助ける冒険の旅に出発します。どうぶつ島ではライオン、トラ、サイなど恐ろしい動物たちが待ちうけていました。エルマーは、知恵と勇気で出発前にリュックにつめた輪ゴムやチューインガム、歯ブラシをつかって、次々と動物たちをやりこめていきます。エルマーはりゅうの子どもを助け出すことができるのでしょうか?

冒険ファンタジーですが、単なる「冒険もの」ではありません。勇気を持って行動する主人公の姿に、小学生が「ぼく(わたし)だったらどうするかな?」と自然に考えるきっかけになります。感動というより、心に火をつけてくれるタイプの本。
じいちゃんと孫の絆を描き出したお話です。この絵本のキーワードは「ごくらく(極楽)」。おじいちゃんとの楽しい時間、やがて訪れる死。二つのまったく異なる場面を、このキーワードが結びつけます。登場人物の心情が切々と伝わってくる文章、表情豊かな絵。心揺さぶる一冊です。

死をテーマにした絵本で、小学生でも理解できるやさしい表現で描かれています。大切な人との別れに触れたことがある子なら、心に強く残る作品。「命」や「ありがとう」を素直に言葉にしたくなる一冊です。
ちょっと笑えるユーモア系で楽しく書ける本3選
【説明】年に一度の、町のお祭りに出かけたおしりたんてい。仮装した人びとでいっぱいの会場に着くと、なにやら事件が…。

シリーズとしても有名ですが、事件の謎解きとおしりネタが絶妙にミックスされており、「笑えるのにちゃんと話がある」名作。低学年向けですが、発想が面白く、読後に“好きな場面”を書くタイプの感想にぴったりです。
【説明】ひとり修業の旅にでたゾロリは、あるときお姫さまの花むこにりっこうほすることにしました。そのためにすばらしい計画をたてます。

王道のユーモア作品で、ゾロリのトラブルと知恵、ドジっぷりが子どもに大人気。「ゾロリのように、◯◯してみたい」など、自分なりの視点を持って書く感想が楽しくなります。作文が苦手な子にもおすすめ。
【説明】アニメやマンガのできごとを科学的に考えると、どうなるか!?タケコプターが本当にあったら、空を飛べるのか? かめはめ波を撃つには、どうすればいい? アニメやマンガでおなじみの現象を科学的に検証すると、オドロキの結論がみえてくる。とっても笑える理科の本!

科学的なツッコミを交えたギャグ満載の本。「ドラえもんの道具って本当にできるの?」のような話が続き、子どもが夢中になります。楽しさの中に「知らなかった!」があるので、驚きや発見をそのまま感想にできます。
命・生き方・障がいを考えられるノンフィクション3選
【説明】「目の見えない人とアートを見る?」タイトルへの素朴な疑問は、驚きとともに解消されます。白鳥建二さんと現代アートや仏像を鑑賞すると、現れるのはこれまで見えていなかった世界。「白鳥さんと作品を見るとほんとに楽しいよ!」という著者の友人マイティの一言で、「全盲の美術鑑賞者」とアートを巡るユニークな旅は始まりました。視覚の不思議、アートの意味、生きること、障害を持つこと……などが白鳥さんや友人たちとの会話から浮かび上がってきます。

美術館でのアート鑑賞を、視覚障がい者の白鳥さんと共に体験していくノンフィクション。視点を変えることで見える世界の面白さ、違いを認める優しさが学べます。少し長めですが、小学5~6年生におすすめ。
【説明】第二次世界大戦中、ナチ・ドイツの迫害から逃れ、隠れ家での生活をつづった『アンネの日記』の作者、アンネ・フランク。普通の生活を願い、希望にあふれる将来を夢見た彼女がなぜ命を落とさねばならなかったのか。

世界的に有名な実在の少女・アンネの暮らしを、児童向けにわかりやすく描いた漫画版。戦争、自由、命…考えるテーマは深いですが、「自分ならどう感じる?」という視点で感想を書きやすい内容です。
【説明】吃音の悩みを抱え中学生になった悠太。思い切って入部した放送部にいたのは同じクラスの女子で・・・。葛藤と成長の、胸打つ青春物語

吃音に悩む少年の姿に、多くの人が共感し、涙した1冊。「読むのが苦手な子でも感動できた」「感想文で入選できた」など、熱い声多数。子どもに読ませたい、そして大人にも読んでほしい、そんな物語です。
読書感想文がスラスラ書ける3つの工夫
読書感想文に苦手意識を持っている子は少なくありません。
でも、「何を書けばいいか」が見えてくると、思った以上にスラスラ言葉が出てくることもあります。
ここでは、作文がグッと書きやすくなる3つのコツを紹介します。
「好きな場面」→「なぜ?」と考えるだけで深い感想に
まずは「このシーンが好き!」と思った場面を一つ選んでみましょう。
そして、その理由を一緒に考えてみてください。
たとえば、「主人公が勇気を出すシーンが好き」と言ったら、「どうしてそのシーンが印象に残ったの?」と問いかけてみましょう。
そこに、自分の経験と重なった思い出が出てくることもあれば、「うらやましい」「自分も頑張ってみたい」といった気持ちが芽生えることも。
この「なぜ?」という問いかけが、感想文を“あらすじの説明”ではなく“自分のことば”に変えてくれる第一歩です。
親が聞き役になると、自然に言葉が出てくる
感想文は一人で机に向かうより、「話しながら考える」ほうがスムーズに進むことも多いです。
読後すぐに「どこが面白かった?」「登場人物の誰が好きだった?」と軽く会話をしてみてください。
正解を求める必要はありません。むしろ「へぇ〜、そう思ったんだ!」と興味を持って聞くことで、子どもは安心して話せます。
言葉に出すことで思考が整理され、「さっき言ってたこと、書いてみようか?」と文章につなげることができます。
本を読んだあとの5分間が勝負!
本を読み終えた直後は気持ちがいちばん動いているタイミング。
その時にこそ、「思ったこと」をメモするのが効果的です。
・面白かった?
・びっくりしたところは?
・最後どう思った?
こういった簡単な質問で構いません。できれば親子で一緒に「感じたことを言い合う」時間を5分だけ作ってみてください。
その時間が、感想文を書く“種まき”になります。
本を読むのが苦手な子にはどうする?
読書感想文の課題が出ると、「うちの子、本を読むのが苦手で…」と不安になる保護者の方も多いと思います。
ですが、無理に読ませようとする必要はありません。興味を引き出し、自然と読書に近づく工夫をするだけでも十分です。
「短編」「シリーズもの」から入るのがオススメ
いきなり長編や難しいテーマに挑むのではなく、まずは読み切りやすい短編や、親しみやすいシリーズ作品を選んでみてください。
たとえば「かいけつゾロリ」や「おしりたんてい」など、ユーモアたっぷりでテンポのいい作品は、読書が苦手な子でも“最後まで読めた!”という達成感を味わいやすくなります。
シリーズ物なら、「続きが気になる」という感覚から自然と読書量も増え、感想を書くための材料もたくさん手に入ります。
読み聞かせや音声読み上げも効果あり
「読むのは苦手だけど、聞くのは好き」という子も少なくありません。
そんなときは読み聞かせや、音声読み上げサービスの活用がおすすめです。
たとえば【Audible(オーディブル)↗】などを使えば、プロのナレーターが読み上げてくれるため、物語の世界にスッと入り込みやすくなります。
絵本や児童文学の読み上げ作品も多く、通学中や寝る前の時間にも活用できます。
「読書=目で読む」だけでなく、「耳で聞く読書」も立派なインプット。感想文の材料にもなります。
読めなくても責めない。「興味の芽」を大切に
何より大切なのは、“読み切れたかどうか”ではなく、“興味をもてたかどうか”。
途中で飽きてしまっても、「どこまで読んだ?」「そこまでで何が気になった?」と、できたことにフォーカスして声をかけてあげてください。
ときには、読書の入り口として絵本や図鑑、漫画を選んでもOK。
「これ面白そう!」と思える本に出会う経験が、感想文だけでなく、将来の読書習慣にもつながっていきます。
読書感想文の書き方に悩んだときは、以下の記事もあわせてご覧ください。
まとめ
小学生が読書感想文に取り組むうえで、いちばん大切なのは「本との出会い方」です。
内容やページ数ももちろん大事ですが、それ以上に、「この本、ちょっと読んでみたいな」と思える気持ちの芽を大切にしたいところ。
感想文は“作文の宿題”である前に、“本を通して自分の気持ちを見つける体験”でもあります。
親子で一緒に本を選び、読み終わったあとに「どうだった?」「どこが好きだった?」と話す時間。
そのひとときが、読書感想文のヒントになるだけでなく、お子さんの心の中に「本って面白いかも」という感覚を育ててくれるはずです。
無理に読ませるのではなく、寄り添って楽しむ。
そんな読書の時間が、きっと一生の思い出にもなります。

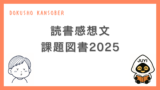




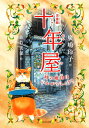
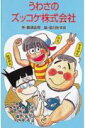
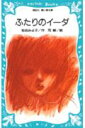
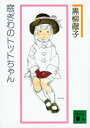












コメント