読書感想文を書くとき、思いのほか迷いやすいのが『「かぎカッコ」』の使い方。
セリフや引用をどう書けばいいのか、原稿用紙ではどこに配置すればいいのか──。
とくに小学生の子どもが清書する場面では、ちょっとしたミスで一から書き直し…なんてことも。
本記事では、読書感想文におけるかぎカッコの正しい使い方を実例を交えて丁寧に解説します。
会話・引用・強調など、カッコが登場する3つの場面を軸に、「原稿用紙で迷わないためのルール」や「清書前のチェックポイント」までしっかりカバー。
「どう書けば読みやすく伝わるのか?」

子どもと一緒に考えながら、表現する楽しさを感じられるヒントをお届けします。
読書感想文で「かぎカッコ」の使い方は意外と悩みがち
読書感想文を書くとき、意外とつまずきやすいのが『かぎカッコ「」』の使い方です。
普段の音読や授業では何気なく目にしている記号でも、いざ自分で原稿用紙に書くとなると、途端に混乱してしまう子どもは多くいます。
特に小学校低学年では、カッコの意味や使い方をまだ十分に理解していないこともあり、保護者がサポートする場面が必要になるでしょう。
会話文や引用、さらには強調のために使うパターンなど、使い方には意味があり、ちょっとした工夫で文章の印象もぐっと変わります。
ぜひ、子どもと一緒に「かぎカッコのコツ」を確認して、読みやすく伝わる感想文づくりに役立ててください。
読書感想文でカッコが登場する3つのシーン
『「かぎカッコ」』が登場する場面は主に3つあります。
「会話」「引用」「強調」
です。
まず「会話」の場合、本の中で登場人物が話しているセリフを感想文の中で紹介する際に使います。
たとえば「『がんばって!』という言葉に、私は元気をもらいました」のように、誰かの発言をそのまま書き写すときには、かぎカッコをつける必要があります。
次に「引用」は、本の中の印象に残った一文や、感想を支える根拠として言葉を抜き出すときに使います。
「私は『あきらめなければ夢は叶う』という言葉に感動しました」といった使い方が典型です。
最後に「強調」は、自分の文章の中で特定の語句を目立たせたいときに使います。
たとえば「私は『努力』という言葉が好きです」のように、自分の言葉であっても目立たせる目的で括弧を使うことがあります。
ただし、強調のための使用はやりすぎないよう注意が必要です。これらの場面を知っておくことで、かぎカッコの使い方に自然と自信がついてきます。
原稿用紙での「かぎカッコ」の基本ルール
かぎカッコは使うだけでなく、原稿用紙のルールに従って“どう書くか”も大切。
まず、始まりのカッコ「は、原則として行頭で1マス空けずに書きます。ただし、段落の最初であれば通常の1字下げをしてから書き始めましょう。
一方で、行末にカッコがきた場合は注意が必要です。
閉じカッコ」が行末にくるときは、原稿用紙の最後のマスに文字と一緒に書いてもOKですが、始まりカッコ「が行末にくるのは避けるのが基本です。
その場合は文の構成を少し調整して、次の行に回すようにしましょう。
また、カッコの中に句点(。)を入れるかどうかもよく迷うポイント。
小学生の読書感想文では、「。」をカッコの中に入れてから閉じるのが一般的な書き方です(例:「ありがとう。」)。
この場合、句点と閉じカッコを同じマスに書くこともできます。
さらに、会話文や引用文が始まるときには改行をするのが一般的ですが、強調など短いフレーズであれば改行せず文中に続けて書いても問題ありません。
大切なのは、一貫したルールで読みやすく仕上げること。
原稿用紙におけるかぎカッコのルールを押さえておけば、清書時のやり直しも防げて、子どもも安心して感想文を書けるようになります。
セリフを生かせば、登場人物の心が伝わる
読書感想文で登場人物のセリフを取り上げると、物語の印象がぐっと深まります。
ただ「おもしろかった」「感動した」と感想だけを書くよりも、具体的なセリフを引用することで、読者にその場面の臨場感や気持ちの変化が伝わりやすくなるからです。
たとえば、「『もう大丈夫。私がいるから』という言葉に、安心した気持ちになりました」といった書き方なら、そのセリフを通して自分の感じたことをよりリアルに伝えられます。
また、子どもにとってセリフは、登場人物と自分を重ねやすいきっかけになります。
悲しいときに「泣いてもいいよ」と言ってもらえた場面、迷っているときに「信じて」と背中を押された場面など、心が動いた瞬間をセリフとともに書くと、自然と気持ちも整理され、感想文に説得力が出てきます。
注意点としては、ただセリフを並べるのではなく「なぜその言葉が心に残ったのか」「自分の体験とどうつながったのか」を書き添えること。
セリフを使うことで、物語と自分自身の間に橋をかけることができるのです。
引用のタイミングと注意点
読書感想文で「引用」をうまく使うと、子どもの感じたことがより具体的に、説得力を持って伝わるようになります。
たとえば、「『一歩ふみだせば、世界が変わる』という言葉に私は勇気をもらいました」といった引用文は、その場面での感情や考えを読み手に共有する手助けをしてくれます。
ただし、引用は「なんとなくいい言葉だから」ではなく、「自分が何を感じたか」とセットで書くことが大切です。
引用するタイミングとしておすすめなのは、「感情が動いた場面」「考えが変わった場面」「自分の経験とつながった場面」です。
特に読書感想文では、「この言葉を読んで、自分もこう思った」という流れが自然で読みやすくなります。
一方で、引用のしすぎには注意が必要です。
あくまで感想文は「自分の意見」を書くものであり、本の内容を丸写しする場ではありません。
引用は“補足”であり、“主役”ではないという意識を持つことが大切です。
また、原稿用紙では引用部分に「」をつけ、必要に応じて改行や1字下げのルールを守るようにしましょう。そうすることで、文章全体の読みやすさも自然とアップします。

引用も合わせて活用すると読書感想文のクオリティが上がりますよ。
子どもと一緒にチェックしたい「清書前の見直しポイント」
原稿用紙での清書は、一度書き始めると簡単には修正できません。
そのため、書き直しのストレスを減らすには、清書前にしっかりと内容を確認し、「かぎカッコ」の使い方も含めた見直しがとても重要です。
特に低学年の子どもにとっては、カッコの位置を1マス間違えるだけで全体を書き直さなければならないケースもあり、大きな負担になります。
清書前に確認したいポイントは、大きく3つあります。
①かぎカッコの前後に必要な改行や1マス空けが適切か
②「。」と閉じカッコが同じマスに収まっているかどうか
③始まりカッコ「が行末にきていないかどうか」です。
この3点をチェックしておくだけで、読みやすさも整い、提出後の印象もぐっと良くなります。
また、保護者の方がそばで声をかけながら進めることで、子ども自身がルールを体感し、次回からの作文にも自信をもって取り組めるようになります。
「一緒にチェックする」ことで、ただの作業ではなく、学びの時間にもなるのです。
間違いやすいパターンとその対処法
かぎカッコの使い方で子どもがつまずきやすいのは、どれも「ほんの1マス」の違いです。
たとえば、始まりカッコ「が行の最後のマスに来てしまう、閉じカッコ」と句点(。)の順番を逆にしてしまう、1マス空けるべきところで詰めて書いてしまう——こうしたミスは、感想文全体のバランスを崩す原因になり、修正も大変です。
特に清書では、「ここでカッコを入れると行が足りない!」という場面も出てきます。
その場合、前の文章の中に「、」を足して文字数を調整したり、短い表現に置き換えるといった工夫で、かぎカッコが変な位置にこないように調整できます。
また、改行のタイミングも要注意。
会話文や長めの引用は改行するのが基本ですが、強調のための短い言葉(例:「努力」など)は改行せず文中に入れた方が読みやすくなります。
子どもが不安そうにしていたら、迷ってもいいこと、間違えても大丈夫だということを伝え、修正の仕方を一緒に考えてあげましょう。
書き直しを恐れるより、「工夫して直せた」という経験こそが力になります。
読書感想文にふさわしい「書きぶり」とは?
読書感想文では、「正しいルール」だけを守っていても、心に残る文章になるとは限りません。
大切なのは、読んだ本を通じて何を感じ、何を考えたのかを“自分の言葉”で書くことです。
特にかぎカッコを使った表現では、「こう書かなきゃ」と型にはめすぎず、子ども自身が大事にしたい言葉を選び、それをどう伝えるかを一緒に考えていくことが重要です。
たとえば、印象に残ったセリフを引用する際、「『あきらめないで』という言葉が心に残りました」で終わらせず、「そのとき私は、転んでも立ち上がったときのことを思い出しました」とつなげると、ぐっと読み手の共感を呼ぶ書きぶりになります。
また、文章全体が「です・ます調」なのに、セリフのあとだけ口語調で違和感がある、といったケースもよくあります。
そうしたズレに気づいて直せるよう、読み返しの習慣をつけるとよいでしょう。
読書感想文は、型に沿って書くことよりも、「その子らしさ」を大切にするほうが、先生にも伝わる内容になります。
見た目の整った清書の先にある、心の通った書きぶりを目指しましょう。
まとめ|「カッコ」を味方につけて、自信のある読書感想文に
読書感想文における『「かぎカッコ」』の使い方は、一見すると些細な技術のように思えるかもしれません。
しかし実際には、登場人物の気持ちや物語のメッセージを的確に伝えるための大切な表現手段です。
正しく使うことで、子どもの感じたことがより深く、よりリアルに読み手に伝わります。
原稿用紙での清書となると、カッコの位置や句点との関係、改行のタイミングなど、意外と細かなルールや判断が求められます。
けれども、その都度「こうすればいいんだね」と親子で一緒に考え、工夫しながら完成させる体験は、作文の技術以上に、子どもの「表現する力」を育てるきっかけになります。
大切なのは、“正しく書くこと”よりも、“伝わるように書くこと”。
セリフや引用を丁寧に選び、「どうしてその言葉にひかれたのか」を自分の気持ちと結びつけて表現できれば、それはもう立派な読書感想文です。
カッコを味方にすれば、子どもたちの言葉がもっと輝き、自信のある一枚が仕上がるはずです。
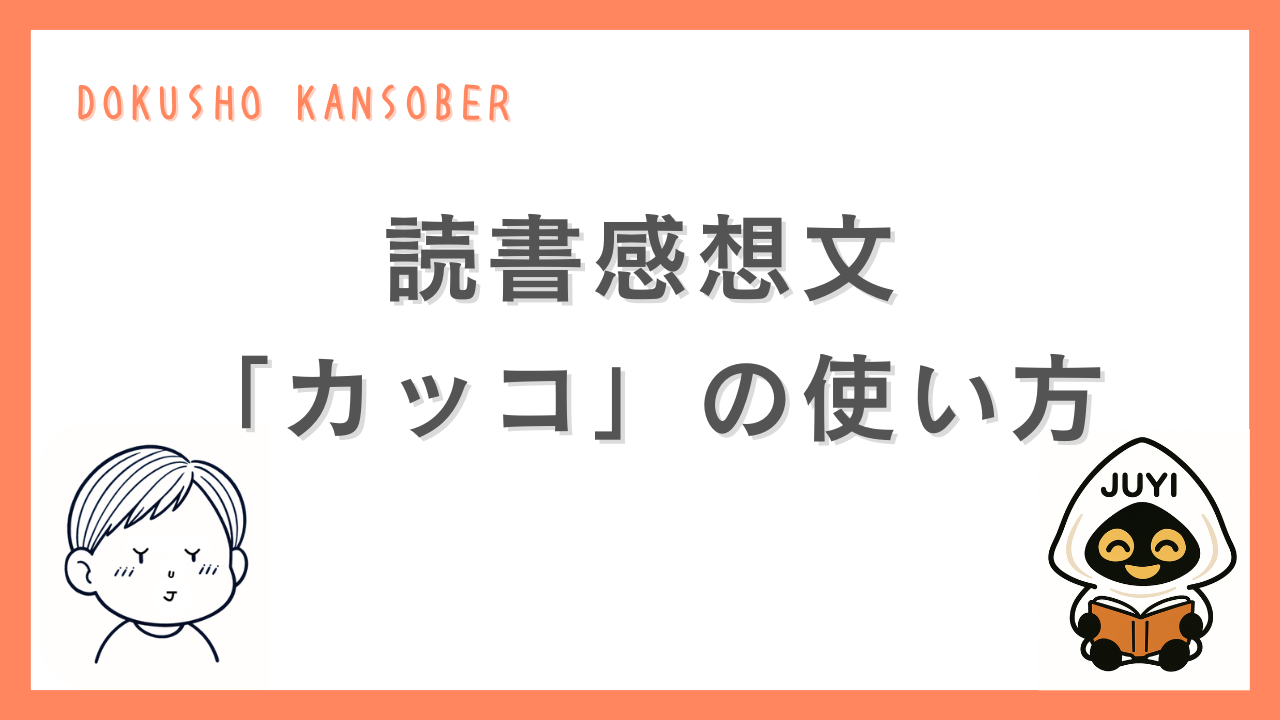
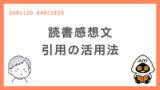
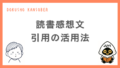

コメント