読書感想文のタイトル、どうやって決めていますか?

「〇〇を読んで」って書けば無難だけど、なんだか物足りない……。
せっかく読んで感じたことがあるのに、それが伝わらないのはもったいないですよね。
この記事では、「評価されるため」じゃなく、自分がワクワクして書きたくなるタイトルの見つけ方を紹介します。
コツはむずかしい言葉を使うことではなく、自分の気持ちに正直になること。
タイトルづけのヒントと、すぐに使える例文もたっぷり紹介しているので、「ピンとくる言葉が見つからない…」という人でも大丈夫。

読み終えるころには、「書いてみたいタイトル」がきっと見つかるはずです。
そのタイトル、ワクワクできる?
読書感想文のタイトルって、「〇〇を読んで」と書けばそれなりにまとまるし、学校でもよく見かける定番の形。でも、それで本当にあなたの伝えたいことが伝わるでしょうか?
読書感想文は、感想を書くもの。つまり、あなたの気持ちや考えが主役です。
タイトルだって同じ。自分の言葉で「こう感じた」「ここが印象に残った」と思える部分を表現するチャンスなんです。
「なんかこのタイトル、ちょっとおもしろそうかも」「自分でも書いてみたいな」と思えるような言葉を、自分で選んでいいんです。
とはいえ、いきなり自由に!と言われても難しいかもしれません。そこで次に紹介するのが、タイトルを考えるときのヒント。

まずは「誰かのためじゃなく、自分が書きたくなるタイトルってどんなもの?」という視点から見ていきましょう。
「自分が書きたくなる」タイトルがいちばん正解
読書感想文のタイトルは、誰かにウケるためのものではなく、自分が「これで書いてみたい!」と思えるものであることが一番大切。
たとえば、「この主人公、私みたい!」と感じたなら、「もし私が〇〇だったら?」というふうに、自分目線の問いかけにしてみてもいいでしょう。
「なんかこの場面、忘れられないな」と思ったら、その感情を素直に言葉にしてみると、自然とあなただけのタイトルになります。
本を読んでワクワクした気持ち、心がざわついた場面、笑ったこと、泣いたこと。そうした感情を思い出して、「それを一番言いたい!」と思う言葉を見つけること。
それが、あなただけの読書感想文の入り口になります。書くのが楽しみになるような、そんなタイトルを、自分のために選んでみてください。
「評価される」より「伝わるか」で考えてみる
読書感想文って、つい「先生にほめられたい」「うまく書かなきゃ」と思ってしまいがち。でも、それがプレッシャーになってしまって、自分の言葉じゃなくなるのはもったいないですよね。
大事なのは、「正解を狙うこと」ではなく、「自分の感じたことがちゃんと伝わるかどうか」です。
誰かの評価を気にしてタイトルをつけると、つまらなくなったり、書く内容も型にはまってしまったりします。
それよりも、「この本を読んで、私はこんなふうに思ったんだよ」と、素直に伝えられるタイトルのほうが読む人の心には響きます。
たとえば、「〇〇って、そんな人だったの?」や「〇〇のひとことが忘れられない」など、あなた自身の視点や気づきをそのまま言葉にすれば、それだけで立派なタイトルになります。

誰かのためじゃなく、自分の気持ちをちゃんと届けるためにタイトルを考えてみましょう。
読書感想文のタイトルが変わる7つのヒント【例文付き】
難しいテクニックは必要ありません。あなたの中にある「おもしろさ」や「ひっかかり」をタイトルにしてみましょう。
タイトルって、“正解”があるように見えて、実はとても自由。
誰かに褒められるためではなく、自分が「あ、これだ」と思えるタイトルを見つけられたら、それだけで感想文を書くのが楽しくなります。
ここでは、自分らしいタイトルを見つけるためのヒントを7つ紹介します。
どれも、ちょっとした視点の変化でできるものばかり。ピンとくるものがあれば、ぜひ試してみてください。
① 自分と本とのつながりをそのまま言葉にしてみる
本を読んで「これ、私に似てるかも」「前に同じようなことがあったな」と思ったことはありませんか?
そんなときは、その気づきこそがタイトルにする価値のある“つながり”です。
たとえば、『走れメロス』を読んで、「もし自分がメロスだったら…」と考えたとしたら、そのまま《私がメロスだったら、友を信じられたか?》というタイトルにできます。
自分と本の登場人物を重ねるのは、とても自然で、書きやすいアプローチ。
また、「この本の○○という場面、まるで自分の体験みたい」と思ったなら、《○○で泣いた日を思い出した》のように、自分の経験と結びつけるのもおすすめです。
本を読んだのは、あなた自身。そのあなただけの視点や記憶を、遠慮なくタイトルに活かしてみましょう。
『走れメロス』⇒「 私がメロスだったら、友を信じきれただろうか?」
『モモ』⇒「 “時間どろぼう”に追われていたのは、私自身かもしれない」
『エルマーのぼうけん』⇒「わたしにとっての“りゅう”を助けに行く物語」
② 読んだときの気持ちをタイトルにこめる
読書中に心が動いた瞬間、ありましたか? ドキドキした、泣きそうになった、モヤモヤした、怒りがわいた…。
その「気持ち」をタイトルに入れると自分らしさがぐっと伝わりやすくなります。
たとえば、『ごんぎつね』を読んで「やるせない気持ち」になったなら、《どうして、ごんは…》や《悲しさだけが残った》など、その感情を率直に表す言葉を使ってみるのが効果的です。
ポイントは「うまくまとめよう」と思わなくていいということ。
自分がその本を読んだときに出てきた、率直な気持ちこそが、いちばんオリジナルなタイトルになります。
言葉にならないような感情もムリに説明せず、「うまく言えないけど、心に残っていること」をキーワードにしてみてください。
『ハチ公物語』⇒「信じるって、こんなにせつないことだったの?」
『ビルマの竪琴』⇒「心がざわざわして、読み終わってもしばらく動けなかった」
『ちいちゃんのかげおくり』⇒「あんなに静かな涙を流したのは初めてだった」
③ 「あれ?」と思ったことをそのまま疑問形に
本を読んでいて、ふと立ち止まってしまった場面はありませんか?
「えっ、なんで?」「それって本当に正しいの?」――そんな“ひっかかり”を感じたとき、それをタイトルにしてしまうのもアリです。
たとえば、《主人公は、本当に幸せだったの?》《私なら、同じことをしたかな?》など、自分の疑問や違和感をそのままタイトルにすれば、「どうしてそう思ったのか」を書く動機になります。
疑問形のタイトルは、読む人の興味を引きやすいだけでなく、自分自身も書きながら考えるきっかけになります。
「感動した」よりも、「なんかひっかかった」「気になった」から始まる感想文は、実はすごく深みが出やすいんですよ。
『クモの糸』⇒「本当に、主人公は幸せだったの?」
『スーホの白い馬』⇒「悪いのは誰だったんだろう?」
『二十四の瞳』⇒「あの選択は“正しかった”のか?」
④ 本の中の言葉を自分の言葉でアレンジする
登場人物のセリフや印象的なナレーションなど、本の中に残る言葉があるなら、それをアレンジしてタイトルに使う方法もおすすめです。
たとえば『星の王子さま』の中の有名な一節「大切なことは目に見えない」を読んで心に残ったら、《僕にとっての“目に見えないもの”とは》というタイトルにするなど、自分の体験や考えに引き寄せて表現できます。
その言葉がどんな意味を持っているのか、自分にとってどう響いたのかを考えることが、そのまま感想文の中身にもつながります。
一語一句そのまま使う必要はありません。少し言い回しを変えてみたり、自分の言葉で言い直したりしてみましょう。
「この言葉、ずっと心に残ってる」そんな一節があるなら、タイトルの候補にしてみてください。
『星の王子さま』⇒「 “目に見えない大切なもの”を、私はまだ持っているかな?」
『おじさんのかさ』⇒「“ぬれちゃいかん”の意味がやっとわかった」
『あらしのよるに』⇒「 “あらしのよるに”始まった友情」
⑤ 世間のイメージと自分の感想がズレていたらチャンス
有名な作品を読んだとき、「みんなが言ってるほど感動しなかった」「ちょっと違和感があった」なんてことはありませんか?
そう感じたなら、まさにそれが“自分だけの視点”です。
たとえば、『クモの糸』を読んで、「本当にあれは救いだったの?」と疑問に思ったなら、《クモの糸は“やさしさ”だったのか?》というように、自分の解釈を問うタイトルにしてみましょう。
世間のイメージとズレているからこそ、逆に深く考えた証拠にもなりますし、そこにこそあなたの感想文の個性が表れます。
「この本、どうして評価が高いんだろう?」という違和感も、大切な感情のひとつ。周りに合わせる必要はありません。
『走れメロス』⇒「 感動の話、だと思っていたけど違った」
『カモメに飛ぶことを教えた猫』⇒「 “正義”がちょっと怖くなった」
『クモの糸』⇒「読み終わっても、モヤモヤが残ったままだ」
⑥ 「このフレーズが刺さった!」をそのまま題名に
読書中に「うわ、今の一文めっちゃいい!」と思う瞬間があれば、そのままタイトルに使うのも立派な方法です。
たとえば、『アルジャーノンに花束を』のラストのセリフ「お墓に花を…」に強く心を動かされたなら、《花を手向けたい気持ちで読み終えた》など、そのフレーズを起点にしてタイトルを作ってみましょう。
その言葉がどこで出てきたか、どういう意味があったか、なぜ刺さったのか……。
その“感じた理由”を書けば、自然と読書感想文の軸ができていきます。
本のフレーズに自分の感情を添えて表現することで、「あなただけのタイトル」に生まれ変わります。
『ビルマの竪琴』⇒「“悲しみの上に立って、生きる”という言葉が忘れられない」
『窓ぎわのトットちゃん』⇒「“君はほんとうはいい子なんだよ”の意味を考えた」
『アンネの日記』⇒「 “ありがとう”の一言が、あんなに重く感じたことはなかった」
⑦ 友達に「どんな本だった?」と聞かれたら?を考えてみる
もし友達に「その本、どうだった?」と聞かれたら、あなたはなんて答えますか?
そのひとことが、意外とそのままタイトルになります。
たとえば、「うーん、泣いた」「最後の展開が信じられなかった」「あの子が変わっていくの、すごくよかった」――そんな“感想の第一声”が、あなたのリアルな反応。
それをそのままタイトルにするなら、《最後のページ、まさかああなるなんて》《私はこの子の変化を見届けたかった》など、感情がそのまま乗ったものができます。
むずかしく考えるより、友達との会話のように、ラフな気持ちで言葉を探してみましょう。
本音で話したい言葉こそ心を動かすタイトルになります。
『ズッコケ三人組』⇒「うまく言えないけど、すごく心があたたかくなった本」
『ルロイ修道士』⇒「読んだあと、静かに涙が流れた」
『泣いた赤おに』⇒「ああ、友情ってこういうことかもしれない」
「いいタイトルが浮かばない」ときの考え方
「どうしても決まらない!」ときにこそ、少しだけ視点を変えてみましょう。
「タイトルが全然思いつかない」「考えれば考えるほど、平凡な言葉しか出てこない」——そんなときもあります。
でも大丈夫。感想文のタイトルは、最初に決めなくてもいいし、かっこよくなくてもいいんです。
大事なのは、あなたが「この本を読んで何を感じたのか」「どんなところに引っかかったのか」。
その“自分らしい感想”に寄りそったタイトルが、最終的にはいちばん伝わるものになります。

ここでは「行き詰まったときにどう考えるとラクになるか?」という視点から、3つのヒントをご紹介します。
タイトルは最後に考えてもOK
読書感想文に限らず、タイトルを最初に決めようとして手が止まってしまうこと、ありませんか?
でも実は、タイトルは感想文を書き終わってから決めても、まったく問題ありません。
書きながら思考が深まったり、「本当はこう感じていたんだ」とあとから気づいたりすることもよくあります。
そういうとき、最初に決めたタイトルと中身がズレてしまうことも。ならば、先に思いのまま書いてみて、最後に“ぴったりくる言葉”を探すのが自然です。
書き終えたあとに読み返しながら、「自分はこの本で何を伝えたかったんだろう?」と問い直してみましょう。
その答えが、そのままあなたのタイトルになります。
「好きな言葉」をタイトルに借りてみる
「好きな言葉」や「よく口にするフレーズ」ってありますか?
それをタイトルに借りるのも、実は立派な作戦です。
特に気に入った言い回しや自分にとって特別な言葉がある人におすすめです。
たとえば、「ありがとう」という言葉が好きなら、その言葉を軸にしたタイトルにしてみましょう。
たとえば
『アンネの日記』⇒「ありがとうを言いたくなった一冊」
『ごんぎつね』⇒「ごんに、ありがとうを伝えたかった」
このように「自分が自然に使う言葉」を入口にすると、自分らしい語り口のまま、自然と感想文に入っていけます。

難しい表現をひねり出すよりも「自分の言葉」を選んだ方が、読み手にもあなたの想いがまっすぐ届くのです。
「誰かに話すなら?」を想像してみる
「この本、どうだった?」と友達に聞かれたとしたら、どう答えるでしょう?
実はその“答え方”が、そのまま読書感想文のタイトルになることがよくあります。
たとえば、感想文を書こうとして言葉が出てこないときでも、会話の中では意外とサラッと「面白かったよ」「〇〇のところで泣いた」なんて言えてしまうものです。
その感覚を活かして、こんなタイトルが考えられます。
『ビルマの竪琴』⇒「なんだか、読んでるあいだずっと静かだった」
『泣いた赤おに』⇒「うまく説明できないけど、泣いた」
このように、“誰かに話すような言葉”には難しくないぶん本音が出ていて、しかも自然と伝わる力を持っています。
もしタイトルで悩んだら、「ちょっと誰かに話すとしたら、何て言う?」と想像してみるのがおすすめです。
まとめ
読書感想文のタイトルに「正解」はありません。
けれど、「自分が感じたことを自分の言葉で表す」という出発点に立てば、きっとあなたらしいタイトルが見つかります。
「〇〇を読んで」といった形式にとらわれる必要はありません。
感動したこと、疑問に思ったこと、心に残った一言、登場人物とのつながり、自分の中に起きた変化……それらすべてが、タイトルの材料になります。
また、書き出しが難しいと感じたときは、タイトルをあとで考えるのもOK。
「好きな言葉」「誰かに話すならどう言うか?」など、少し視点を変えるだけで、ことばはスッと出てくることがあります。
この記事で紹介したヒントや例をヒントにしながら、誰かのためではなく、あなた自身の言葉でタイトルをつけてみてください。
それが、感想文を「書かされるもの」ではなく、「書いてよかったもの」に変えてくれるはずです。
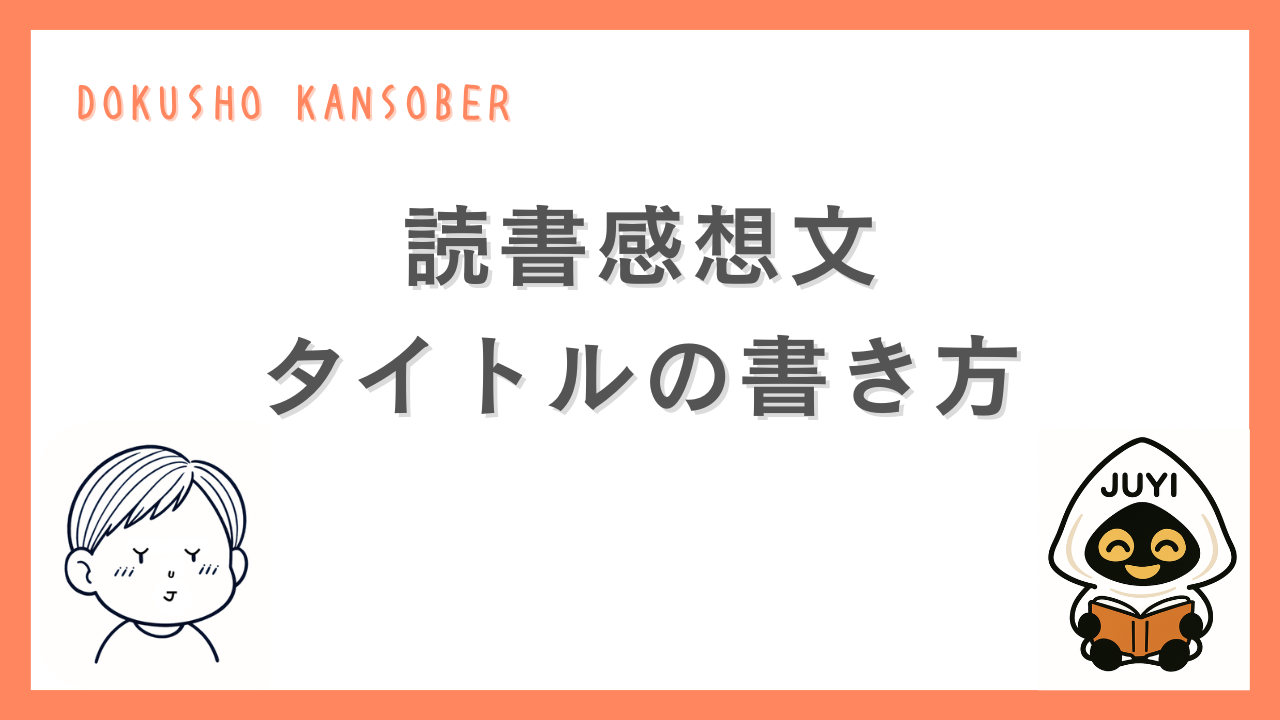
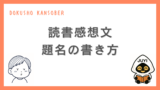
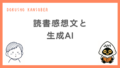

コメント