2025年の読書感想文コンクールに向けて、各学年ごとの課題図書が発表されました。
「どの本を選べばいい?」「感想文ってどう書いたらいいの?」と迷う保護者や子どもたちのために、本記事では小学生・中学生・高校生向けに課題図書18冊を学年別でわかりやすくご紹介。
選定理由や読みどころ、感想文の構成のコツまで、はじめての読書感想文でも安心して書き進められるようサポートします。

ぜひ、お子さんにぴったりの1冊を見つけてください。
読書感想文の課題図書とは?【2025年版】
毎年、夏休みの宿題として出される「読書感想文」。
その中でもよく耳にするのが「課題図書」という言葉です。
でも、「課題図書ってなに?」「自由に選んじゃダメなの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
ここでは、読書感想文における課題図書の意味や選ばれる理由、そして2025年ならではの注目ポイントまで、わかりやすくご紹介します。
青少年読書感想文全国コンクールの課題図書とは
読書感想文の「課題図書」とは、毎年開催される「青少年読書感想文全国コンクール」に向けて、全国学校図書館協議会と毎日新聞社によって選ばれる推薦図書のことです。
このコンクールは、日本全国の小学生・中学生・高校生が対象で、読書を通じた思考力・表現力の育成を目的としています。
課題図書は学年別に4〜5冊ずつ選ばれ、小学生は低学年・中学年・高学年、中学生、高校生の5部門に分かれています。
選ばれる本は、教育的価値や心の成長を促す内容であることが重視されており、実際に読んで「考えたこと」「感じたこと」を深めやすい作品が揃っています。
各学校での感想文の宿題にも、この課題図書が指定されることが多く、全国的にも認知度の高い図書群です。
課題図書と自由図書のちがい
読書感想文の提出においては、「課題図書部門」と「自由図書部門」のどちらかを選ぶことができます。
このうち「課題図書部門」では、全国学校図書館協議会が発表した本の中から選んで書く必要があります。
一方の「自由図書部門」では、児童・生徒本人が好きな本を自由に選んで感想文を書くことが可能です。
課題図書には審査基準に適した構成やテーマ性があり、評価されやすい一方で、人気が集中するため競争が激しいという側面も。
一方、自由図書なら自分の興味に合った本を選べるので、より個性的な読書感想文を書くチャンスがあります。
ただし、書きやすさという点では、課題図書の方が「感想が深まりやすい構造」になっていることも多く、作文が苦手な子にとっては安心材料となることも。
| 比較項目 | 課題図書 | 自由図書 |
|---|---|---|
| 選び方 | 全国学校図書館協議会が指定 | 自分で自由に選べる |
| テーマ・構成 | 審査基準に合った構成・テーマ性がある | テーマ・ジャンルは自由で個性が出やすい |
| 書きやすさ | 感想が深まりやすく書きやすいことが多い | 興味がある本なら書きやすいが、構成に迷う場合も |
| 評価の傾向 | 評価されやすいが、応募数が多く競争も激しい | 個性的な作品になりやすいが、評価はバラつきがち |
| 向いている人 | 感想文に苦手意識がある人、受賞を狙いたい人 | 読書が好きで自由に表現したい人、自分の言葉で書きたい人 |
2025年の傾向と注目ポイント
2025年の課題図書に共通して見られる特徴は「多様性」と「気づき」がキーワードになっている点です。
小学生向けには「友だち」「自分らしさ」「いのち」といったテーマ、中学生向けには「食」「貧困」「女性の生き方」など身近な問題から社会性を育む内容、高校生向けには「歴史」「宗教」「障がい」などより深い社会的課題が描かれた作品が選ばれています。
特に今年は、実話をもとにしたノンフィクションや生き物とのふれあいを描いた作品が目立ちます。
また、グローバルな視野を持たせるような海外作品の翻訳も多く、世界とのつながりや異文化理解がテーマとして強く打ち出されています。

どの学年においても、読後に「これは他人事じゃない」と感じさせるような構成の本が多く、感想文を書きながら自然と“自分の言葉”が出てくる内容になっているのが今年の大きな特長です。
2025年の課題図書一覧【学年別】
2025年の課題図書は、各学年ごとに「心の成長」「多様性への気づき」「社会性」がテーマとして色濃く反映されています。
そこで、ここでは小学生(低・中・高学年)、中学生、高校生と学年別に1冊ずつピックアップし、その魅力と選びどころをお伝えします。
さらに、価格や出版社、ジャンルも一覧表にまとめて比較しやすくしました。
小学生の課題図書
小学生向けの課題図書は、低学年・中学年・高学年の3つの学年区分ごとに、それぞれ3〜4冊ずつ選ばれています。
2025年のラインナップには、友情や多様性、自己肯定感、環境問題、障がい理解など、子どもたちが身近に感じられるテーマが豊富に含まれており、読後に「自分だったらどうする?」と自然に考えを深められる本が揃っています。
学年に応じた表現のやさしさや、絵・写真の力も活かされており、感想文を書きやすい工夫が随所に見られます。
「うちの子にはどれが合うかな?」と迷っている保護者の方にも参考になるよう、それぞれの魅力と読みどころを学年別に詳しくご紹介します。
小学校低学年(全4冊)
『ライオンのくにのネズミ』(さかとく み雪/中央公論新社)
父親の転勤でライオンのくにに引っ越したねずみの家族。ライオンが怖くて仕方がない子ねずみだったが、あることをきっかけにライオンと対決することに。使う言葉も習慣も体の大きさも違う彼らはわかりあうことができるのか?「優しさと勇気」についての絵本としても、「国際理解教育」の教材としても読める、幅広い層に届けたい1冊。

ライオンの学校に転校してきたネズミの「ぼく」が、体の大きさも言葉も習慣も違うクラスメートたちと交流しながら、自分の勇気を試していく物語。絵本でありながら、現代の多文化社会や「違いをどう受け入れるか」というテーマを、やさしくも力強く伝えてくれます。子どもたちの“人とのかかわり”を考えるきっかけになる一冊です。
『ぼくのねこポー』(岩瀬成子/PHP研究所)
ぼくがひろったのは、すてねこなのかな?学校からのかえり道に見つけたねこ。のらねこなのかな?それともすてねこ?ぼくんちのねこになってくれたらいいな。

拾った猫が、もしかすると転校生・森くんが探している猫かもしれない。でも、手放したくない……。そんな葛藤の中で、主人公は自分の気持ちと向き合いながら、本当に大切なものに気づいていきます。「正しさ」だけでは解決できない場面に、子どもがどう向き合うかを考えさせられる物語です。
『ともだち』(リンダ・サラ 作/ベンジー・デイヴィス 絵/しらいすみこ 訳/ひさかたチャイルド)
ぼくとエトは、だいのなかよし。だんボールばこをおかのうえまでひっぱっていっては、はこのなかにはいってあそぶ。これって、さいこうにおもしろいんだ。あるひ、しらないおとこのこがなかまにいれてほしいとやってきた。エトは「いいよ!」っていったけど、ぼくのほんとうのきもちは…。新しいともだちがあらわれ、揺れる「ぼく」の気持ちを丁寧に描いたものがたり。

大の仲良しだった「ぼく」と「エト」が、もう一人の男の子を仲間に入れたことで、気持ちが揺れ動きます。「ふたり」から「さんにん」になることで生まれる戸惑いや、うれしさ、さみしさ。友だちとの関係性が変化していく中で、どう気持ちを整理していくのかが、やさしいタッチで描かれています。
『ワレワレはアマガエル』(松橋利光/アリス館)
カエルと聞いて思いうかぶのは?ぴょこんと目が出て、緑色のーーそう、ワレワレ、アマガエルだろう!体のしくみや、産卵からおたまじゃくし、冬眠までを、アマガエルたちの自己紹介で、楽しく見せます。

「ワレワレ」と語りかけてくるアマガエルが、卵からオタマジャクシ、そしてカエルへと変化していく驚きの生態を、迫力ある写真とともに紹介してくれます。子どもたちが自然に興味を持ち、理科や環境への関心を高めるきっかけにもなる、楽しくて学びの多い科学絵本です。
小学校中学年(全4冊)
『ふみきりペンギン』(おくはらゆめ/あかね書房)
ゆうとはペンギンの話を、るりは白いヘビのうわさを、ななこは鏡のライオンを、そうすけはフクロウの占いを、聞いたり、見たり、かんじたり…。「ふつうとは?」を決めつけず、それぞれの自分らしさを肯定する、ある町の小学三年生の物語。

主人公・ゆうとがペンギンにばかにされ、「ふつうってなんだろう?」と悩むところから始まる物語。子どもたちが感じる「自分ってちょっとヘンかも?」という不安に寄り添いながら、自分らしさを見つけていく過程が丁寧に描かれています。やさしい文章でありながら、心に響くテーマが光る一冊です。
『バラクラバ・ボーイ』(ジェニー・ロブソン 作/もりうちすみこ 訳/黒須高嶺 絵/文研出版)
バラクラバ帽をかぶった転入生のトミーがやってきた。なぜトミーは帽子をかぶってるの?あの帽子の下には何がかくされている?ぼくとドゥミサニのたいくつな日々は、「バラクラバ・ボーイ」によって大きく変わったんだ。小学中級から。

転校生のトミーは、いつもバラクラバという帽子をかぶっている。なぜ?その帽子の下には何がある?という興味から始まり、友情や偏見、違いの受け入れについて考えさせられる物語です。笑いあり感動ありの展開で、最後に心があたたかくなる読後感が待っています。
『たった2℃で…』(キム・ファン 文/チョン・ジンギョン 絵/童心社)
地球の平均気温が2℃あがると、環境災害がはじまる。人間は、野外活動ができなくなる。海の魚たちの大量死、大移動がおこる。海の生きものの種の25%がくらすサンゴ礁がきえる。虫が、ばくはつてきにふえて生態系の混乱がおこる。そして…
気温がたった2℃上がることで、地球やそこに生きる私たちの生活がどう変わるのか?を、具体的に、かつビジュアル豊かに伝えてくれる絵本。難しい地球温暖化の話を、子どもたちにもわかりやすく伝える構成で、環境問題への関心や行動の大切さに気づかせてくれる一冊です。
『ねえねえ、なに見てる?』(ビクター・ベルモント 文・絵/金原瑞人 訳/河出書房新社)
多様性と他者理解について知るSDGs絵本。科学者のママ、ゲーム好きのパパ、音楽家のおじさん…同じ場にいても、見ているもの、その見え方はまったくちがう!?きみには、どんなふうに見えてる?

同じ場所にいても、見る人によって“見え方”は全く違う。色覚異常を含む「視点の違い」から始まり、科学者、音楽家、アーティストなど、さまざまな人の見え方を紹介するユニークな絵本です。視覚的にも楽しめ、多様性や共感を学ぶ入り口として最適です。
小学校高学年(全4冊)
『ぼくの色、見つけた!』(志津栄子/講談社)
「あれ、あれれ。おまえ、チョコレートを食べたのかぁ」ぼくの絵を見て、最初に笑ったのは足立友行だ。「口にチョコレートがついてるよ」口にチョコレートがついているって?ぼくは自分の描いた似顔絵をまじまじと見た。これ、口の色じゃなかったのか。-自分の「世界の見え方」に向き合い、自分なりの「光」を見つけていく物語。

色がうまく見えないという障がいを抱えながらも、自分の見え方を受け入れ、成長していく主人公の姿が描かれます。人とは違う自分を「不安」と捉えるか、「特別」と捉えるか。その葛藤と気づきが、読者の心に深く残ります。先生や周囲の理解も温かく、前向きな気持ちになれる作品です。
『森に帰らなかったカラス』(ジーン・ウィリス 作/山﨑美紀 訳/徳間書店)
一九五七年、ロンドン郊外の町。11歳の少年ミックは、近所の森で、ケガをしたニシコクマルガラスのひなを見つけた。父さんや母さん、親友ケンの手を借りつつ、けんめいに手当てをするうち、ひなはすっかりミックになつく。ジャックと名づけられたひなは成長し、やがて、地域のみんなに知られる人気者になるが…?人々の心に第二次世界大戦の傷あとが残る、一九五〇年代のイギリスを舞台に、少年が動物とふれあい成長するすがたを描く。ロンドン動物園の元主任飼育員の少年時代の実話にもとづく、心あたたまる児童文学。

ケガをしたカラスを助けた少年と、その後も家に戻ってくるようになったカラスとの交流を描いた物語。実話をベースにしており、命や動物との関係、人の優しさや戦争の影まで描かれていて、幅広い読後の考察が期待できます。静かな感動がじんわり広がる一冊です。
『マナティーがいた夏』(エヴァン・グリフィス 作/多賀谷正子 訳/ほるぷ出版)
11歳の夏休み、ピーターはすべてうまくやれるはずだった。「生き物発見ノート」を完成させ、認知症のおじいちゃんのお世話をし、けがをしたマナティーを守る。それなのにー。変化に向き合う勇気をくれる、ひと夏の成長物語。

フロリダの自然の中で、マナティーと出会った少年・ピーターが、祖父や親友との思い出とともに成長していく姿を描く物語。自然との関わり、命との向き合い方、人とのつながりなど、読後にたくさんの問いが生まれる作品です。海外作品ながら読みやすく、感情移入もしやすい構成です。
『とびたて!みんなのドラゴン』(オザワ部長/岩崎書店)
内気で人前で話すことができないマナミが通う小学校にはただひとつの部活動、合唱部があった。上手なだけじゃない、部員たちの輝く姿を見て、マナミは入部を決意する。でも、4月から顧問になった先生には、ある秘密があったー

ALS(筋萎縮性側索硬化症)を患う先生と、小学校合唱部の子どもたちが全国大会を目指すノンフィクション。病気への理解、人前で話すことが苦手な子の挑戦、仲間との絆など、どの登場人物にも感情移入できるのが魅力です。事実に基づく感動の物語は、読書感想文の題材にも適しています。

課題図書以外でおすすめの本を知りたい方は下記の記事も参考にしてください。
中学生の課題図書
中学生向けの課題図書では、思春期の悩みや人間関係、社会課題と向き合う力を養える3冊が選ばれました。
2025年は「食」「貧困」「女性の生き方」といった、身近でありながら深いテーマに触れる作品が揃っています。
読書感想文では、主人公の気持ちを想像したり、自分と照らし合わせたりしながら、内面を掘り下げて書きやすいラインナップです。
読後に感じたことを「自分の言葉で」表現しやすいのが、中学生部門の魅力です。
『わたしは食べるのが下手』(天川栄人/小峰書店)
少食で食べるのが遅い葵は、食事の時間が苦手。とくに給食は…。「小林さんさ、たぶん君、会食恐怖症だわ」無理に油淋鶏を飲みこんで気持ちが悪くなった葵は、保健室でクラスの問題児、咲子にそう言われる。実は咲子も、食にかかわるある悩みを抱えていた。そんな二人は、新任のイケメン栄養教諭に焚きつけられて、給食改革に乗り出すことに…。わたしたちが望む給食って、いったいどんなだろう?

会食恐怖や摂食障がいという“食べること”に悩む中学生2人が、周囲の人との関わりの中で少しずつ変化していく姿を描いた物語。「ちゃんと食べなきゃいけない」というプレッシャーや、まわりと違うことへの不安など、誰もが一度は感じたことのある葛藤が丁寧に描かれています。「食べること=生きること」の大切さを問い直しながら、相手の立場を思いやる視点も育める一冊です。
『スラムに水は流れない』(ヴァルシャ・バジャージ 著/村上利佳 訳/あすなろ書房)
そもそもの問題は、水がたりないことだった。インド有数の大都会ムンバイ。12歳のミンニと15歳の兄サンジャイが暮らすスラムには、ムンバイの人口の40パーセントが住んでいるにも関わらず、水は市全体の5 パーセントしか供給されていない。水不足がきびしくなる三月のある夜、サンジャイが「水マフィア」を目撃してしまい……。家族の絆、友情、そしてインドの「今」を描く、勇気と成長の物語。

インドのスラムに暮らす少女・ミンニは、水が極端に不足する環境でたくましく生きています。母の病気、兄の失踪、そして汚職や差別といった理不尽な現実と向き合いながら、希望を捨てずに未来を切り拓いていく姿が感動的です。海外の貧困問題を、読者が「自分とは無関係」と切り離さずに考えられるようになる貴重な物語で、社会への視野を大きく広げてくれる作品です。
『鳥居きみ子:家族とフィールドワークを進めた人類学者』(竹内紘子/くもん出版)
人類学者・鳥居きみ子をはじめて描いた人物伝。夫・龍蔵や家族とともに、まるで探検するようなフィールドワーク(野外調査)を進めた鳥居きみ子。人類学のなかでも、昔から伝わる生活・風習・伝説・歌などを調べる民族学を切り開きました。さまざまな困難に直面しながらも、龍蔵に対する大きな信頼と度胸のよさでつきすすんだきみ子。これまで紹介されることがなかった人物の生涯を描きます。

明治・大正・昭和という時代を生きた女性人類学者・鳥居きみ子の伝記。調査対象地に家族とともに出向き、母として子どもを育てながら、研究者としても道を切り拓いていったその生き方は、多くの制約の中で「どう生きるか」を模索する若い世代の共感を呼びます。フィールドワークの面白さだけでなく、家族の絆や情熱の大切さにも触れられる一冊です。

課題図書以外でおすすめの本を知りたい方は下記の記事も参考にしてください。
高校生の課題図書
高校生向けの課題図書は、文学的な深みと社会的な問題意識を併せ持つ作品が多く、自分の価値観や生き方を見つめ直すきっかけになる内容が中心です。
2025年は、ろう文化、分断された歴史、そして文学との出会いを通じて心を動かす3冊が選ばれました。文章量はやや多めですが、読みごたえがある分、感想文でも多様な視点で書くことができます。
思春期の迷いや模索に寄り添う本が揃っているのが、高校生部門の特徴です。
『銀河の図書室』(名取佐和子/実業之日本社)
県立野亜高校の図書室で活動する「イーハトー部」は、宮沢賢治を研究する弱小同好会だ。部長だった風見先輩は、なぜ突然学校から消えてしまったのか。高校生たちは、賢治が残した言葉や詩、そして未完の傑作『銀河鉄道の夜』をひもときながら、先輩の謎を追っていきー。物語を愛するすべての人へ贈る、青春小説の金字塔!

宮沢賢治を愛する高校の読書同好会「イーハトー部」の部長が突然いなくなった――その謎を追いながら、残されたメンバーたちが読書と向き合い、自分自身と向き合っていく青春小説です。賢治の言葉を手がかりに、それぞれの悩みや想いが交差する構成になっており、「ほんとうの幸い」を探す旅は、読み手の心にも静かに問いを投げかけます。文学好きにもおすすめの一冊。
『夜の日記』(ヴィーラ・ヒラナンダニ 著/山田 文 訳/作品社)
イギリスからの独立とともに、ふたつに分かれてしまった祖国。ちがう宗教を信じる者たちが、互いを憎みあい、傷つけあっていく。少女とその家族は安全を求めて、長い旅に出た。自分の思いをことばにできない少女は亡き母にあてて、揺れる心を日記につづる。

インドとパキスタンの分断という激動の時代の中、少女ニシャは「亡き母への日記」に自分の思いを綴ります。宗教や文化の違いによって起こる争いや、家族の絆、言葉にできない思いをどう表現するかといったテーマが、静かで力強い文体で描かれています。『アンネの日記』を彷彿とさせる構成は、文学としても高い完成度。国際問題と個人の心情の交差が、深い読後感を残します。
『「コーダ」のぼくが見る世界』(五十嵐 大/紀伊國屋書店)
コーダ(CODA)=聴こえない/聴こえにくい親のもとで育つ、聴こえる子ども。もし、親の耳が聴こえたらーなんて、想像もつかなかった。ときに手話を母語とし、ときにヤングケアラーと見なされて、コーダは、ろう者とも聴者とも違う複雑なアイデンティティを抱えて揺れ動く。映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』原作者の最新エッセイ集。

「コーダ(CODA)」とは、聴こえない親をもつ“聴こえる子ども”のこと。著者は自身の経験をもとに、手話で育った日常、言葉の壁、そして善意の押しつけに戸惑った体験を描いています。人とわかりあうとはどういうことか?という根源的なテーマに、読者自身も深く向き合わされるノンフィクション。文章は平易ながら中身は深く、気づきを得られる一冊です。

課題図書以外でおすすめの本を知りたい方は下記の記事も参考にしてください。
【一覧表つき】2025年課題図書まとめ(価格・出版社・ジャンル)
ここでは、2025年に選ばれた課題図書18冊を、学年別に一覧表でまとめました。
本のタイトルや著者、出版社、価格、そしてジャンル(テーマ)をひと目で比較できるようにしています。
「どんな本があるかざっと把握したい」「書店で探すときに目安を知りたい」「内容やジャンルで選びたい」といった方におすすめの表です。
気になる本があれば、上の紹介文に戻ってじっくりチェックしてみてください。
📚 2025年 課題図書一覧表(全18冊)
| 学年 | 書名 | 著者(訳者) | 出版社 | 価格(税込) | ジャンル(テーマ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校低学年 | ライオンのくにのネズミ | さかとく み雪 | 中央公論新社 | 1,760円 | 絵本・異文化理解 |
| 小学校低学年 | ぼくのねこポー | 岩瀬成子 | PHP研究所 | 1,430円 | 物語・心の葛藤 |
| 小学校低学年 | ともだち | リンダ・サラ/ベンジー・デイヴィス/しらいすみこ | ひさかたチャイルド | 1,760円 | 絵本・友情と関係性 |
| 小学校低学年 | ワレワレはアマガエル | 松橋利光 | アリス館 | 1,870円 | 写真絵本・生き物の生態 |
| 小学校中学年 | ふみきりペンギン | おくはらゆめ | あかね書房 | 1,430円 | 物語・自己理解 |
| 小学校中学年 | バラクラバ・ボーイ | ジェニー・ロブソン/もりうちすみこ/黒須高嶺 | 文研出版 | 1,540円 | 物語・異文化理解と友情 |
| 小学校中学年 | たった2℃で… | キム・ファン/チョン・ジンギョン | 童心社 | 1,980円 | 絵本・地球温暖化 |
| 小学校中学年 | ねえねえ、なに見てる? | ビクター・ベルモント/金原瑞人 | 河出書房新社 | 1,793円 | 絵本・視点の違い/多様性 |
| 小学校高学年 | ぼくの色、見つけた! | 志津栄子 | 講談社 | 1,650円 | 小説・障がい理解 |
| 小学校高学年 | 森に帰らなかったカラス | ジーン・ウィリス/山﨑美紀 | 徳間書店 | 1,760円 | 小説・動物とのふれあい/命の重さ |
| 小学校高学年 | マナティーがいた夏 | エヴァン・グリフィス/多賀谷正子 | ほるぷ出版 | 1,760円 | 小説・自然・成長 |
| 小学校高学年 | とびたて!みんなのドラゴン | オザワ部長 | 岩崎書店 | 1,650円 | ノンフィクション・合唱・難病と挑戦 |
| 中学生 | わたしは食べるのが下手 | 天川栄人 | 小峰書店 | 1,760円 | ノンフィクション・食と心の問題 |
| 中学生 | スラムに水は流れない | ヴァルシャ・バジャージ/村上利佳 | あすなろ書房 | 1,760円 | 小説・貧困・環境・家族 |
| 中学生 | 鳥居きみ子 | 竹内紘子 | くもん出版 | 1,540円 | 伝記・女性の生き方・家族・調査 |
| 高校生 | 銀河の図書室 | 名取佐和子 | 実業之日本社 | 1,870円 | 小説・青春・読書・文学 |
| 高校生 | 夜の日記 | ヴィーラ・ヒラナンダニ/山田文(訳) | 作品社 | 2,420円 | 小説・宗教・家族・歴史 |
| 高校生 | 「コーダ」のぼくが見る世界 | 五十嵐 大 | 紀伊國屋書店 | 1,760円 | ノンフィクション・ろう文化・共感 |
この表を参考にしながら、お子さんの学年や読書レベル、興味のあるテーマに合わせて、最適な一冊を選んでみてください。
「感想文を書かせるための本」ではなく、「心に残る体験としての読書」を選ぶ視点が、作文力だけでなく思考力や表現力の育成にもつながります。
課題図書の選び方|読書感想文に適した1冊を見つけよう
課題図書は全部で18冊ありますが、実際にお子さんが感想文を書くのは、その中から「学年ごとに選ばれた3~4冊のうち1冊」です。
つまり、「どの本を選ぶか」が感想文の書きやすさや仕上がりに大きく影響します。
難しすぎても、内容にピンとこなくても、なかなか感想が書けずに手が止まってしまうことも…。
そんな失敗を防ぐために、この章では「感想がスラスラ書ける本の選び方」を3つの視点からご紹介します。
お子さんの個性や読書経験に合わせて、ぴったりの1冊を見つけてあげましょう。
「共感できる主人公」で選ぶ
読書感想文において大事なのは「登場人物の気持ちにどれだけ寄り添えるか」。
特に小中学生の場合、「この子、自分にちょっと似てるかも」と思える主人公の本を選ぶと、自然と感想が書きやすくなります。
たとえば、小学校中学年の『ふみきりペンギン』では、「ふつうって何?」と悩む主人公に共感しやすく、自分の経験や気持ちと結びつけやすい内容です。
中学生向けの『わたしは食べるのが下手』も、友だち関係や学校生活に悩むリアルな描写が共感を呼びやすく、感想文でも自分の言葉が出やすい構成になっています。
3~4冊の候補の中で「主人公の気持ちが一番よくわかる」と感じた本は、感想文の題材としてとても書きやすい1冊になります。
「感想を書きやすいテーマ」で選ぶ
読み終えたあと、「おもしろかったけど、何を書いたらいいかわからない…」という声は少なくありません。
これは、感想文に向いていないテーマを選んでしまった可能性があります。
課題図書の中には、環境問題、動物とのふれあい、家族や友情の物語など、感情が動きやすく、書きやすいテーマの作品が多く含まれています。
たとえば『森に帰らなかったカラス』や『マナティーがいた夏』のような自然や命にまつわる物語は、「かわいそう」「助けたい」といった素直な感情をきっかけに感想を広げやすいです。
『たった2℃で…』のような環境絵本も、学習と感想が結びつきやすいテーマの一つです。
数冊ある候補の中で、「この話は自分でも感じたことがある」「話しやすい内容だな」と思えた本は、感想文のとっかかりがつかみやすく、おすすめです。
子どもの読書レベルに合った本を選ぶコツ
課題図書の中には、ページ数や文の難しさに差があります。
すべての子がどの本でも書けるわけではありません。
読み慣れていない子が難しい作品に挑戦すると、「最後まで読めなかった」「内容がよくわからなかった」とつまずくことも。
そうならないためにも、お子さんの読書レベルに合った1冊を選ぶことが大切です。
低学年では、文章が短くイラストの多い絵本(『ともだち』『ワレワレはアマガエル』など)を、中学年ではストーリー展開が明るくテンポのよい物語(『バラクラバ・ボーイ』など)がおすすめです。
読書好きな子には、少し長めで深いテーマの作品(高校生の『夜の日記』など)にチャレンジするのも良いでしょう。
また、迷ったら親子で一緒に冒頭だけ読んでみて、「この本なら読めそう」「この話、好きかも」という感触を確認して選ぶと失敗が少なくなります。

ジャンル別のおすすめ作品に関しては下記の記事を参考にしてください。
読書感想文が書きやすくなるポイントと構成のコツ
課題図書をしっかり読んだのに、いざ感想文となると「何から書けばいいの?」「うまくまとまらない…」と悩むお子さんは少なくありません。
とくに読書感想文が初めての場合は、「どう構成すればいいか」や「どんな言葉で書き始めればいいか」がわからず、手が止まってしまいがち。
この章では、読書感想文を書くときの基本構成や書き出し方のコツ、さらに「先生に伝わりやすい感想文」のポイントを解説します。
文章力に自信がなくても、順を追って書けばしっかり仕上がる方法をご紹介します。
課題図書に合った感想文の構成とは
課題図書で感想文を書くときは、「あらすじの説明」で終わってしまわないことが大切です。
作品に登場する出来事や人物に対して、「自分がどう感じたか」「なぜそう思ったのか」を軸にして構成を組み立てることで、読み手にも伝わりやすい文章になります。
おすすめの構成は、次の4ステップ。
【4つの構成ステップ】
- 本との出会い(選んだ理由・期待)
- 印象に残った場面(できごと・セリフ)+簡単なあらすじ
- 感じたこと・考えたこと(自分の経験や気持ちと結びつけて)
- 読後の変化(考えが変わったこと・これからしたいこと)
この構成は小学生から高校生まで共通して使える基本形です。
特に課題図書は「気づき」や「共感」を呼ぶテーマが多いため、自分の内面とリンクしやすいのが特長です。
あらすじは長く書きすぎず、「自分の考え」をしっかり伝えることを意識しましょう。
書き出し・まとめ方の例文
感想文で最も悩みやすいのが「最初の一文」と「最後のまとめ」です。
書き出しは、いきなり本の感想に入るのではなく、「読もうと思ったきっかけ」や「表紙を見たときの印象」などから始めると、自然な導入になります。
📌 書き出しの例
- 「この本を読もうと思ったのは、タイトルにひかれたからです。」
- 「最初は課題図書だからしかたなく読みましたが、読んでいくうちにどんどん引きこまれました。」
- 「友だちとけんかしたばかりだったので、この話は自分のことのように感じました。」
📌 まとめ方の例
- 「この本を読んで、友だちの大切さにあらためて気づきました。これからは言葉にして気持ちを伝えたいです。」
- 「主人公のように勇気をもって行動できる人になりたいと思いました。」
- 「今まで気にしていなかったけれど、地球のためにできることを少しずつ始めたいです。」
どちらも「感じたこと」や「これからの自分」に少し触れると、作文としての完成度がぐっと高まります。
高評価されやすいポイントとは?
読書感想文で「評価されやすい文章」とは、かならずしも語彙が多い・表現がきれい、ということではありません。
むしろ大切なのは「自分の考えが伝わるかどうか」「本から何を感じたかを自分の言葉で書いているか」です。
特に次のような要素は、審査や先生からも評価されやすいポイントです。
- 感情の動きが伝わる(例:「最初は〇〇だったけれど、読んでいくうちに△△と思うようになった」)
- 気づきがある(例:「この本を読むまで、自分は〇〇に気づいていなかった」)
- 体験とつなげている(例:「以前、私も△△なことがありました。そのときと重なって…」)
- 読み手へのメッセージ性がある(例:「この本を読んで、ほかの人にも△△を知ってほしいと思いました」)
書き方が少しつたなくても、「自分の言葉で書いていること」が伝われば、それはしっかりと評価されます。
親や先生が直しすぎず、子ども自身の視点を大事にすることも高評価への近道になります。
まとめ
2025年の課題図書は、どの作品にも「心が動くきっかけ」がちりばめられており、読書感想文を書くのにふさわしい良書ばかりです。
しかし、全18冊から実際に選ぶのは、各学年ごとに用意された3~4冊の中の1冊。
だからこそ、内容やテーマ、そしてお子さん自身の「読みやすさ」や「共感しやすさ」をふまえて、じっくり選ぶことが大切です。
感想文は正解のない表現の場です。
うまく書こうとするよりも、「自分の気持ちをどう言葉にするか」に目を向けてあげると、子どもたちの言葉は自然と輝きます。
読んだ本が、その子にとって「心の糧」になるように、そして感想文が「読む力」と「書く力」を育てる学びの時間になるように──本選びの段階から、ぜひ親子で向き合ってみてください。
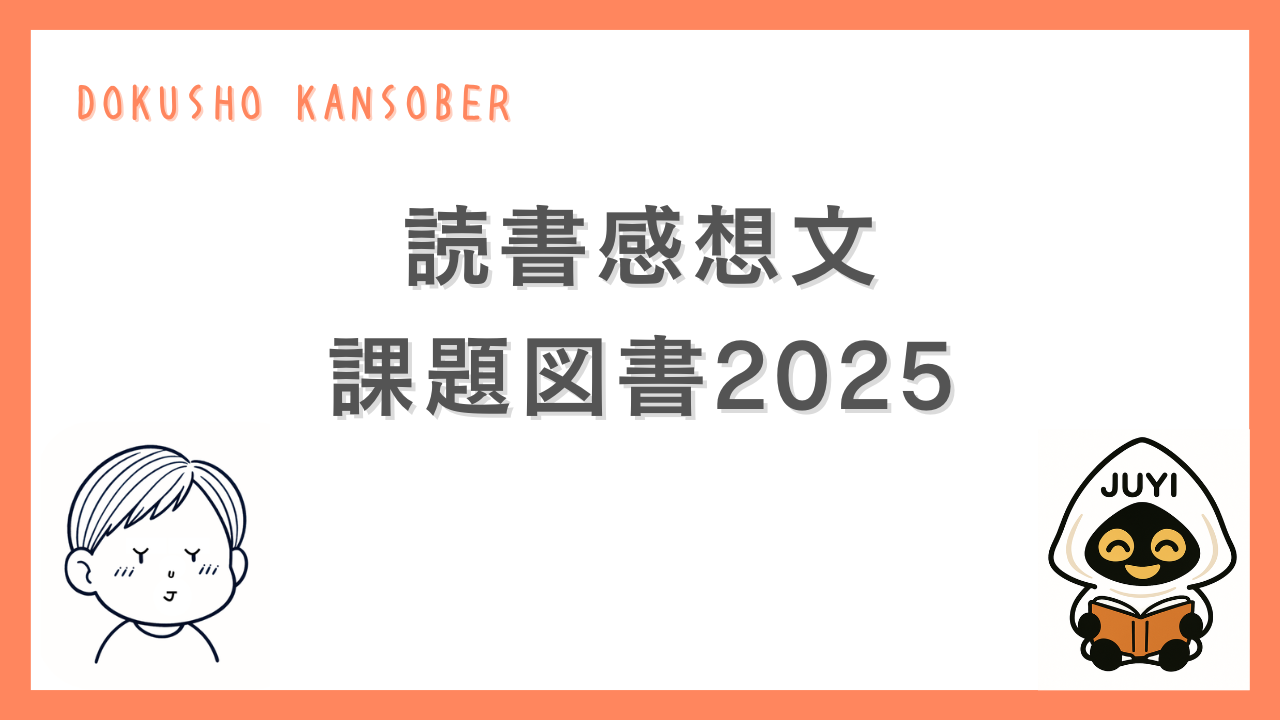






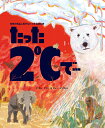









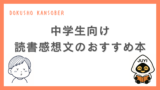



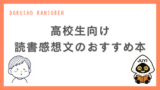
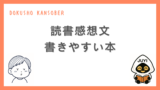
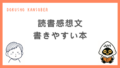

コメント